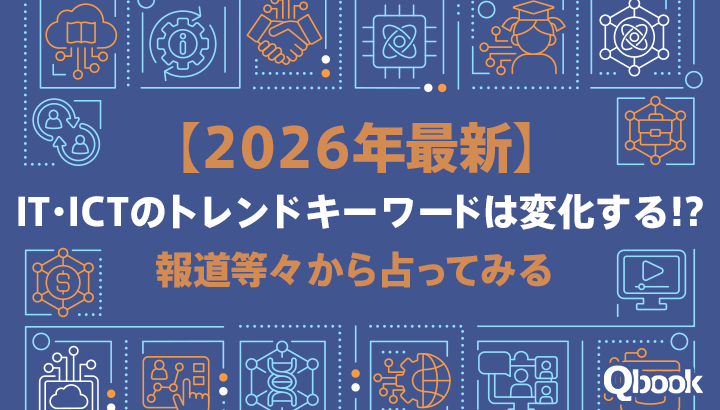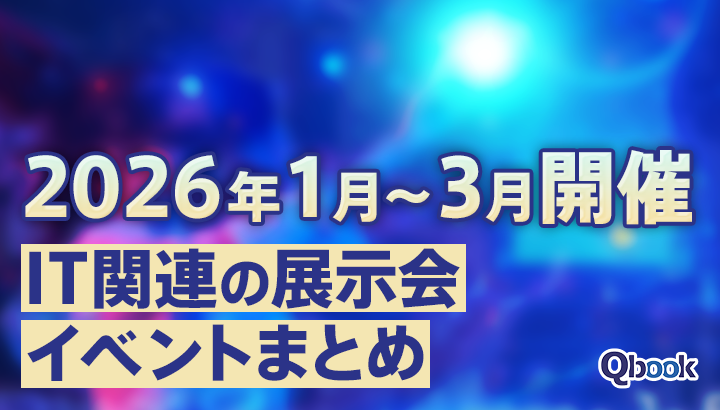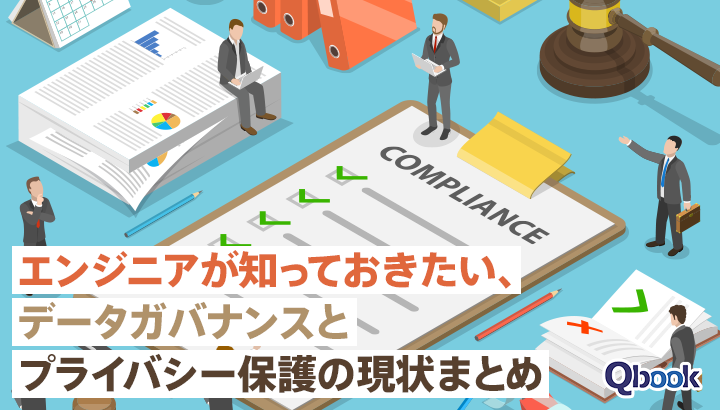「暗号」という言葉に、どんなイメージを持っていますか?ミステリーなどに登場する秘密のメッセージを思い浮かべる人も多いかもしれません。
実は、現代の暗号技術は、そういった「秘密のメッセージ」を超えた、私たちの日常生活を支えるインフラのような働きをしています。
インターネットショッピングやスマホ決済など、暗号技術は情報の安全を守るために使われています。そこで今回は、暗号技術の基本や歴史などをまとめてみました。
- もくじ
1. 暗号技術とは?基本情報と重要性
1-1. 暗号は情報を「守る」ための技術
暗号技術とは、情報を第三者から「隠す」だけでなく、「守る」ための仕組みです。歴史的に見ると、もともと暗号の主な目的は、他人に読まれたくないメッセージを第三者にわからないようにする「隠す」ことでした。
しかし、現代の暗号技術は、ただ隠すだけでなく、情報が改ざんされていないことを保証したり、送信者や受信者が本当に正しい相手かどうかを確認したりするなど情報そのものの安全を守る役割も担っています。「隠す」から、「壊されない」「すり替えられない」ように「守る」技術へと進化してきたといえるでしょう。
1-2. 情報に「鍵」をかける
暗号技術の基本は、情報に「鍵」をかけることです。
例えば、金庫に大事なものをしまって鍵をかけ、他人が勝手に開けられなくするように、デジタル情報にも「鍵」をかけて、許可された人だけが中身を見たり使ったりできるようにします。この「鍵」は、数字や記号の組み合わせでできていて、正しい鍵を持っている人だけが情報を「開ける」ことができます。逆に、鍵がなければ、たとえ情報自体を手に入れても、中身を知ることはできません。これが暗号技術の基本的な考え方です。
1-3. 「暗号化」と「復号」の基本的な流れ
そして、暗号技術の中心となるのが「暗号化」と「復号」です。まず、送りたい情報(「平文」といわれます)を、特定のルールと鍵を使って「暗号文」に変換します。これが「暗号化」です。
暗号文は、たとえ他人に見られても内容がわからないようになっています。そして、受け取った人は、正しい鍵を使って暗号文を元の情報(平文)に戻します。これが「復号」です。この流れで、情報が安全にやりとりできるわけです。
1-4. 現代における暗号化の重要性
現代では、インターネットを通じて膨大な情報がやりとりされています。もし、これらの情報が暗号化されていなければ、悪意のある第三者が簡単に盗み見たり、改ざんしたりすることができてしまいます。
とくにクレジットカード番号やパスワード、個人情報などが漏れてしまうのは恐怖でしかありません。当然、金銭的な被害やプライバシーの侵害につながってしまいます。
例えば、カフェや駅などの公共Wi-Fiを使う場合、通信が暗号化されていないと、同じネットワークに接続した誰かがあなたの通信内容を盗み見ることができてしまいます。また、ネット上でデータを送受信する際、途中で誰かがデータを書き換える(改ざんする)こともあり得ます。
暗号化によって、こうした危険から私たちの大切な情報が守られます。その意味で、暗号化は情報化社会において必須な技術といってよいでしょう。
2. 暗号技術の歴史~古代から現代まで~
2-1. 古代の暗号技術
ここで、暗号への理解を深めるため、暗号の歴史を代表例から見ていきましょう。
暗号の歴史は非常に古く、紀元前の時代から使われています。太古からという説もあるほどですが真偽はわかりません。
紀元前で有名なのが「シーザー暗号」でしょう。これは古代ローマのシーザー(カエサル)が使っていた暗号で、アルファベットを一定の文字数だけずらして書き換えるというシンプルな方法です。例えば、「A」を「D」に、「B」を「E」にする、といった具合です。現在では子ども向けのクイズでも見かけますが、当時は意外に解読が難しかったと考えられています。
古代ギリシャでは「スキュタレー」と呼ばれる道具も使われていました。これは細長い帯に文字を書き、それを特定の太さの棒に巻き付けて読むことで意味がわかるようにする暗号です。正しい道具(=鍵)を使って解読できるようにする仕組みは、古くから使われてきたことになります。
ほかにも、中世ヨーロッパの「ヴィジュネル暗号」など、さまざまな暗号が考案されてきました。これらは主に、政治や軍事の機密通信に使われました。
2-2. 「エニグマ」と「ナバホコード」
近代に入ると、暗号技術はさらに進化します。第二次世界大戦では、ドイツ軍の「エニグマ暗号機(Enigma)」が有名です。
これは非常に複雑な機械式の暗号装置で、当時は「絶対に解読できない」と考えられていましたが、イギリスの数学者アラン・チューリング氏らの活躍によって解読されています。
このときのチューリング氏の活動は『イミテーション・ゲーム』として映画化されました。他にも『エニグマ』(2001年)など複数、映画化されており、小説などの題材にもなっています。
アメリカ軍が使った「ナバホコード」もよく知られています。文字がなかったアメリカ先住民ナバホ族の言語を通信に使う方法で、言語を知らない人にはまったく意味が通じませんでした。
ナバホ語の語彙を軍事用に応用し、例えば「爆撃機」は「鉄の鳥」、「潜水艦」は「魚の鉄の家」などと表したり、英語のアルファベットの各文字をナバホ語の単語で表現する方式も用いたりして、体系的に符号化して、通信を行っていました。
このように「言語そのものを暗号にする」発想は、その後の暗号技術に新しい方向性を示したとされています。
2-3. コンピュータ時代の到来と現代の暗号
戦後、コンピュータの登場によって暗号技術は飛躍的に発展します。手作業では到底できない複雑な計算ができるようになり、暗号の仕組みも格段に高度化します。
そして、コンピュータの膨大な計算能力を背景にした数学的な理論に基づいた暗号が主流となっていきます。
1970年代には「共通鍵暗号」や「公開鍵暗号」といった新しい方式が登場し、現代のデジタル社会を支える基盤となりました。共通鍵暗号方式のDES(Data Encryption Standard)やAES(Advanced Encryption Standard)といった、複雑な手順でデータを変換するブロック暗号が登場したほか、1980年代には、より安全性の高い「RSA」と呼ばれる公開鍵暗号方式も登場しました。
これはインターネット時代に不可欠な技術となり、今日まで活用され続けています。
通信技術が進歩し、誰もがインターネットやスマートフォンを活用する時代になると、人々の身近な生活の中で暗号技術が普通に使われるようになっていきます。
次第に暗号技術は「国家の機密を守るための道具」としてだけでなく、「誰もが安心安全に情報を扱うためのインフラ」としても利用されるようになってきたことになります。
3. 暗号技術の種類
ここでは簡単に暗号技術の種類をご紹介します。
3-1. 「共通鍵」暗号と「公開鍵」暗号
現代の暗号技術には、大きく分けて「共通鍵暗号」と「公開鍵暗号」の2種類があります。
「共通鍵暗号」は、暗号化と復号に同じ鍵を使う方式です。例えば、家族だけが知っている合言葉のように、送り手と受け手が同じ鍵を持っていなければなりません。処理が早く、実用性も高いのですが、鍵の受け渡しにリスクが伴うという問題もあります。
一方、「公開鍵暗号」は、暗号化に使う「公開鍵」と、復号に使う「秘密鍵」が別々になっています。公開鍵は誰でも知ることができ、秘密鍵だけが本人しか持っていません。相手は公開鍵を使って暗号化し、自分だけが秘密鍵で復号する。これにより、鍵のやりとりの手間やリスクを大きく減らすことができるわけです。
この「鍵のペア」によって安全な通信を実現する仕組みは、インターネットのような不特定多数が利用する場面ではとくに欠かせないとされています。Wi-Fiの接続などで、よくお世話になっている方も多いのではないでしょうか。
3-2. 「ハッシュ関数」はデジタル指紋
「ハッシュ関数」とは、任意のデータから「固定長の文字列」を作り出す仕組みです。例えば、どんな長さの文章でも、ハッシュ関数を通すと「32文字の英数字」など決まった長さの値になります。
この値は「ハッシュ値」と呼ばれ、まるでデジタルの「指紋」のように、元のデータが少しでも変わるとまったく違う値になります。
ハッシュ関数は、データの改ざん検出によく使われます。
例えば、あるファイルをダウンロードした際に、提供元が公開しているそのファイルのハッシュ値と、自分でダウンロードしたファイルのハッシュ値を比較することで、ファイルがダウンロード中に改ざんされていないかを確認できます。パスワードの保存や、データが改ざんされていないか確認するためなど、さまざまな場面で使われています。
3-3. 「デジタル署名」が重要になる
インターネット上で「この情報が本当に本人から送られてきたものか」を証明するために使われるのが「デジタル署名」です。これは、送信者が自分だけの秘密鍵でデータに署名(サイン)をし、受信者は公開鍵を使ってその正しさを確認する仕組みです。
デジタル署名は、紙の書類に押す印鑑やサインのような役割をデジタルの世界で実現するものです。これを利用することで、以下の二つのことを確認できます。
送信者の認証
その情報が本当に名義人本人から送られたものであること。
データの非改ざん性
情報が送信されてから受け取るまでの間に改ざんされていないこと。
デジタル署名は、主に公開鍵暗号とハッシュ関数を組み合わせて実現されています。デジタル署名があることで、「なりすまし」や「改ざん」を防ぎ、安心して電子メールやメッセージ、電子契約をやりとりできるようになります。
4. 暗号技術がつかわれている事例
4-1. インターネットショッピング
ネットショッピングでクレジットカード番号などを入力するとき、画面のURLが「https」から始まっていると思います。これは「SSL/TLS」という暗号化技術が使われているためです。
SSL(Secure Sockets Layer)およびTLS(Transport Layer Security)は、Webブラウザとサーバー間の通信を暗号化し、情報の漏洩や改ざんを防ぐ技術です。
簡単に言えば、通信のトンネルを作って、外から中身が見えないようにしているイメージです。SSL/TLSでは、公開鍵暗号方式を使って安全に共通鍵を交換し、その後の実際のデータ通信は高速な共通鍵暗号方式で行われます。
SSL/TLSは、インターネット上でやりとりされる情報を暗号化し、第三者が盗み見たり改ざんしたりできないように守っています。これにより、私たちは安心してオンライン決済を利用できるのです。
4-2. スマホ決済と仮想通貨
スマートフォンでのキャッシュレス決済や、仮想通貨の取引にも暗号技術が欠かせません。
スマホ決済では、個人情報や決済情報がスマートフォンと決済サービス提供者の間で安全にやりとりされる必要があります。
ここでも、通信の暗号化はもちろん、デジタル署名といった暗号技術が活用されています。Apple PayやGoogle Pay、交通系ICカードといった非接触型決済では、カードの情報そのものを直接送らず、暗号化された「トークン」を使って取引を行っています。これにより、実際のカード情報が盗まれるリスクを低減しているのです。
ビットコインなどの仮想通貨の取引には「ブロックチェーン」と呼ばれる技術が使われています。
ブロックチェーンは取引の記録を分散して管理し、不正な書き換えを防ぐ仕組みで、たいへん重要な技術です。ブロックチェーンは、仮想通貨だけでなく、さまざまな分野で安全な取引やデータ管理に活用されるようになっています。
4-3. 行政のデジタル化とマイナンバー
行政サービスのデジタル化が進む中、個人情報の保護も重要な課題となっています。日本の「マイナンバー制度」では、個人情報が厳重に暗号化され、外部からの不正アクセスや情報漏洩を防ぐ仕組みが導入されています。
マイナンバーカードにはICチップが搭載されていて、これにより本人確認や電子署名ができるようになっています。
例えば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)では、マイナンバーカードを使って電子申告を行うことができますが、ここに暗号技術が使われています。暗号技術によって、行政手続きのオンライン化が進み利便性が向上しています。
4-4. SNSとエンドツーエンド暗号化
LINEやWhatsAppなどのSNSアプリの多くには「エンドツーエンド暗号化」が導入されています。
これは、メッセージが送信者から受信者まで暗号化され、途中で運営会社や第三者が内容を見られないようにする仕組みです。
これにより、友人や家族とのやり取りが、サービス提供者を含む第三者に見られることなく、安全に行えるようになります。プライバシーを守り、安全にコミュニケーションできる環境を実現しているのです。
5. 暗号技術の未来
暗号技術は今後も進化を続けていくでしょう。今後、とくに注目されているのが「量子コンピュータ」の登場です。なぜなら、高性能な量子コンピュータが実用化されると、現在の公開鍵暗号方式が簡単に解読されてしまう可能性があるからです。
これに対抗するため、「量子暗号」や「ポスト量子暗号」と呼ばれる新しい暗号方式の研究が進んでいます。「量子暗号」は、量子力学の原理を利用して、理論的に絶対安全な通信を目指すものです。量子暗号は非常に高い安全性を持ちますが、現在のところ、長距離の通信や複数の拠点間でのネットワーク構築には技術的な課題があるとされています。
「ポスト量子暗号」は、量子コンピュータでも解読が難しい新しい数学的手法を使った暗号です。従来のコンピュータでも実装でき、かつ量子コンピュータでも効率的に解くことが難しいとされている数学的な問題に基づいています。いずれ現在の公開鍵暗号方式は「ポスト量子暗号」に置き換えられていくと考えられています。
こういった新しい暗号技術の動向には注目したいところです。
まとめ
暗号技術は、現代社会のインフラとして私たちの生活を支えています。
今では、インターネットショッピングやスマホ決済、行政サービスなど、あらゆる場面で情報の安全を守る重要な役割を果たしています。
量子コンピュータの時代に向けて新たな暗号技術も研究されています。デジタル社会を安全に生きるために、暗号技術の基礎を知ることは日々の生活を送るうえでも重要です。
今後も技術の進化に目を向け、安全な選択をするよう心がけたいものです。