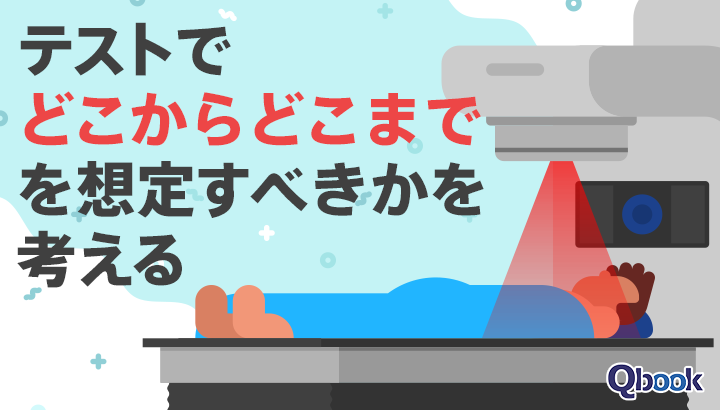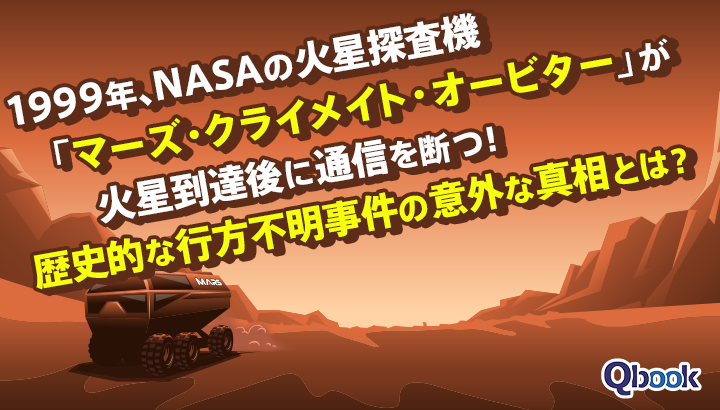日常を気軽にSNSでシェアする行為が、思わぬ落とし穴になることがあるのをご存知ですか?
「モザイクアプローチ」という手法を使うと、「何も個人情報は掲載していない」と思える投稿から個人を特定できてしまう恐ろしいことが起こり得るのです。
そこで、今回は実際に起きた事件の例や、今や一般人も標的となる現状を踏まえて、私たちがどのように自分の情報を守ればよいのかまとめてみました。
1. 「モザイクアプローチ」とは何か?
1-1. SNS時代の新たな個人情報特定手法のこと
SNSが普及して、誰もが気軽に日常の出来事や趣味、思ったことなどを発信できるようになりました。しかし、その裏で「モザイクアプローチ」と呼ばれる新たな個人情報特定手法が広がっています。
モザイクアプローチとは、SNSやブログ、動画投稿サイトなどに散在する断片的な情報を複数組み合わせることで、個人を特定する技術や方法のことです。
例えば、投稿した写真に写り込んでいる背景や、つぶやきの内容、プロフィール情報など、一つひとつは無害に見える情報でも、いくつも小さな情報を集めてつなぎ合わせることで、居住地や勤務先、行動パターンなどが浮かび上がってしまうのがモザイクアプローチです。
まるで名探偵のように、防犯や調査の分野で使われることもありますが、逆に、犯罪目的で悪用されてしまうケースも近年増加しているのです。
1-2. なぜモザイクアプローチが危険なのか
モザイクアプローチが危険視される最大の理由は、「自分では個人情報を出していないつもり」でも、断片的な情報が積み重なって、思わぬ形で知られたくない個人情報が特定されてしまう点にあります。
SNSの投稿は、友人やフォロワー以外にも公開されていることが多く、第三者でも容易に情報収集できてしまいます。これは、私たちが気づかないうちにリスクに晒されていることを示す、目に見えない怖さともいえるでしょう。
特に注意したいのは、顔や風景が映り込んだ写真、習慣的な投稿内容、使用するハッシュタグなどです。
何気なく投稿した情報でも、断片的なデータを集めてつなぎ合わせる「モザイクアプローチ」によって、あなたの自宅や職場が特定される危険があります。個人情報がジグソーパズルのように組み合わされることで、ストーカーなど悪意のある人物によるプライバシー侵害のリスクが高まってしまうのです。
しかも、モザイクアプローチの怖さは、特定の専門知識がなくても、誰でも簡単に情報収集ができてしまうことにあります。現代のネット社会の「怪談」といってよいかもしれません。
1-3. 断片的な情報が組み合わさるとどうなる?
モザイクアプローチの怖さは、情報量はもちろんありますが、量よりも「組み合わせ方」で情報が特定できてしまうことです。一例ですが、以下のような情報がネット上に出回っていたとしましょう。
- 通勤途中に撮ったと思われる駅のホーム写真
- 平日、毎朝投稿される「おはようツイート」
- 週末によく登場するショッピングモール名
- 自宅の窓から見える風景
これらは単体では何の問題もない、他愛のない投稿といってよいでしょう。
しかし、ある程度の心得がある人が見れば、通勤経路や自宅の位置を割り出す材料になってしまいます。投稿の時間帯や頻度から生活リズムまで推測されることもあり、本人が意図しない形で個人情報が外部に漏れ、待ち伏せされる可能性すらあります。
最近は、こうした情報の「つなぎ合わせ」が、AIや検索エンジンの進化によってさらに容易になっているようです。
2. 実際に起きた事件から学ぶモザイクアプローチの脅威
2-1. 2019年「アイドルストーカー事件」
2019年、ある女性アイドルが自宅を特定され、ストーカー被害にあう事件が発生しました。
犯人は、なんとアイドルがSNSに投稿した自撮り写真の瞳に映り込んだ風景を拡大して、周辺の建物や駅名などの情報をもとに居住地を割り出したとされています。
技術の進歩で、自撮り写真の「瞳」に映った数ミリの画像情報でも、拡大や補正によって多くの手がかりが得られてしまうとは、現代の技術の怖い一面を見せつけられました。
この事件で、日常の何気ない投稿が、思わぬ形で個人を危険にさらすことを世間に強く印象づけたのではないでしょうか。
2-2. 有名YouTuberのストーカー事件の教訓
2017年には、有名YouTuberが、モザイクアプローチによるストーカー被害にあい、話題になりました。
有名YouTuberが投稿した動画やSNSの写真、発言内容などから、ファンが自宅を特定してしまい、無断で訪問する事件が発生しました。
YouTuberという職業柄、多くの情報発信を行っているため、情報の断片が多く存在しました。犯人はこれらの情報を収集・分析して、情報の断片を組み合わせて彼の自宅を割り出したことになります。
この事件も、特定の決定的な情報があったわけではなく、さまざまな断片的な情報がモザイクのように組み合わされることで個人特定に至ったモザイクアプローチの典型的な事例といえるでしょう。
2-3. 企業も標的に
モザイクアプローチの脅威は、個人だけでなく企業や公的機関にも及んでいます。
例えば、社員がSNSに投稿したオフィスの写真や、社内イベントの様子、業務に関する何気ないつぶやきが、外部の人間によって組み合わされ、企業の内部情報が特定されてしまうケースです。
企業の場合、広報などで発信されている公開情報がありますので、比較的、時間の特定が素早くできる「時系列」のヒントがあります。
そのため、職場の一部の風景や、写り込んでいるモノ、社内イベントに関する情報や「つぶやき」などが組み合わされることで企業の内部事情やプロジェクトの進行状況などが推測されてしまう可能性があるわけです。
以下の記事は、情報が組み合わせというより「単独の漏洩事例」事例ですが、モザイクアプローチのリスクを理解する参考となるでしょう。
2-4. すでに一般人も標的に......
かつては著名人や企業が主なターゲットでしたが、現在では一般のSNS利用者もモザイクアプローチの標的となっています。
トラブルの内容的に、具体的な報道事例は少ないようですが、SNSに投稿した写真や位置情報をもとに、住所や勤務先を特定され、脅迫や嫌がらせを受ける事件が発生しているとテレビの報道番組などで報じられています。
3. モザイクアプローチから身を守るには?
3-1. 個人情報の「カケラ」に注意する
SNSに投稿する前に、まず「この情報で自分が特定される可能性はないか?」と考える習慣をつけてみましょう。以下のようなポイントがあります。
位置情報の確認
スマートフォンで撮影した写真や動画には、撮影場所のGPS情報が付加されている場合があるので、写真に位置情報が含まれていないか確認し、必要に応じて削除します。
また、利用しているSNSの機能を調べて、投稿時にGPS情報が自動的に削除する機能が付いているかも確認しておくと安心です。
しかし、著名なランドマーク、例えば東京ドームで撮影した写真は、GPSがonでもoffでも「バレバレ」のため、情報の重要度にも配慮が必要です。逆にいうと、個人が特定されそうな場所では注意が必要ということになります。
写真の背景チェック
投稿前に写真や動画に写り込んだ背景を確認しましょう。自宅や職場の窓から見える景色、近所の建物、駅やお店の外観、表札、郵便物など、個人を特定できる情報が写り込んでいないか注意が必要です。とくに反射物(窓ガラスや鏡、瞳など)への映り込みには気をつけましょう。
持ち物や服装
制服や名札、個人名が入った持ち物、定期券、クレジットカード、車のナンバープレートなど、個人情報が特定できるものが写っていないか確認すると安心です。
投稿内容と頻度、タイミング
「〇〇駅にて」「△△カフェでお茶」といったリアルタイムの投稿や、「毎週金曜日は習い事」といった定期的な行動を示す投稿は、行動パターンを特定されるリスクがあるので気をつけましょう。
また、一人暮らしの方が「今、旅行中」とリアルタイムで(結果的に)留守情報を発信してしまうと、空き巣などの犯罪リスクが高まるという指摘もあります。
3-2. デジタルフットプリントを最小限に抑える方法
上記で確認したような、個人情報の「カケラ」を「デジタルフットプリント(ネット上に残る足跡)」といいます。デジタルフットプリントを残していないか意識しておくとよいでしょう。基本は「必要以上に情報を公開しない」ことです。基本対策は以下のようになります。
不要なアカウントの削除
使用していないSNSアカウントやウェブサイトの会員登録など、不要なオンラインアカウントは削除しましょう。とくに、他の会員に見られるものは気をつけます。情報が古いまま放置されているアカウントが過去のデジタルフットプリントとして利用されてしまう可能性が指摘されています。
プロフィール情報の見直し
公開されているプロフィール欄には本名や住所、電話番号などの個人情報を記載しない方がよいかもしれません。必要最低限の情報だけを公開することを検討してください。
情報発信を計画的にする
必要以上に多くの情報やプライベートな情報をインターネット上に公開しない方がよいでしょう。特に、自分以外の人物を特定できるような情報の公開には、慎重になる必要があります。周囲の人を巻き込まない注意が必要な時代になったといえるかもしれません。
3-1、3-2の対策を組み合わせることで、デジタルフットプリントを最小限に抑えられます。それにより、モザイクアプローチによる個人特定のリスクを減らすことができるのではないでしょうか。
3-3. プライバシー設定を見直しておく
SNSには、投稿の公開範囲やフォロワーの管理、タグ付けの許可設定など、さまざまなプライバシー設定があります。これらを適切に設定することで、個人情報の流出リスクを減らすことができます。
SNSの公開範囲設定
あなたの投稿やプロフィール情報を誰に見せるか、設定できるSNSがほとんどです。
「全体公開」になっている情報を「友達のみ」や「特定の人だけ」に変更するなど、公開範囲を調整しましょう。過去の投稿についても、公開範囲を見直すとよいでしょう。
タグ付け設定
他のユーザーがあなたを写真や投稿にタグ付けできる設定を見直すことも考えてみましょう。タグ付けされることで、意図しない形でモザイクアプローチが発動してしまう可能性があるためです。タグ付けされた場合に通知を受け取る設定にしたり、手動で承認するように設定を変更したりすることもできます。
これらのプライバシー設定は、一度設定すれば終わりではありません。SNSやサービスのアップデートによって設定項目が変わることもありますので、定期的に見直して、自分が望む公開範囲になっているか確認しておくことがポイントです。
3-4. 企業ではどう気をつけたらいいか?
企業の場合、社員一人ひとりのSNS利用が情報漏洩のリスクにつながるため、社内での「ガイドライン策定」や「セキュリティ教育」が不可欠といえます。
ガイドラインの策定
業務に関連する情報発信や、個人のSNS利用における注意点などを明確にしたガイドラインを策定しておくと安心です。
セキュリティ教育
情報発信における注意点やセキュリティについて、定期的な教育を実施することが推奨されています。
情報公開の「レベル」設定
公式ウェブサイトやプレスリリース、SNSなどで公開する情報レベルを、情報漏洩につながらないよう事前に検討しておくと運用が楽になります。
例えば、詳細すぎる社内写真や、特定の人物が特定できるような情報の公開をしないように決めておくとよいでしょう。
モニタリング体制の構築
何か問題があれば迅速に対応できる仕組みを作っておくことも重要です。プライバシーに配慮しつつ、企業のセキュリティを守るバランスの取れた対策が求められます。
企業全体でセキュリティ意識を高め、従業員一人ひとりが情報管理の重要性を理解し実践することで、モザイクアプローチなどによる情報漏洩被害を最小限に抑えることができます。
4. モザイクアプローチの未来
4-1. AIと画像認識技術の発展がもたらす「新たな脅威」
近年、AI(人工知能)や画像認識技術の進化により、モザイクアプローチの危険性はさらに高まっている可能性があります。なぜなら、AIは大量の画像やテキストデータから特徴を抽出して、断片的な情報を高速かつ正確に組み合わせることが可能だからです。
例えば、SNSに投稿された写真から、AIが背景や人物、物体を自動的に認識し、位置情報や生活パターンを割り出すことも技術的には難しくなくなってきているように思われます。また、画像認識技術の精度向上により、写真や動画に写り込んだ背景や物体から、より正確な場所や状況を特定することができるようになるでしょう。
恐ろしい話ですが、今後は、AIによる自動的なデジタルフットプリント収集による個人特定や、悪意ある情報収集が巧妙化してしまう可能性が否定できないでしょう。
4-2. ビッグデータ時代における個人情報保護の課題
ビッグデータの活用が進む現代社会では、個人の行動履歴や購買履歴、位置情報など、膨大なデータが日々蓄積されています。これらの情報が組み合わされることで、個人の嗜好や生活パターン、交友関係までが詳細に分析されてしまうリスクがあります。
例えば、複数の企業のサービス利用履歴や位置情報データを組み合わせることで、個人の行動パターンや生活習慣が詳細に把握されてしまう可能性があります。これらの情報が悪意を持って利用されれば、個人の特定はもちろんのこと、その人の弱みや行動を先読みするといった、より悪質な行為につながることも考えられます。
ビッグデータを活用すること自体の全てが悪いわけではありませんが、個人情報保護とのバランスをどのように取るのかが、現代社会における大きな課題となっているといってよいでしょう。
4-3. 法整備と技術開発。社会全体での取り組みの必要性
ここまで見てきたように、モザイクアプローチによる個人特定のリスクを減らすためには、個人の努力だけでなく、社会全体での対策が欠かせません。そのために重要なのが、「法整備」と「技術開発」です。
日本では、個人情報保護法の改正により、個人情報の定義や取り扱いに関する規定が強化されています。しかしながら、現行の法律では、断片的な情報収集・分析といった行為そのものを明確に規制することが難しいという課題も指摘されています。
モザイクアプローチが悪用されるケースが増加している現状を踏まえ、個人情報保護に関する法制度がさらに整備されるとよいのではないかと考えます。
また、技術開発も重要です。モザイクアプローチによる個人特定の試みを検知・防御するための技術や、プライバシーを保護しながらデータを活用できるような技術の開発が求められています。プライバシー保護技術の研究開発も進んでいるようなので、今後の発展に期待したいです。
5. まとめ
モザイクアプローチとは、SNSやブログ、動画投稿サイトなどに断片的に存在する、一見無害に見える情報を集めて組み合わせ、個人を特定する手法を指します。
SNSの普及とともに、モザイクアプローチによる個人情報漏洩のリスクが急速に高まっています。
断片的な情報の積み重ねが、思わぬ形でプライバシーを脅かす時代になりました。企業も個人も安全なネット利用のために、投稿前の情報チェックやプライバシー設定の見直しに気をつけたいですね。