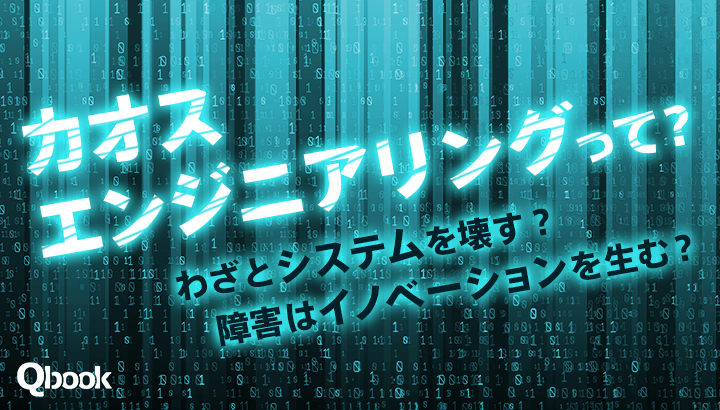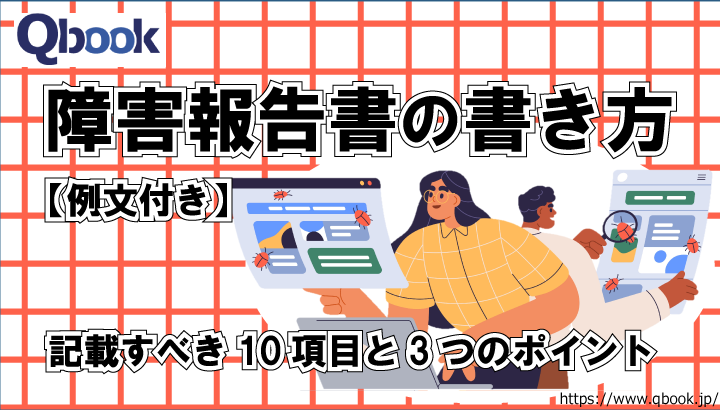現代のITシステムは、クラウドやマイクロサービスの普及によって、かつてないほど複雑になっています。ユーザーが使うアプリやサービスは便利になった一方で、裏側では「予期せぬ障害」がいつ起きてもおかしくない状況です。そんなリスクに立ち向かう手法として注目されているのが「カオスエンジニアリング」です。一見すると「わざと壊す」ように思えるこの考え方は、実はシステムをより強く、信頼できるものに育てるためのアプローチです。そこで今回は誕生の背景から実際の事例と実践ポイントの基本までをまとめました。
- もくじ
1. カオスエンジニアリングとは何か?
1-1. 「意図的な障害」でシステムを鍛える
「カオスエンジニアリング」とは、システムに意図的に障害を発生させ、その影響を観察・分析することで弱点を見つけ出し、改善につなげる手法のことです。普通であれば、エンジニアは障害を避けようとします。しかし、現実には障害はゼロにできません。そこで逆転の発想として「起こる前提で準備する」ために、あえて自ら障害を仕掛けるのです。
例えば、稼働中のサーバーをランダムに停止させてみたり、ネットワークを意図的に遅延させたりします。すると「どこで不具合が連鎖的に広がるのか」「どの部分がボトルネックになるのか」が見えてきます。結果として、実際に本番で障害が起きた時にも迅速に対処できる耐性が身につくというわけです。
これは、人間がワクチンを接種する行為に似ているかもしれません。ワクチンは、無毒化あるいは弱毒化した病原体をあえて体内に注入することで、免疫システムを刺激し、本物の病原体が侵入してきた際に備えるためのものです。同様に、カオスエンジニアリングも、制御された小規模な「偽の障害」をシステムに経験させることで、将来起こりうる大規模で未知の障害に対する「免疫」を獲得させることを目的としている......といったイメージです。
1-2. 「障害は必ず起こるもの」という前提に立つ
従来のIT運用では、「障害を防ぐこと」が最重要課題※でした。しかしクラウドや分散システムの時代になると、ハードウェアの故障やネットワークの断絶、外部サービスの停止など、避けられないトラブルが無数に存在します。
カオスエンジニアリングは「障害は必ず起こるもの」という前提から出発しています。そして、起きた時にいかに被害を最小限に抑えるか、ユーザーに気づかせないようにサービスを維持するかを重視します。つまり、防御一辺倒ではなく「攻めの備え」をするのです。この考え方が、多くの企業で注目を集めている理由です。
以前のシステム開発・運用における品質保証は、「障害をいかにして防ぐか」という視点が中心でした。テストを入念に行い、バグを一つ残らず潰し、完璧な状態でリリースすることを目指します。もちろん、この考え方は今でも非常に重要です。しかし、現代の複雑化したシステムにおいて、すべての障害を100%未然に防ぐことは、もはや不可能に近いこともまた事実ではないでしょうか。
1-3. 分散システムにおける「予期せぬ」課題の正体
マイクロサービスやクラウドを利用した分散システムは、一見するとスケーラブルで効率的です。しかし、複数のサービスが相互に依存するため、どこか一つが不調になると連鎖的に障害が広がることがあります。
例えば、ユーザーがECサイトで商品を購入する流れを考えてみましょう。ログイン、商品検索、カート、決済、在庫確認といった機能がそれぞれ独立したサービスになっている場合、その一つが落ちただけで全体の体験が壊れてしまいます。しかも、問題が表面化するまでに時間がかかり、気づいた時には影響範囲が拡大しているケースもありえます。
かつてのシステムは、一つの巨大なコンピュータ(サーバー)の中で、すべての機能が一体となって動く「モノリシックアーキテクチャ(Monolithic Architecture)」が主流でした。これは、構成がシンプルな反面、一部の機能修正が全体に影響を及ぼしやすく、柔軟性に欠けるという課題がありました。
これに対し、現代では「マイクロサービスアーキテクチャ(Microservices architecture)」に代表される分散システムが広く採用されています。無数のサービスが複雑に連携し合う分散システムでは、個々のサービス単体では何の問題もなくても、それらが相互作用する中で、開発者の想定をはるかに超えた予期せぬ振る舞いが発生することがあります。
「予期せぬ課題」の正体は、この複雑な依存関係にあります。だからこそ、あえて障害を発生させてシステム全体の振る舞いを観察し、未知のリスクを洗い出すことが重要なのです。
2. カオスエンジニアリングの歩みと主要事例
2-1. Netflixと大規模障害の教訓
カオスエンジニアリングが世に広まるはじまりは、動画配信サービスの『Netflix』でした。
2008年、同社は大規模なデータベースの障害により長時間のサービス停止を経験しました。この出来事を契機に「障害は必ず起こる」という前提を受け入れ、一つの故障がシステム全体の停止につながる箇所(単一障害点=SPOF)を持つ自社のデータセンターは危険だという認識を持ってクラウド(AWS:Amazon Web Services)への全面移行を進めると同時に、新たな運用手法を模索することになりました。
クラウドへの移行は、単一障害点のリスクを低減させる一方で、新たな課題を生み出しました。それは、自社で物理的に管理できない、無数のサーバー(インスタンス)上でサービスを稼働させなければならないという現実です。そこで、Netflixはシステム全体の耐障害性を高めるために「わざと障害を発生させる」という実験を行いました。その結果として生まれたのがカオスエンジニアリングの原型ということになります。
2-2. 「Chaos Monkey」の誕生秘話
この過程で、Netflixが開発した代表的なツールが『Chaos Monkey(カオスモンキー)』です。これは、稼働中のサーバーをランダムに停止させるプログラムで、システムの弱点をあぶり出す役割を担います。
2010年に開発されたChaos Monkeyの役割は、非常にシンプルです。それは、AWS上で稼働しているNetflixのサービス群(サーバーインスタンス)を、白昼堂々、意図的に、そしてランダムに停止させて回るというものです。その名の通り、まるで猿(Monkey)がデータセンターで暴れ回る(Chaos)かのように、本番環境のコンポーネントを無作為に落としていくのです。
「サーバーが突然落ちたらサービスはどうなるのか?」――通常であれば恐ろしくて試せない実験を、日常的に行う仕組みを整えたのです。この取り組みによって、Netflixは障害に強いシステムを構築し、世界中のユーザーに安定したサービスを提供できるようになりました。
この過激なツールをあえて本番環境で動かし続けることで、エンジニアは常に「いつサーバーが落ちても大丈夫な設計」を意識せざるを得なくなります。Chaos Monkeyによる小さな障害を日常的に経験することで、システムは徐々に鍛えられ、いざという時の大規模な障害にも耐えうる、真の回復力(リカバリー能力)を身につけていきました。
2-3. 日本のパイオニア、クックパッドも実践
日本でも、カオスエンジニアリングを実践する企業が出てきています。その代表例がレシピサービスで知られるクックパッドです。同社は2010年代から分散システムの運用に取り組み、早い段階でカオスエンジニアリングを導入しました。
クックパッドは「本番環境で障害が起きた時にユーザーへ影響を与えないこと」を重視し、カオス実験を通じてシステムやチームの耐障害性を高めてきました。同社ではシステムが複雑化する中で、障害発生時にその影響範囲や原因の特定が困難になるという課題を抱えていました。
この課題に対応するため、2018年頃から本格的にカオスエンジニアリングの導入を開始しています。彼らのアプローチは非常に堅実で、まずは本番環境とほぼ同じ構成のステージング環境で、CPUに高い負荷をかける、サーバーを停止させるといった小規模な実験からスタートしました。国内企業としては先駆け的存在であり、その姿勢は他の企業にも刺激を与えています。
3. エンジニアが知っておくべき実践と効果
3-1. カオス実験の基本的なステップ
カオスエンジニアリングは、単にシステムを壊すだけではありません。実験には明確な手順があります。
一般的に、カオス実験は以下の4つの基本的なステップで構成されます。第一に、「定常状態の定義」です。これは、実験を行う前のシステムが「正常」である状態を、客観的な指標(メトリクス)で定義することからはじまります。例えば、「ウェブサイトのトップページは1秒以内に表示される」「秒間あたりのエラー発生率は0.01%未満である」といった、ビジネス上重要となる指標を具体的に数値化します。
第二に、「仮説の立案」です。定常状態を元に、「もし〇〇という障害が発生しても、システムの定常状態は維持されるだろう」という仮説を立てます。ここでのポイントは、楽観的な仮説を立てることです。例えば、「データベースサーバーの1台が停止しても、冗長化されているため、ユーザーの検索機能には影響が出ないはずだ」といった仮説を立てます。
第三に、「実験の設計と実行」です。立てた仮説を検証するため、実際の障害を模したイベントをシステムに注入します。データベースサーバーを1台停止させる、特定のサービス間のネットワークに遅延を発生させる、といった具体的なアクションです。この際、最も重要なのは「影響範囲を最小限に留める」ことです。
そして最後に、「結果の検証と学習」です。実験の結果、立てた仮説が正しかったのか、それとも覆されたのかを検証します。もし仮説通りにシステムが正常に稼働し続けたのであれば、そのシステムの耐障害性に対する自信を深めることができます。
この「仮説→実験→分析」というサイクルを繰り返すことで、システムは徐々に強化されていきます。逆に、仮説が覆され、想定外の問題が発生した場合、それはシステムの未知の弱点を発見できたことを意味します。この発見こそがカオスエンジニアリングの最大の価値であり、チームはこの結果を分析し、システムの恒久的な改善へとつなげていくのです。
3-2. ツールはあくまで手段
カオスエンジニアリングを支えるツールとしては、Netflixが公開した「Chaos Monkey」のほか、「Gremlin」や「Chaos Mesh」といったプロダクトも知られています。これらを使えば、複雑な障害シナリオを簡単に再現することができます。
Chaos Mesh: A Powerful Chaos Engineering Platform for Kubernetes
重要なのは、ツールはあくまで手段に過ぎないという点です。目的は「障害に強いシステムを作ること」であり、ツールを導入しただけでは意味がありません。実験の設計やチームの学びに重点を置く姿勢が求められます。ツールは、カオスエンジニアリングという文化を実践するための強力な武器ですが、それを使うエンジニアやチームの目的意識こそが、最も重要であることを理解しておく必要があります。
3-3. チームの耐障害性を高める
カオスエンジニアリングの効果は、システム面にとどまりません。チーム全体のインシデント対応力を高めることにもつながります。
実際の障害対応は、エンジニア個人の力量に依存しがちです。しかし、カオス実験を通じてチームで対応を訓練することで、誰が担当しても一定のレベルで解決できる体制を築けます。これは、ユーザーにとっても企業にとっても大きな安心材料となります。
予期せぬ障害は、エンジニアにとって大きなストレスとなります。深夜に鳴り響くアラート、原因がすぐには分からないエラー、復旧作業へのプレッシャー。こうした事態は、誰にとっても避けたいものです。しかし、カオスエンジニアリングを実践しているチームは、制御された安全な環境下で、障害対応の「訓練」を日常的に積むことができます。
意図的に引き起こされた障害に対応するプロセスを通じて、チームメンバーはインシデント発生時の適切なコミュニケーション方法を学びます。誰が指揮を執り、誰が調査を行い、誰が顧客へのアナウンスを担当するのか。こうした役割分担や連携を、本物の障害が起こる前にシミュレーションできるのです。
このような経験を積み重ねることは、エンジニア個人のスキルアップにつながるだけでなく、「障害は誰かの失敗ではなく、チームで乗り越えるべき課題である」という文化を醸成します。これにより、いざ本番環境で深刻な障害が発生した際にも、チームはパニックに陥ることなく、冷静かつ迅速に問題解決にあたることができるようになります。
3-4. 国内での導入事例の広がり
カオスエンジニアリングは国内でも広まりつつあり、クックパッド以外にも、ヤフー(Yahoo! JAPAN)などが積極的にカオスエンジニアリングを実施しています。
4. まとめ
カオスエンジニアリングは「わざと壊す」というユニークな発想で、システムと組織をより強靭にする手法です。Netflixの成功をきっかけに世界中へ広まり、日本でもクックパッドやヤフーなどが実践しています。実験のサイクルを通じて障害に強い仕組みを作り、チーム力も高められる――それが、このアプローチの最大の価値といえるでしょう。複雑化したシステムが急増する現代、「障害への備え」は守りであると同時に攻めの技術革新にもつながっています。