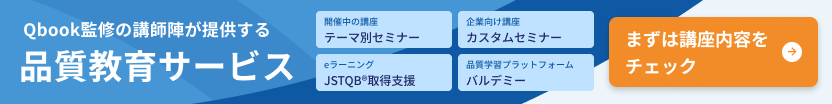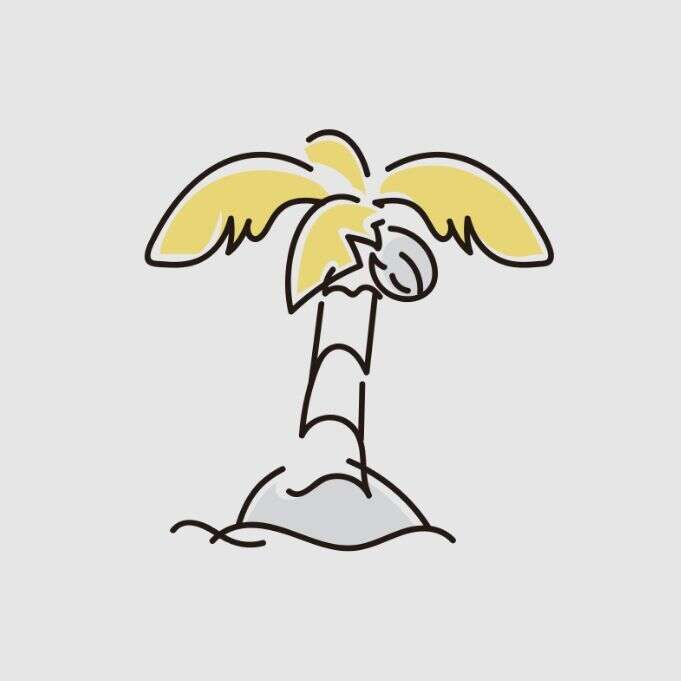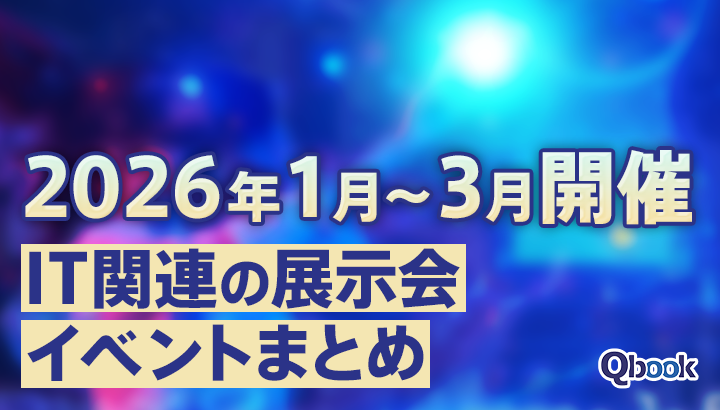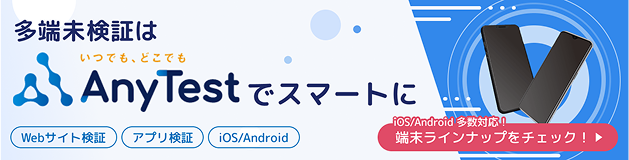2023年から2024年にかけて世界中を席巻した生成AIブームは、2025年には「とりあえず触ってみる」というフェーズを完全に終え、普通に利用されるツールとなりました。来る2026年は、AI技術が「驚き」の対象から「実用」の道具へと移行し、企業やエンジニアには「どうビジネスに組み込み、どう安全に回し続けるか」と活用面が問われる局面に入りそうです。
本記事では、2026年にエンジニアが避けて通れないキーワードを勝手にピックアップしてITトレンドを占い、現場のエンジニアがどのような課題と向き合うことになるのか、現在公開されている報道等から予測していきたいと思います。
1. 2026年も話題の中心は「AI関係」
1-1. 「エージェンティックAI」は現実化するか?
2026年の生成AIのトレンドにおいて、最も重要な変化は「チャットボットからエージェントへ」の進化が見られることではないかと思います。
これまで生成AIは、人間がプロンプト(指示)を入力して回答を返す「受動的」なツールで、「対話」が中心にありました。しかし、2026年により注目を集めるのは「エージェンティックAI(Agentic AI)」でしょう。
エージェンティックAIは目標を与えられると、自ら計画を立案し、必要なツールを選択して実行し、結果を確認しながら修正するというサイクルを自律的に回せるAIです。例えば、「来月、北海道への出張手配をして」と指示するだけで、フライトの検索、ホテルの予約、スケジュールの調整、経費精算の下書き作成等々を、複数のシステムと連携しながら遂行するイメージです。
調査会社Gartnerの予測によれば、2028年までに日常的な業務上の意思決定の少なくとも15%がAIエージェントによって自律的に行われるようになるといいます。同時に、2027年末までにエージェント型AIプロジェクトの40%以上が中止されると予測しているのも面白いと思います。
Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027
エンジニアにとっては、生成AIを単に「使う」だけでなく、「どこまで自律させるか」「どこで人間が承認するか」という権限設計や、AI同士の連携を管理するスキルが求められるようになっていくかもしれません。
1-2. 検索拡張生成=RAG(Retrieval-Augmented Generation)が広まる?
検索拡張生成(RAG = Retrieval-Augmented Generation)は、2026年には新しい技術用語としてよりも、企業による生成AI活用の基本となっていきそうな予感がします。
RAGは、簡単にいえば生成AIの精度を大幅に向上させる技術のことです。生成AIが回答を生成するとき、社内マニュアルやデータベースなどの外部情報を検索・参照します。これにより、広く浅く学んでいるLLM(大規模言語モデル)が学習していない最新情報や、企業固有の機密情報に基づいた正確な回答が可能になります。
すでに大手企業の一部では全社的なRAG基盤を導入していると報じられていますが、2026年にはこの動きが中堅・中小企業にも広がるかもしれません。
さらに技術面では、テキストだけでなく図面や画像、音声データなども検索対象とする「マルチモーダルRAG」が注目を集めるでしょう。AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」のリスクを抑え、回答に根拠を持たせる「グラウンディング」の信頼性が高まります。
エンジニアの役割は、RAGシステムの構築そのものから、「更新頻度の異なるデータをどう同期させるか」「機密情報をどうマスキングするか」といった、データパイプラインの設計とガバナンスの維持を含むものとなっていきそうです。
1-3. 「Private LLM」「Enterprise LLM」社内AIはどうなる?
ChatGPTなどのパブリックなAIサービスに社内データを入力することへの懸念から、2026年には「Private LLM(プライベートLLM)」や「Enterprise LLM」の導入が一般的な選択肢となる可能性があります。
これは、企業専用の環境にLLMを構築・運用するアプローチです。特に金融、医療、製造業など、機密情報の保護が最優先される業界では、外部ネットワークから遮断された環境や、特定の業務知識に特化してファインチューニング(追加学習)されたモデルが好まれる傾向が強まるでしょう。
IBMのwatsonxやNTTグループの取り組みなど、企業向けにセキュリティと日本語性能を強化したプラットフォームが充実していくことになりそうです。
また、コストと速度のバランスを考慮して適材適所が進む可能性もあります。定型的な処理や秘匿性の高いデータ処理には自社内の小型モデル(SLM)を使う場面が増えるかもしれません。エンジニアは、モデルの精度だけでなく、インフラコストやセキュリティ要件を踏まえて最適なAIモデルを選定・配置するアーキテクト的な視点が求められるようになるかもしれません。
1-4. 「AI Coding Assistant」で考える時代に?
GitHub CopilotやAmazon CodeWhispererなどの「AI Coding Assistant(AIコーディング支援ツール)」は、コーディング用AIと呼ばれる2026年には開発者にとって「あって当たり前」の存在になりそうです。「同僚」とか「バディ」の存在感を得るかもしれません。市場規模も急速に拡大しており、AIを使わずに開発をするエンジニアは少数派になるのではないかと思います。
2026年のAIアシスタントは、これまでのコード補完機能に加えて、どんな機能が追加されていくかが注目点でしょう。コードベース全体を俯瞰したリファクタリングの提案、テストコードの自動生成、さらにはバグの原因特定までを半自動的に行えるようになるかもしれません。
こうなれば、プログラマー、エンジニアの仕事は「コードを書く」ことから、「生成AIが生成したコードの品質をレビューし、システム全体の設計(アーキテクチャ)を考える」ことへと重心が移っていくでしょう。
ただ、生成AIに頼りすぎることで、若手エンジニアが基礎的なロジックを理解しないまま実装できてしまう、スキルの空洞化やブラックボックス化のリスクも高まるはずです。
GitHubの年次レポート「Octoverse 2025」では、『Copilot code review」を使用した開発者の72.6%がレビュー効果の向上を報告しており、AI生成コードに対するレビューとテストの重要性が増していることが示されています。
Octoverse: A new developer joins GitHub every second as AI leads TypeScript to #1 - The GitHub Blog
2026年のエンジニアには、生成AIという「優秀だが時々間違える部下」を適切に指導する新たなマネジメント能力が必要になるのかもしれません。
1-5. 「AIガバナンス」お題目から実務へ
2026年は、AIガバナンスが「努力目標」から「実務上の必須事項」、さらには法的義務へと変わる節目の年となるかもしれません。
普及の一方で世界的にAI規制の波も広がっています。特にEUの「AI法(EU AI Act)」は、違反企業に巨額の制裁金を科す厳しい内容で、2026年には多くの規則が適用開始となります。日本でもAI事業者ガイドラインの運用が進み、AI基本法の制定に向けた議論が本格化しています。これにより、企業は「どのようなデータでAIを学習させたか」「AIの判断にバイアス(偏見)がないか」を説明する責任を負うことになるでしょう。
現場のエンジニアにとって、AIガバナンスは「ポリシー文書を作る」ことだけではありません。開発スピードを落とさずにコンプライアンスを担保することが、2026年以降の開発で求められるようになるはずです。
2. 2026年、日常的に使われそうなキーワード
2-1. 「MLOps」「LLMOps」は"作る"から"回す"に
2026年のIT現場では、「MLOps(Machine Learning Operations)」およびその大規模言語モデル版である「LLMOps」が、DevOpsと同様に当たり前の用語として定着しそうです。
これまでは「いかに高性能なAIモデルを作るか」に注目が集まっていましたが、実用フェーズに入った2026年では「いかに安定して、低コストで運用し続けるか(回すか)」が最大の関心事になるのではないでしょうか。
とくに生成AI(LLM)は、利用量に応じたトークン課金や膨大な計算リソースを必要とするため、漫然と運用すればコストが経営を圧迫しかねません。そのため、プロンプトの管理、回答精度の監視、そしてコスト最適化(FinOps)までを含めたライフサイクル管理基盤としてのLLMOpsが不可欠になっていきます。
エンジニアにはAIモデルを作る技術と同等かそれ以上に、AIシステムを継続的に改善・運用する技術が求められるようになるのかもしれません。PoC(概念実証)で終わらせず、ビジネス価値を生み出し続けるためのAIの運用設計ができる人材が求められるようになりそうです。
2-2. 「オブザーバビリティ(Observability:可観測性)」が一般化?
システムの監視手法は、従来の「Monitoring(監視)」から「オブザーバビリティ」へと変化するのかもしれません。
クラウドネイティブ化やマイクロサービス化によってシステムが複雑化したことに加え、AIエージェントがシステムに組み込まれることで、「何が起きているか」を把握する難易度が劇的に上がっていきます。
従来の「CPU使用率」や「死活監視」だけでは、「なぜAIがその回答をしたのか」「どのエージェントが遅延の原因か」といった根本原因を突き止めることができません。
オブザーバビリティは、未知のトラブルの原因を推論可能にします。2026年は、AIを活用するシステムにおいてブラックボックス化を防ぐため、AIの推論プロセスも含めて可視化する「AIOps」的なアプローチが広まり、トラブル対応は「起きてから調べる」ものから「予兆を検知して防ぐ」ものへと変化していきそうです。
2-3. 「ゼロトラスト(Zero Trust)」が当たり前に?
「決して信頼せず、常に検証する」ゼロトラストのセキュリティ概念は、2026年には具体的な運用ルールとして広まるのではないでしょうか?
2025年もさまざまなセキュリティに関する事件・事故が報道され、「社内ネットワークなら安全」という境界防御モデルが崩壊した印象が形成されつつあります。さらに、今では人間だけでなく、AIもが社内システムにアクセスしています。これらに対応するには、ユーザーやデバイス、そしてAIエージェントの身元(ID)を厳格に確認し、アクセスごとに最小限の権限のみを与える制御が不可欠といえるでしょう。
米国政府によるゼロトラスト戦略や日本政府の方針もあり、企業での導入が加速し、場合によっては「ゼロトラスト対応」がシステムの必須要件となるかもしれません。
3. これから意味が変わっていきそうなキーワード
3-1. 「DX」変革というよりも業務改善の象徴語へ
2026年においても「DX」「デジタルトランスフォーメーション」は使われ続けます。ただ、そのニュアンスは「2025年の崖」に代表されるような、社会の危機を脱するための魔法のような大変革から、より現実的でシビアなデジタルを使った業務改善を象徴する言葉へと変わり、DXにおいても、ROI(投資対効果)が吟味されるようになるでしょう。
これまでのDXブームでは、ツールの導入が目的化するケースも見られましたが、本質的な変革に至っていない企業も多かったといわれています。2026年のDXは、生成AIやRPA、ノーコードツールを現場が使いこなし、経理処理や問い合わせ対応といった具体的な業務を自動化・効率化する業務効率化の積み重ねとして再定義されるのではないでしょうか。
DXは華々しいスローガンというよりも、現場の泥臭い課題を解決し続ける"改善"を意味する言葉へと変貌しそうな予感があります。
3-2. 「クラウドネイティブ」度合いが変わる?
「クラウドネイティブ」という言葉は、2026年には「とにかくクラウドを使えば良い」という意味合いではなく、よりビジネスに直結した意味で使われるのではないかと思います。
これまでは、すべてのシステムをパブリッククラウド上に構築することが正解とされがちでした。しかし、円安やAI利用によるクラウドコストの肥大化や情報管理が経営課題となっているため、「クラウド最適化」や「FinOps(クラウドコスト管理)」が注目を集めるはずです。
その結果、セキュリティの観点などから、クラウド上のワークロードの一部をオンプレミスやエッジ環境に戻す「オンプレミス回帰」が選択肢として検討されるでしょう。ただし、これは昔ながらの環境に戻ることではなく、オンプレミス環境でもクラウドと同じようにコンテナ技術などで管理する「クラウド・ネイティブ・オンプレミス」や、適材適所でクラウドとオンプレミスを使い分ける「ハイブリッドクラウド」が求められるようになるのではないでしょうか。
3-3. 「フルスタックエンジニア」内容が大変化?
「フルスタックエンジニア」の定義も、2026年には大きく様変わりするのではないでしょうか。かつては「フロントエンドからバックエンド、インフラまで一通りコードが書ける人」を指しましたが、AIコーディングアシスタントの普及により、「コードが書ける」こと自体の希少価値が相対的に下がりそうだからです。
2026年以降の「フルスタックエンジニア」に求められるのは、すべてを自作する能力ではなく、既存のクラウドサービス(SaaS/PaaS)やAIモデルをうまく組み合わせ、システム全体を設計・統合する能力です。具体的には、従来の技術スタックに加え、「AIスタック(LLMの選定、RAGの構築、プロンプトエンジニアリング)」や「セキュリティ・ガバナンス」の知識を横断的に持っている人材が、真のフルスタックとして評価されるのではないでしょうか。
「何でも自分で作れる人」から、「AIやクラウドサービスという強力な手駒を使って、ビジネス価値を素早く組み立てられる人」へ。フルスタックの意味は、実装の深さから、技術を繋ぐ広さ、言い換えると「プロデュース力」へとシフトしていくのかもしれません。
4. 「大穴!?」もしかしたら大化けするキーワード
4-1. 「Web3」と「メタバース」トレンド語から「機能」へ
数年前にバズワードとなった「Web3」や「メタバース」は、2026年にはトレンドとしての輝きを失う一方、ITインフラ内の見えない機能の一つとして静かに浸透していきそうです。
Web3を代表するブロックチェーン技術は、暗号資産の文脈から離れ、サプライチェーンでの真正性証明や、デジタル会員証(NFT)、チケット管理といった実務的な裏方技術として定着していく可能性があります。これは令和5年版の情報通信白書(総務省)でも指摘されていました。
メタバースに関しても、「仮想空間で生活する」という壮大なビジョンではなく、製造業でのデジタルツイン(現実空間の再現によるシミュレーション)や、オンライン会議、遠隔作業支援といった具体的なビジネスツールとして使われるようになるのではないでしょうか?
つまり、2026年以降は、ユーザーが「Web3を使っている」「メタバースにいる」と意識することなく、サービスの裏側でこれらの技術が当たり前に動いている状況が発生しそうです。エンジニアは「データベースの選択肢の一つとしてブロックチェーンを検討する」といった目利きが求められるようになるでしょう。
4-2. 「ノーコード」の潮流変化
プログラミング不要でアプリを作れる「ノーコード/ローコード」ツールは、生成AIとの融合により、2026年はさらに深化が進みそうです。ただ、同時にリスクが明確になるかもしれません。
なぜなら現場部門による自律的な業務改善(市民開発)は加速すると、同時に、IT部門が把握できない「シャドーIT」の増加を意味するからです。いわゆる「野良アプリ」が業務の中核に入り込み、メンテナンスが難しくなるリスクが顕在化する可能性があります。セキュリティ対策やデータ連携が不十分な場合はより深刻なリスクになり得ます。
エンジニアは、セキュリティガイドラインを整備し、現場がノーコードやローコードで作ったアプリを適切に管理・統合するガバナンス力が求められる可能性があります。
4-3. 「技術的負債」AIが見つけてしまう!!
今後は、AIの活用によって「技術的負債(Technical Debt)」が可視化され、解消へ向かう手法が一般化する可能性があります。
これまでは「コードが複雑化している」「ドキュメントがない」といった負債は、ベテランエンジニアの勘や経験で語られる定性的なものでした。しかし、AIがコードを解析するようになると「どこにバグの温床があるか」「どのモジュールが複雑すぎるか」を定量的なレポートとして出力できるようになります。
AIが技術的負債を発見し、修正案まで生成する時代になれば、技術的負債の解消は「難易度の高い業務」から「AIと共に攻略するゲーム」のように変わる可能性があります。一方、AIコーディングツールの乱用によって、エンジニアが中身を理解していないコードが大量生産される、AI起因の新たな技術的負債の発生も懸念されています。AIに見つけられる前に、人間がどう設計品質を保つか。過去の技術的負債との向き合い方が問われる年になるかもしれません。
5. まとめ
2026年のITトレンドは、生成AIの「万能の魔法」が解け、ビジネスの現場でどう活用し、どう責任を持って運用するかが問われていくAI中心の流れが続いていきそうです。その意味で、2026年は聞いたこともないバズワードがいくつも発生する可能性は低いかもしれません。ここ数年で姿を現した多様な「手札(技術)」を冷静に組み合わせ、セキュリティとコストのバランスを取りながら、実質的な業務改善を積み重ねていく「現実解」を導き出す力がエンジニアに求められる年になるのではないでしょうか?