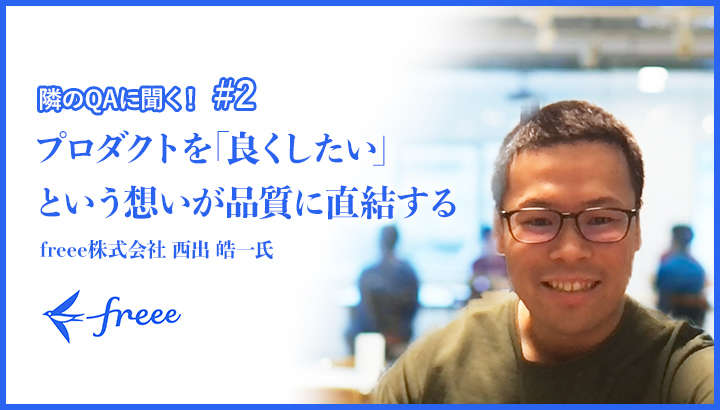さまざまな現場でQA業務に携わっている方々の「声」をダイレクトにお届けする『隣のQAに聞く!』。QA・品質向上の重要性が増している今、他のチームでは、どのようにQA業務が行われているか気になっている方も多いと思います。本連載では、その取り組みや「想い」などを伺い、エンジニアの皆さまにお伝えします。
今回は、freee株式会社のQA/SEQマネージャー 西出 皓一さんにお話をいただきました。
今回インタビューを受けてくださった方

- 西出 皓一 氏
freee株式会社 QA/SEQマネージャー
2015年にfreeeに入社。freee人事労務の開発を経て、現在はQA/SEQマネージャーとして奮闘。
- もくじ
1.QA業務には、やることから探っていける魅力がある

――はじめに、これまでのQA業務に関するご経歴を教えてください。
西出氏:freeeに入社して7年ほどになります。前職では開発エンジニアを4年ほどしており、入社直後は『freee人事労務』の開発をしていました。その後、QA業務や品質に興味があったこともあり、5年ほど前にQAエンジニアに転身しました。
――QAを志望された理由を聞かせていただけますか?
西出氏:きっかけは会社から打診があったことです。はじめは『freee人事労務』のエンジニアと両方やりたいと考えましたが、絞ることにしました。なぜなら、QAはとても重要な業務で、できることが無数にあり、まず、そこから探っていける課題感覚に惹かれたからです。
2.freeeで展開されているQA業務について
――御社のQA業務体制について教えてください。すでに5年前にはQAチームが立ち上がっていたのでしょうか?
西出氏:私が4人目というフェーズでした。当社のQA部門が立ち上がったのは、それより少しさかのぼって1?2年前です。私が入社した頃、QA部門は1人体制で、担当者が1人でリリース前のテストや自動テストの開発をしていました。
――かなり早くから取り組んでいたことになりますね。
西出氏:そうですね。現在でも毎日リリースしていますが、当時から自動テストは毎回、必ず回るようになっていました。
――御社のQA業務の位置づけやミッションを教えてください。
西出氏:当社のサービスはSaaSです。継続的に使う価値があることをユーザーにご理解いただけないと成り立たないビジネスを展開しています。また、ユーザーの業務を担わせていただく社会的責任の大きいサービスです。そのため、継続的に品質を作り込んでいくことがなにより重要になってきます。
当社のQAのミッションは、起きてはいけない不具合を起こさない開発体制にしていくことです。製品の価値を届けるリリースを頻繁にしていく中で、細かい不具合を全て出さないことにすると、リリースの速度が落ちてしまいます。
そこで、絶対に出してはいけないもの、起きてはいけない不具合と、出してからでも直せるものを正しく認識しておく必要があると考えました。そこには、絶対に起きてはいけないことにフォーカスして、継続的にそれを発生させない体質にしていくという私たちの意思も入っています。
――具体的に何か、工夫されていることはありますか?
西出氏:「絶対に起こしてはいけないこと」は意外に人によって異なります。そこで、全社的にしっかり定義をしました。
――皆でトラブルのレベルを分けて認識し、その最も高いレベルのものは「絶対に起こさないようにする」ということでしょうか?
西出氏:はい。サービスごとに問題の「重篤度」を定義しています。フェーズはサービスごとにそれぞれ異なるため、全サービス共通の定義はしていません。
――freeeは積極的に機能追加をされており、競合製品と比べて機能豊富なイメージがあります。テストの領域も幅広いのではないでしょうか? どんな体制で取り組まれていますか?
西出氏:一つのプロダクトにエンジニアが在籍する複数のチームがあり、個々のチームには必ずQAが1人います。そして、プロダクト全体を見るQA担当がいる体制が基本です。また、名称は造語ですが、SEQ(Software Engineer in Quality)という、テストの自動化や保守運用、テスト環境のボトルネックの解消などを通じてQAを支えているチームがあります。SEQでは、品質をエンジニアリングで押し上げていく土台づくりに取り組んでいます
――御社はディベロッパーブログなどでエンジニアが積極的に情報発信をされていますが、どのような意図があるのでしょうか?
西出氏:私たちがエンジニアリングで取り組んでいることを、自分たちから発信していかないと世間には伝わらないので、ブログなどで積極的かつオープンに情報をアウトプットしています。社内でも、アドベントカレンダーなども毎年書いていますし、社内ブログも活発です。最近のQAの取り組みついてもこちらに書いたので、ご興味ある方はご覧いただけると嬉しいです。