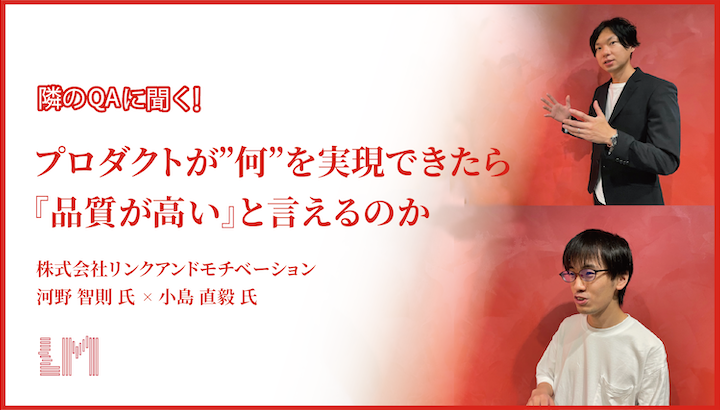さまざまな現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。社会のデジタル化が進み、クラウドサービスを活用して企業変革を推進する時代になっています。その流れもあり、さまざまなクラウドサービスへの関心が高まりを見せ、同時にアプリやソフトウェアの品質も重視されるようになりました。そんな中、他のチームでは、どのようにQA業務を実施しているか、気になっているエンジニアの方も多いのではないでしょうか?
本記事では、QAに取り組む上でのポイントなどを伺い、皆さまにお伝えします。
今回は株式会社リンクアンドモチベーションの河野 智則さん、小島 直毅さんに、同社のSRE(サイトリライアビリティ(信頼性)エンジニアリング)とQAを融合したユニークな『SRE/QAチーム』の特徴と同社のQA活動についてお話をいただきました。
今回インタビューを受けてくださった方

- 河野 智則 氏
株式会社リンクアンドモチベーション
SRE/QAユニットマネージャー
20代前半に独学でプログラミングを学び、エンジニアリングの世界に入る。2011年に入社した大手メディア企業でテックリード、マネジメントといった立場から技術評価や組織作りに取り組む。2020年6月、株式会社リンクアンドモチベーションに入社。SRE/QAユニットマネージャーとしてチームを率いる。

- 小島 直毅 氏
株式会社リンクアンドモチベーション
QA エンジニア
2018年、新卒で株式会社リンクアンドモチベーションに入社。当初はバックエンド開発を担い、後にQAチームに加わる。現在はチームリーダーとしてプロジェクトをリードする存在。学びを通じてJaSST(ソフトウェアテストシンポジウム)に参加。「JaSST'21」には「QAのファンネルで将来のQAチームを描く」で登壇。
- もくじ
1.『顧客価値を安全に、迅速に、確実に届ける』ためSREとQAで共通の指標を設定
――御社はSaaS製品などの品質を向上させるため『SRE/QAチーム』を構成するなど、新たな取り組みを推進されています。まず、SRE/QAチームの位置づけや目標、ミッションを含めて、なぜこのような挑戦をされているのでしょうか?
河野氏:もともと我々は職能別の組織体制をとっていましたが、昨年、ミッション制の組織へと変革しました。この流れの中、SREチーム、QAチームでクラウドサービス『モチベーションクラウド』をはじめとするプロダクトの効果的な改善活動をするための指標を探しました。闇雲に品質、生産性を改善しても何がどれだけ良くなったのか評価できないため、品質、生産性を上げるための現実的な指標が必要だという考えに至りました。
そのとき、フォーキーメトリクス(Four Key Metrics)に出会いました。これはデプロイ頻度、復元時間、変更失敗率、リードタイムの4つを指します。これらは、顧客満足度、収益性、生産性と相関している指標です。科学された指標であり、SREとQAの共通の指標にできるという気づきもあって、二つの活動が近づいたのがSRE/QAチームがはじまる"きっかけ"でした。
このようにして共通のモノサシを持つSRE/QAを一つのチームとして組成し、『顧客価値を安全に、迅速に、確実に届ける』というミッションを掲げました。SREやQAといった横断的に活動するチームは顧客(エンドユーザー)から遠くなってしまうことが多いため、どこに私たちが価値を提供しているのかを明確に言語化し、"顧客に価値を提供するために活動している"ことを明確にしました。「スピードと品質はトレードオフではなくて、"AND"で取れるものである」といった考え方も同時に表現しています。
――SREとQAが一緒に品質改善に取り組む以外にも、他社のQAに比べて「ここが違う」と捉えられているポイントはありますか?
小島氏:私が感じる特色一つは「とても活気にあふれている」ことかと思います(笑) 言い替えると周りを巻き込もうとする意欲がとても強いです。品質という一つの目標に向かって、守護神やゴールキーパーのように"守る"のではなく、どうやったらより良いチームになれるのか?みんなで達成するためにはどうしたらいいのか? このテーマに対して熱意があふれ出て、結果的に活気に満ちているのだと思います。
要件定義から設計の中で、顧客のユーザーストーリーをPdM、エンジニア、QAと、みんなで良くしてこうとしています。その中で、QAから盛り上げていくアクションが取れている状態です。クオリティの意味をより広く捉えると、ソフトウェア品質とは、バグがないだけではなくて顧客に価値を提供することだとチーム内で共有できていると評価しています。
2.顧客価値が届いている実感がやりがいに繋がっていく
――SRE/QA活動を続けていて、どんなときに「やりがい」や「楽しさ」を感じていますか?
小島氏:一つは私たちが作ったものが、本当に人々の役に立っていると感じられたタイミングです。そして、改善するプロセスそのものに関われていることです。
二つめは、チームが本来あるべき価値に向き合うようなアクションをQAから提供できていると実感できたときですね。特にクラウド製品においては、製品品質を上げるだけでなく、開発を続けるチームそのものもプロダクト品質の一部だと考えています。そのため、チームがより良くなること自体がやりがいに繋がっています。
――反応が返ってきたり、チームが良くなっていったりすることが「楽しさ」に繋がっているのですね。
河野氏:実際に私たちが環境や品質面で関わっているプロダクトを使ってくださった顧客から「こんな良い変化があった」といった喜びの声を聞く機会を定期的に設けるような仕組みがあります。仕組みの提供やプロセス改善といった間接的な関わりの中で、顧客への貢献を実感できることが、私にとってやりがいの一つになっています。