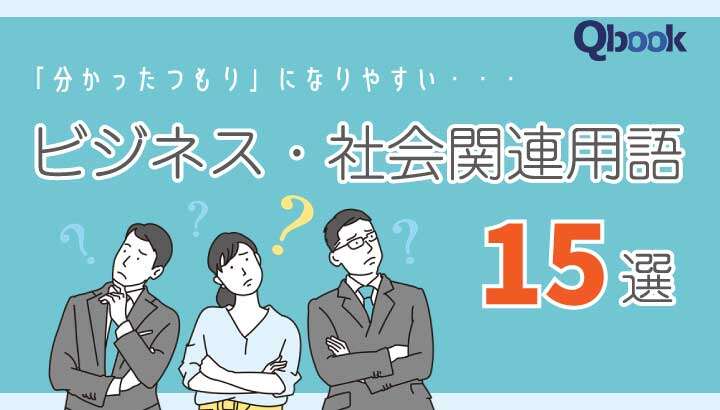最近、ビジネスなどの現場で頻繁に使用される言葉には、一見すると理解しやすく見えて、実は複雑な意味を持つものがあります。
これらの言葉は、メディアやニュースで頻繁に使用されることで広まっていますが、その意味や背景を知らず「なんとなく」使われていることも多いようです。
本記事では、そんな「分かったつもり」になりやすい言葉を集めて、その意味をまとめてみました。
1.ビジネス戦略を彩る言葉
1-1 「イノベーション思考」とは?新しいだけじゃない?
「イノベーション思考」とは、既存の経営資源に新たな経済的価値を付加する思考法です。大規模な技術革新だけでなく、人間の思考や視点を少し変えることや新しいアイデアを生み出すことで、新しい付加価値を生み出すことを意味しています。
例えば、同じ製品で、それまでにない新しい使い方を新規顧客層に提案して需要を発掘したり、顧客が喜んで買いたいと思う新機能やサービスを追加したりすることで、経営資源に新しい経済価値を付加することができます。
イノベーション思考の本質は、技術を重視しつつ、さらに人間の創意工夫によって新たな着想や見方の変化を実現することにあるといってよいでしょう。
1-2 「創造的破壊」は単なる"破壊"とどう違う?
「創造的破壊」は、経済学者ヨーゼフ・シュンペーター(1883-1950)が著書の『資本主義・社会主義・民主主義』で提唱した概念です。
新たな効率的な方法が生み出されると、古い非効率的な方法が駆逐されていくという経済発展のプロセス、新陳代謝のことを指します。単なる破壊ではなく、新しい価値の創造を伴う破壊を意味しています。
シュンペーターは、「創造的破壊」の特徴は、外部環境の変化ではなく企業など集団の内部のイノベーションによって引き起こされることだと指摘しました。
持続的な経済発展のためには、絶えず新たなイノベーションで創造的破壊を行うことが重要とされています。ただし、不況時には社会的に有用な企業の倒産が増加して新規参入が困難になって新陳代謝は起こらず、古い企業が存続しやすくなることもありえます。
1-3 「戦略的パートナーシップ」の本当の意味
「戦略的パートナーシップ」とは、政治や経済などで、共通の目標を持つ2つ以上の国や、事業体等が長期的に利益を得ることを前提に協力関係を結ぶことを指します。
言い換えると、これは単なる取引の交換ではなく、インフラや資源、専門知識、ネットワーク等を共有し、集団的な成功を達成するために戦略的な関係性を構築すること意味しています。
戦略的パートナーシップの特徴は、信頼、価値観の共有が長期的なコミットメント(公約、約束、責任)の上に築かれていくことです。
企業や集団は新たな市場を開拓し、事業範囲を拡大し、ゼロベースではなく、他の方法では利用できない新たなリソースを得ることができます。
外交的には、国同士のつながりをより強固にしていく狙いがあるとされます。最近では「日EU戦略的パートナーシップ協定」の批准書等の交換が話題になったばかりです(2024年11月1日)。
2.社会や環境に関係する言葉
2-1 「サステナビリティ」戦略は三本柱がポイント
「サステナビリティ(sustainability)」とは、「持続する(sustain)」と「~できる=可能性(able)」から、「持続可能性」と訳されていることが多いようです。持続可能な発展を目指す考え方や取り組みのことを指して使われます。
環境保護にフォーカスされがちですが、経済発展と社会開発を含む"3つの柱"であることがポイントです。
企業の目線から見ると、未来に向かって健全に利益を出し続けること、環境や社会に配慮すること、人権や労働の権利の尊重、健全なコミュニティの維持を図ることが重要な点とされています。
環境面では、自然資源を守り、生態系の健全性を保ちながら、持続可能な方法で資源を利用することが求められています。
また、「SDGs(Sustainable Development Goals)」と混同されて使われることがあるようです。
サステナビリティは考え方や取り組み方のことで、SDGsは、2015年9月の国連サミットで定められた世界共通の具体的な目標という違いがあります。
2-2 「ダイバーシティ」推進の本質について
「ダイバーシティ(diversity)」は多様性の意味で、組織や集団内に存在する個人や集団間のさまざまな属性の違いを指します。
これには人種、性別、年齢、宗教、価値観、障がい有無などさまざまな概念が含まれています。
ダイバーシティを推進するということは、いろいろな多様性を受け入れ、活躍の道を用意することで組織の成長と個人の満足度を向上につなげていくことを意味します。ダイバーシティ推進により、グローバル市場における競争力は大きく強化されるでしょう。
また、多様な人材が活躍する組織は、環境変化に強く、柔軟性が高いとされ、変化の早いグローバル市場だけでなく、あらゆる場面で強い競争力を維持できる可能性が高くなるという指摘もあります。
「共存」の意味で使われることもありますが、多様な人材の個性や能力を活かして、組織や個人の成長につなげていくことがポイントだといえるでしょう。
2-3 測れるのか?「社会的インパクト評価」
「社会的インパクト」とは、内閣府の定義によると「短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会的、環境的なアウトカム」であるとされています。
これともに使われる言葉が「社会的インパクト評価」です。こちらを内閣府は「社会的インパクトを定量的・定性的に把握し、当該事業や活動について価値判断を加えること」と定義しています。
上記2つの定義は、「社会的インパクト評価検討ワーキング・グループ」が作成した『社会的インパクト評価の推進に向けて』に掲載されています。
社会的インパクトを測定することは重要ですが、実際のところ、定量化は容易ではありません。社会的インパクトを測定するためには、明確な定義と目標設定が必要です。
例えば、「環境に優しい製品の売上を高める」という漠然とした目標ではなく、具体的な数値目標を設定することが大切です。短期的な評価だけでなく、長期的に見ていくことがポイントになるでしょう。
3.さまざまなリスクを示す言葉
3-1 「地政学的リスク」は広がる?
「地政学的リスク」とは、特定の国や地域の政治的・軍事的・社会的な緊張の高まり、地理的な状況が原因で関連地域や世界の経済や政治の先行きを不透明にしてしまうリスクのことです。
具体的には、国際的な紛争や戦争、テロや内戦、経済制裁や貿易障壁、政策変更などが関連することが多いようです。
近年、地政学的リスクは拡大傾向にあるとされています。
例えば、ロシアとウクライナの戦争、中国と台湾の関係、北朝鮮によるミサイル発射、中近東の政治的緊張・紛争など、世界各地で地政学的リスクが顕在化しているといえます。
これらのリスクは、直接的な衝突だけでなく、経済制裁や貿易障壁といった形や物価の変動という形で、他国や企業活動に影響を与えることがあります。
地政学的リスクは一国や地域に留まらず、世界経済全体の先行きを不透明にする可能性があるため、常に国際情勢に注目しておくことが大切です。
3-2 「構造的リスク」とは何か
「構造的リスク」とは、組織や社会システムに内在する構造的な問題から生じるリスクを指します。
原因構造が明確ですが、組織や社会システムの基本的な設計や運営方法、つまり構造に問題があるため、長期的な影響をおよぼす可能性があります。
組織や社会全体に影響範囲を広げやすいのも特徴です。例えば、経済システムにおける所得格差の拡大といった問題がこれに当たります。
また、構造的リスクは、性質上、短期的な対策では解決が困難で、システム全体の見直しや長期的な取り組みが必要となることが多いです。
逆に、原因と結果がつながらない(明確でない)ものは「非構造的リスク」と呼ばれます。
3-3 「レジリエンス」とは回復力のこと?
「レジリエンス(resilience)」とは、困難な状況から気持ちを立て直す「精神的な回復力」を意味します。
ビジネスの世界では回復力以上の意味があり、トラブルや強いストレスに直面したときに、適応する精神力と心理的プロセスのことをいいます。つまり、レジリエンスは「速やかに立ち直る力」だということができそうです。
「レジリエンス力」と"力"をつけて表記される場合は、レジリエンスを発揮する具体的な能力、スキルを示すことが多いようです。ややこしい記し方になりますが、「回復力を発揮する能力」といったニュアンスで使われることもあります。
4.経営・組織に縁が深い言葉
4-1 法令遵守だけではない「コンプライアンス」
「コンプライアンス(compliance)」とは、「法令遵守」のことですが、最近では、多くの場合、法令遵守に留まらない意味があるようです。
大きくは「法」「社内規範」「倫理」の3種類に分けられています。コンプライアンスの概念は、法律だけでなく、倫理観、公序良俗や社会通念上のさまざまなルールやマナー、企業が自ら定めた社内規定などの規範に従って、公正・公平に業務を行うことを意味しています。
そのため、法に触れなくても、倫理的でない行為はコンプライアンス違反として社会から非難される可能性があることになります。
コンプライアンス意識を高めるためには、法令を守るだけでなく、企業や組織の社会的責任を認識して、倫理的な判断力を養っておくことが重要とされています。
4-2 「経済的合理性」には落とし穴がある?
「経済的合理性」とは、経済的な価値基準に沿って論理的に判断した場合に、利益があると考えられる性質や状態のことで、最も効率的で利益を最大化する選択をすることを意味しています。
しかし、この考え方を狭義に解釈して実行すると、人間や社会にとって望ましくない結果をもたらす可能性があります。
つまり、長期的な持続可能性を無視した短期的な利益追求に走って信頼を失ったり、環境や社会的なコストを無視してしまったり、従業員の健康や幸福を犠牲にしてしまう人間性軽視の動きが見られてしまったりすることが、大きな損失を引き起こすことがあるのです。
したがって、経済的合理性を追求する際は、短期的な利益だけでなく、長期的な持続可能性、社会的責任、人間の幸福などを総合的に考慮する必要があるといえます。
4-3 「潜在的ニーズ」は本当にあるのか?
「潜在的ニーズ」とは、顧客自身も自覚していない、潜在的な欲求(ニーズ)のことを指します。これは顕在化されたニーズと対比される考え方です。
潜在的ニーズはビジネスにおいて重要な意味を持ちます。潜在的ニーズを発見し、それに応える製品やサービスを提供することで、新たな市場を創造したり、競争優位性を獲得したりすることができるからです。
オンリーワンになることも可能ですが、潜在的ニーズの発見は容易ではありません。
とくに強い潜在的ニーズを見つけることは難しく、「どう見つけるか」といった見つけ方がテーマになることもあります。
「隠されたニーズ」「裏ニーズ」「真のニーズ」といった記され方をすることがありますが、それぞれニュアンスは異なります。
5.思考や分析に関連する言葉
5-1 「生存者バイアス」の罠
「生存者バイアス」とは、成功例や生き残った事例のみに注目し、失敗例や消えてしまった事例を見落としてしまう認知バイアスのことです。
このバイアスにより、成功の要因を誤って解釈したり、リスクを過小評価したりする危険性があります。
例えば、成功した起業家の特徴のみを分析し、「成功する起業家はリスクを恐れない」と結論づけるのは生存者バイアスの典型だといわれています。実際には、リスクを取った多くの起業家が失敗しているからです。
生存者バイアスを避けるためには、失敗例も含めた包括的なデータ収集を行い、成功要因だけでなく、失敗要因も分析する必要があり、長期的な視点で評価することが大切だとされています。
統計学者エイブラハム・ウォールド(Abraham Wald)は、第二次世界大戦時に爆撃機の損失を最小限にする方法を検討するとき、従来は帰還機のみが注目されていましたが、生存者バイアスを考慮して、撃墜された爆撃機にも注目すべきだと指摘しました。
そして、帰還した爆撃機が損傷を受けていない場所の補強を提案したといいます。
5-2 「ナラティブ・アプローチ」の可能性
「ナラティブ・アプローチ(narrative approach」とは、人々の経験や物語(ナラティブ)を通じて現象を理解し、問題解決を図るアプローチ方法です。
このアプローチは、対人支援の場面でよく活用されています。1990年代に臨床心理学の分野で誕生しました。
ナラティブ・アプローチは、数値データでは捉えきれない人間の複雑な経験や感情を理解するのに有効です。
そのため、医療やソーシャルワークだけでなく、ビジネスの現場では、組織文化の理解をする際に活用されていたり、キャリアコンサルティングに使われていたりします。
ナラティブに似た言葉に「ストーリー」があります。ナラティブは、自分自身が主人公のため終わりがありません。ストーリーはお話の筋が重視されることが多いようです。このように同じ「物語」と訳される単語でも、言葉のニュアンスは異なります。
5-3 「ポリティカル・コレクトネス」の複雑さ
「ポリティカル・コレクトネス(Political Correctness)」とは、差別的な言動や偏見を避け、社会的弱者や少数派に配慮した中立的な表現を用いる考え方、またはそのための対策のことを指します。
「ポリコレ」と略されたり、「PC」と記されたりすることもあります。1980年代以降、欧米を中心に広まっています。
その目的は、言語や行動を通じて社会的公平性を促進することですが、その解釈や適用は複雑さが伴っています。
最近では、ポリコレへの過剰な配慮が表現の自由を制限する可能性や、文化によって適切とされる表現が異なったり、社会の変化とともに変化したりする可能性があることが指摘されています。
ポリコレは、差別や偏見のない社会を目指す上で重要な概念ですが、同時に表現の自由との兼ね合いや、文脈に応じた適切な判断が求められています。企業や組織は、ポリコレの重要性を認識しつつ、硬直化した対応を避け、オープンで建設的な対話を促進することが重要だとされています。
まとめ
今回は、ビジネスや社会でよく使われる「分かったつもり」になりやすい15の言葉について、その意味をまとめました。
「ヨコ文字が多い」と思う方も多いかもしれません。
ただ、これらの言葉は、単なる流行語ではなく、ビジネス戦略、社会・環境問題、リスク管理、経営・組織運営、思考など、重要な領域に関連しています。
そのため、今後もあらゆる場面で使われていくのではないかと思います。