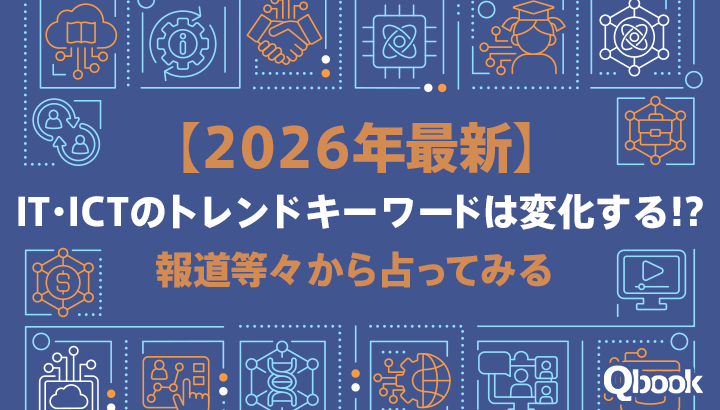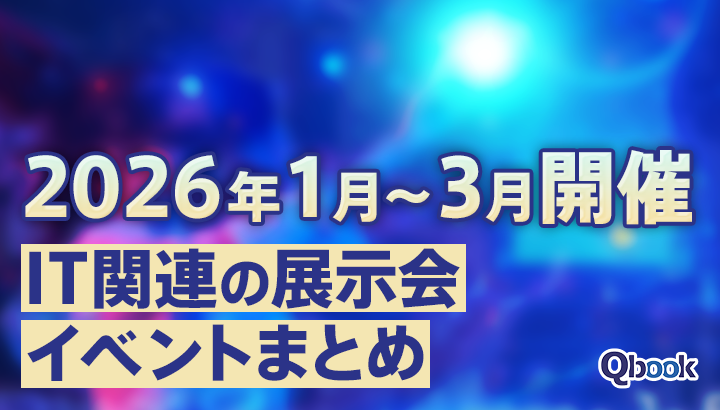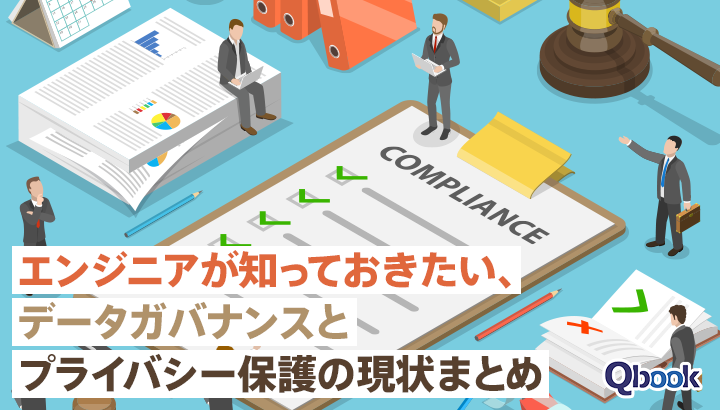テクノロジーの進化がめまぐるしく進む現代において、中国のIT市場は世界の注目を集め続けています。
ニュースや日常生活でも、中国のIT企業やサービスの名前を耳にする機会が増えてきました。
今回は、2025年の中国IT市場に焦点を当て、IT産業構成、主要なOS、スマホ市場、ネットサービスのトレンド、そしてネットで話題になる現象について簡潔にまとめてみました。
- もくじ
1. 中国IT市場の全体像
1-1. ITは中国経済の柱
中国のIT産業は、もはや経済の中心的な存在です。2025年現在、中国のIT産業は付加価値額ベースで国内総生産(GDP)の約4%を占め、製造業や不動産業と肩を並べる"経済を支える柱"になっています。
インターネット普及率の高さや、スマートフォンの爆発的な普及も、この成長を後押ししています。国策による支援と、急速な都市化・デジタル化の流れにより、中国社会全体がITを前提としたインフラにシフトしており、AI(人工知能)の普及にともない、さらに新しいサービスやソリューションが次々に生まれてくると予測されています。
China's software industry achieves robust growth last year(Bastille Post)
1-2. 主要産業と成長分野
中国IT産業の成長をけん引しているのは、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、AI(人工知能)といった先端分野です。
IoTは、スマートホームや交通インフラ、スマートシティの実現に欠かせない技術として発展し、クラウドサービスは企業のデジタル化やデータ活用を支える基盤となっています。とくに中小企業がクラウドサービスを積極的に導入し、業務効率化を加速させています。
AI分野では、顔認証や音声認識、自然言語処理などの技術が実用化され、日常生活やビジネスの現場で広く利用されています。2025年には『DeepSeek』が登場し、世界中で話題になりました。
これらの分野は、今後も中国IT産業をリードする中心的な存在でありつづけるでしょう。
1-3. ソフトウェア産業の市場規模と成長率
中国のソフトウェア産業は、ここ数年で飛躍的な成長を遂げています。2024年の時点で、ソフトウェア産業の市場規模は数10兆円規模に達し、毎年10%を超える成長率を維持しているのです。
アプリ開発、業務用ソフト、OS、検索エンジンなど、多様な分野で堅実な成長を見せています。とくに、国内向けと海外展開の両輪で企業がシェアを広げ、検索エンジン大手の「Baidu」や、クラウドサービスを提供する「Alibaba Cloud」などが市場をリードし、世界的な競争力も強化しています。
また、中国語圏向けに最適化されたソフトが多いため、他国とは異なる進化を遂げているのも特徴です。
1-4. 主要プレイヤーと産業構成
中国のIT産業を代表する企業には、「Tencent(テンセント)」、「Alibaba(アリババ)」、「Baidu(バイドゥ)」、「Huawei(ファーウェイ)」、「Xiaomi(シャオミ)」などがあります。
これらの企業はそれぞれ異なる強みがあります。
「テンセント」はSNSやゲーム、クラウドサービス、「アリババ」はECやクラウド、「バイドゥ」は検索エンジンとAI、「ファーウェイ」は通信機器やスマートフォン、「シャオミ」はスマホやIoT機器で存在感を示しています。
特徴はそれぞれの企業が単一の事業分野にとどまらず、複数の分野で新規事業を展開してエコシステムを形成していることにあるでしょう。さらに、スタートアップや新興企業も続々と登場し、産業の多様化とイノベーションが加速しています。
1-5. 政府政策とデジタル化推進
中国政府は、IT産業を国策として強力に推進しています。とくに2015年から始まった「互聯網+(インターネットプラス)」政策は、伝統産業とITの融合を目指し、デジタル化の波を一気に加速させました。
インターネットプラス政策により、製造業、農業、医療、教育などあらゆる分野でIT技術の導入が進み、社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)が実現しています。
近年では「デジタル中国」という新たなスローガンも掲げられ、行政手続きのオンライン化やスマートシティ化などが加速しています。政府主導の投資や規制緩和、インフラ整備も、IT産業の発展を強力に後押ししています。
2. 中国のスマートフォン市場
2-1. HarmonyOS vs Android vs iOS
中国のスマートフォン市場では、OS(オペレーティングシステム)を巡る競争が熾烈です。
Huawei(ファーウェイ)が開発した独自OS「HarmonyOS(ハーモニーオーエス)」、Googleの「Android」、Appleの「iOS」がシェア争いを繰り広げています。
2025年現在、中国国内ではHarmonyOSのシェアが急拡大しており、iOSを上回ったと報じられています。
Androidが圧倒的な首位(シェア約6割)ですが、ついで、HarmonyOS、iOSが続いています。中国政府のサポートや国産OS推進政策もあるとされ、今後、HarmonyOSの存在感が増すのではないかという予測もあります。
2-2. 中国ブランドの大躍進
中国のスマートフォンブランドは、世界市場でも圧倒的な存在感を示しています。
Huawei(ファーウェイ)、Xiaomi(シャオミ)、Vivo(ヴィーヴォ)、Oppo(オッポ)などのブランドは、革新的な技術やコストパフォーマンスの高さで、世界中のユーザーから支持を集めています。
機能向上やバッテリー持ちの良さなどで差別化を図り、グローバル市場でもAppleやSamsungと肩を並べる存在となっています。とくに中南米や東南アジア、アフリカなどの新興国では、「コスパのよいスマホ」として高い支持を受けています。日本でも「中華スマホ」として一定数のファンがいます。
中国のスマホブランドは、今後も、アジア、ヨーロッパ、アフリカなどでも積極的に展開しつづけ、世界のスマホ市場をリードすることになるのではないでしょうか。
2-3. 「中華スマホ」はなぜ安い?
中国製スマートフォンが安価で高性能なのは、いくつかの理由があります。
まず、中国は世界最大級の電子機器生産拠点を持ち、部品調達や製造コストを大幅に抑えることができる点が上げられます。つぎに、大量生産によるスケールメリット、政府による補助金、税制優遇もあって価格競争力が高められているという指摘があります。
また、中国企業は、中国国内に生産拠点を持ち、部品を国内で調達できるため、サプライチェーンの効率が非常に高いこともポイントになっています。
スマホニュースをよく見る方はお気づきかもしれませんが、「中華スマホ」は製品のライフサイクルを短めで、最新モデルや特別モデルが次々に投入されています。こうすることで市場の注目を集める戦略が成功し、順調に成長を続けているとの指摘もあります。
3. 中国市場を席巻する「スーパーアプリ」とネットサービス
3-1. 「WeChat」はメッセージングだけじゃない
中国の「WeChat(ウィーチャット)」は、単なるメッセージングアプリを超えた存在です。チャットや通話機能に加え、モバイル決済、SNS、ショッピング、タクシー配車、公共サービスの利用まで、生活に必要なあらゆる機能が一つのアプリに集約されています。
いわゆる「スーパーアプリ」として、月間アクティブユーザー(MAU)は2025年に14.8億人に達すると推計されています。
もはや中国ではWeChatなしでは生活が成り立たないといわれるほどです。QRコードによる決済や、企業向けのサービス、アプリ内アプリ(ミニプログラム)も充実し、ビジネスや行政サービスのデジタル化にも大きく貢献しています。この多機能性が、WeChatを単なるアプリではなく社会インフラへと押し上げているのです。
3-2. ソーシャルコマースとエンタメの融合が進んでいる
中国のネットサービスでは、ソーシャルコマースとエンターテインメントの融合が急速に進んでいます。
例えば、ライブ配信を通じて商品を紹介・販売する「ライブコマース」は、巨大な市場規模を誇り、インフルエンサーや一般ユーザーがリアルタイムで商品を紹介することで、消費者との距離を縮めています。
また、短編動画アプリとECサイトが連携することで、広告感を出さずに自然に商品を紹介できるスタイルも主流になっています。インフルエンサーたちが商品の紹介だけでなく、ストーリー性のある演出や歌、ダンスを交えながら販売を行う姿は、まさにエンタメとコマースの融合といえるでしょう。日本のいわゆる「通販番組」とは一線を画するインパクトがあると思います。
このようにショート動画アプリやSNSを活用したマーケティングも活発で、エンタメ体験とショッピングが一体化した新しい消費スタイルが定着しています。このスタイルは、何らかのきっかけで世界に広まる可能性があると思います。
事実、ファッションブランドの「Zara」は、中国でライブショッピング(ライブコマース)が成功したことを受け、これを欧米でも展開しようとしているようです。
After China, Zara expands live shopping experiment to Europe and US(Reuters)
3-3. 中国独自のSNS文化
中国のSNS文化は、西欧諸国や日本とは大きく異なる特徴を持っています。
「Weibo(微博)」はX(旧Twitter)に似たマイクロブログサービスで、芸能人やインフルエンサー、企業が情報発信の場として活用しています。有名人や公式アカウントによる情報発信が活発で、社会的な話題やトレンドが生まれる場となっています。
「Bilibili(ビリビリ)」はアニメやゲーム、サブカルチャーに特化した動画共有サイトで、若者を中心に熱狂的なファンがいることで知られています。特徴的な「弾幕コメント」機能が特徴とされています。これは、日本での「ニコニコ動画」のように動画にコメントが入れられる機能です。
「TikTok(中国版はDouyin)」はショート動画プラットフォームとして世界的に人気ですが、中国国内では独自の機能やトレンドが生まれています。
中国のSNSでは、バズりやすいコンテンツとして、ユーモアや共感を呼ぶ内容、社会風刺、時事ネタ、インフルエンサーによるチャレンジ動画などが人気です。日本に比べるとインパクト重視の傾向があるように感じます。
いわゆる「衝撃映像」関係の投稿が日本のテレビ番組などで取り上げられることも増えたようです。
中国ではリアルタイム性やインタラクティブ性が重視され、ユーザー同士の交流や情報拡散のスピードも非常に速いのも特徴とされています。また、「バズる」現象が政策や経済にも波及することがあり、SNSで話題になった内容がニュースに取り上げられることも珍しくありません。
4. AIとデジタル経済、自動運転
4-1. 中国の「AI」技術の現状
中国はAI分野で世界最先端を走る国の一つです。顔認証や音声認識、自然言語処理などの技術は、日常生活やビジネス、公共インフラに広く導入されています。
とくに、監視カメラによる顔認証システムや、AIを活用した医療診断、教育分野での個別最適化学習など、実用化の範囲が急速に拡大しているとされています。
教育分野でもAIが活用されており、生徒の理解度を分析して教材を最適化するシステムも登場しています。大規模なデータを活用できる中国ならではの強みが、AIの進化を後押ししています。政府主導のAI開発戦略や、豊富なデータ資源、優秀な人材の育成も、AI技術の発展を強力に支えています。
先ほども述べましたが、2025年のAI『DeepSeek』の登場は世界に衝撃を与えました。
4-2. デジタル経済の状況
中国のデジタル経済は、モバイル決済を中心に急成長しています。QRコード決済は都市部だけでなく地方都市や農村部にも普及し、現金を使わないキャッシュレス社会が実現しています。
「Alipay(アリペイ)」や「WeChat Pay(ウィーチャットペイ)」に加え、顔認証決済やNFC(近距離無線通信)を使った非接触型決済も拡大中です。これらの決済方法は屋台や個人商店に至るまで広く導入されています。また、デジタル通貨(デジタル人民元)の実証実験も進められており、今後はさらなるデジタル化が期待されています。
さらに、オンライン銀行、電子契約、クラウド会計など、ビジネスの現場でもデジタル化が進んでおり、紙の書類が必要ない業務も増えています。シェアサイクルや配車サービス、オンラインフードデリバリーといったオンデマンドサービスもデジタル経済の重要な一部を担っています。これらのサービスは、スマートフォンの普及とモバイル決済の利便性によって急速に拡大し、人々の生活スタイルを大きく変えています。
その意味で、中国はデジタル先進国の一つだといえます。
4-3. 自動運転、電気自動車、PHEV分野が急成長
中国は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、そして自動運転技術の分野においても、世界の最前線を走っています。国家主導で進められている「新エネルギー車」政策により、EVの生産台数と販売台数は年々増加。2024年時点では、中国国内で販売されたEVが世界全体の半数以上という状況です。
「BYD」や「NIO」「Xpeng」といった中国車ブランドが急成長し、デザイン性や技術力でも欧米勢と十分に戦えるレベルに達してきました。また、自動運転技術についても、「Baidu」や「Huawei」が研究開発を進めており、一部の都市では自動運転タクシーの実証実験も行われています。
自動運転はまだ法制度やインフラの課題も残されていますが、政府の積極的な後押しにより、世界に先駆けた広まりを見せる可能性があります。政府の後押しが、これらの分野の成長を強力に支えています。
4-4. 今後の展望
今後の中国IT市場は、さらなる多様化とグローバル化が進むと見られています。AIやIoT、クラウド、5Gなどの先端技術が社会のあらゆる分野に浸透し、スマートシティや自動運転、デジタル通貨の実用化が加速するでしょう。生成AI、ブロックチェーン、メタバースといった次世代技術にも積極投資が進んでおり、新たな産業やビジネスモデルが生まれる土壌が整いつつあります。
また、「デジタルシルクロード」構想を通じて、ITインフラを海外に輸出する動きも強まっています。また、国際競争力の強化や、海外市場への進出も積極的に進められる見込みです。一方で、情報統制やプライバシー問題、技術の標準化を巡る国際競争といった課題も指摘されています。
とくにアメリカとの技術覇権争いは今後もつづくと見られ、どのように国際協調と競争とのバランスをとるのかが問われます。今後も、中国のIT産業は世界の注目を集める存在でありつづけるでしょう。
まとめ
2025年の中国IT市場は、国家戦略としての支援を背景に、AI、IoT、クラウドなどの先端技術で目覚ましい発展を遂げています。
IT産業は、「インターネットプラス」政策のもと、社会全体のDX化を推進しています。
これからも中国IT市場は世界のトレンドに影響を与え続けるでしょう。