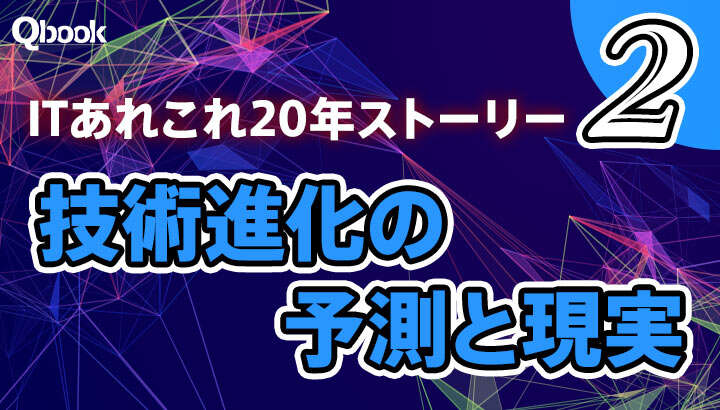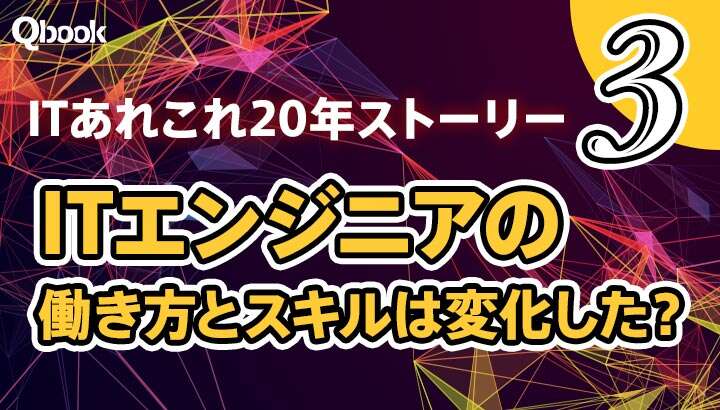今から20年前の2005年ごろに進化が予測、期待されていたIT技術、例えば量子コンピューティング、AIなどが、この20年でどのように進化し、社会やビジネスにどのような変化をもたらしたかを振り返ります。
当時の予測や期待と、2025年現在の実際の技術レベル・社会実装状況を比較し、さらに「当たった予測」と「ハズれた予測」も見ていくことで「今」が見えてくるかもしれません。
- もくじ
1. 2005年ごろのIT技術予測と社会から期待は?
1-1. 2005年ごろのIT技術レベルと未来予測
2005年のIT技術は、今になって思えば、ある意味「素朴」な時代でした。スマートフォンは存在せず、多くの人が携帯電話(フィーチャーフォン/ガラケー)を使い、SNSといえばmixiが登場したばかりで(2004年)、Twitter(現 X)は存在せず、個人発信メディアとしてはブログが人気でした。
今ではあたりまえの動画メディアはYouTubeが産声をあげたばかり(2005年4月)という状況でした。
この頃はインターネットは主にパソコンからアクセスするものであり、ブロードバンド接続はADSLを中心に普及が進んでいましたが、まだまだモバイルを中心にダイヤルアップ接続も珍しくありませんでした。OSについては、「Windows XP」(2001年リリース)や「Mac OS X v10.3(Panther)」(2003年リリース)が主流でした。また、AI分野では、現在の生成AIのような自然な会話や画像生成は夢物語とされていたようです。
そんな時代、10年先、20年先といった未来について希望に満ちた予測がされていたと思います。
「AIは自然な会話が可能になり、翻訳や業務支援などで人間とともに働く存在になる」
「量子コンピュータが実用化され、医薬品開発や材料設計などで当時のコンピュータでは難しいとされていた高速計算を実現する」
「量子コンピュータを背景にバイオテクノロジーが遺伝子治療の飛躍的進歩をもたらし、難病克服の切り札になる」
といった予測が語られていました。
マンガ・アニメの大ヒット作『鉄腕アトム』の誕生日は初期設定で2003年4月7日だったことから、2005年の少し前には当時のロボット技術が話題になることもありました。
1-2. 政府・業界のビジョンは?
政府も積極的に未来ビジョンを示していました。2005年より少し後になりますが、象徴的な取り組みが、2007年に内閣府が策定した「イノベーション25」構想です。
「2025年までを視野に入れた成長に貢献するイノベーションの創造のための長期的戦略指針」とされています。
興味深いのは、構想の中で「伊野辺家の1日」と題した未来の家族の生活が具体的に描かれていることです。「伊野辺家の1日」では、朝起きると家のセンサーが自動で健康状態をチェックします。通勤ラッシュは消滅し、利用するバスは電気自動車です。そしてテレワーク制度が普及(3割程度が対象者)しています。電気自転車も一般化して自転車通勤がブームになっています。
他にも、ウェアラブル端末機器を活用したり、自動精算をするセルフレジや、携帯端末機器による支払い、生活をサポートするロボット......等々、盛り沢山な内容で、まさに「ITが生活を支える」日常がショートストーリー仕立てで描かれています。
総務省「平成17年版 情報通信白書」(2005年)でも、ICTが新たな成長の柱として開始され、ユビキタス社会の到来が掲げられています。
1-3. AI・量子コンピュータ・バイオテクノロジーへの期待
2005年当時、AI、量子コンピュータ、バイオテクノロジーといった技術は、将来を担う革新的な分野として大きな期待を集めており、一般社会でも注目されるようになってきていました。
AIに関しては、「人工知能が人間のように考える時代がくる」との期待がありました。
当時はまだディープラーニングの実用化前でしたが、すでに音声認識や自動翻訳などの分野では前進があり、教育、医療、ビジネス支援などでの活用が見込まれていました。
量子コンピューティングは、理論上は従来のコンピュータでは不可能な処理を可能にする「夢のマシン」とされ、暗号解読や新素材開発などに期待が寄せられていました。
当時は、比較的早い時期の実現が予測されていましたが、量子ビットの制御など多くの技術的課題が残っており、一般報道に対して2030年ごろに実用化するのではないかといった見方をする専門家も多くいました。
バイオテクノロジー分野では、量子コンピューティング"の将来的実用化"によってヒトゲノム解析や遺伝子治療が飛躍的に進む、という期待が高まっていました。現時点では、量子計算技術の応用研究が進められている段階ですが、がんや難病の治療における画期的な進展につながる可能性があるとして、引き続き注目を集めています。
完全電化への期待も大きく、「電気自動車(EV)」の普及が大いに期待されていました。
エネルギー効率の良い社会が実現し、環境負荷の低いクリーンなエネルギーが利用される未来像が描かれていました。
2. 技術進化の現実――2025年の到達点
2005年ごろの技術と未来への期待を概観したところで、現在の状況を整理してみましょう。
2-1. AIの進化と実社会への実装
2025年現在、AIの進化は目覚ましいものがあり、生成AIの登場と普及は、社会のあらゆる場面に影響を及ぼしているようです。OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」など、自然言語処理を駆使する対話型AIが多数リリースされ、業務効率化や教育支援、カスタマーサービスまで多岐にわたる分野で活用されています。
企業等の問い合わせ用WEB窓口では、チャットボットが基本的な対応を自動化し、教育現場の一部では、AIが個別の学習スタイルに合わせて教材を調整するなどして活用されています。また、プログラミングのアシスタントとしてもAIは活用されており、すでに多くのエンジニアの作業を軽減する存在として使用されています。
2005年には「自然に会話できるAI」などはSFの世界に近かったのですが、現在ではスマートフォンやPCに搭載され、一般の人が日常的に使うツールになっています。まさに、予測が実装に変わった代表例といるでしょう。
2-2. 量子コンピューティングの現状
一方、量子コンピューティングは、いまだ「ブレイクスルー前夜」といる状況が続いています。
Googleは2019年に「量子超越性」を達成したと発表し注目を集めましたが、2025年現在でも汎用的な商用サービスには至っていません。
IBM、Google、Amazon、Microsoftといった大手IT企業が、量子コンピュータのクラウド提供に向けて実証実験を進めており、研究機関やスタートアップと連携した応用開発が加速しており、進展は確かなもと言えます。
注目されているのは、医薬品開発や金融モデリングなど、膨大な計算を必要とする分野への応用です。日本国内でも、理化学研究所と富士通による量子技術の研究が進められており、「ポストスーパーコンピュータ」の中核技術として期待されています。そして2025年、ついに実機が公開されました。
量子コンピュータの商用実装には、まだ技術的課題が残るとされています。2005年当時の「2020年代には商用化されるだろう」という予測は、やや楽観的すぎたかもしれません。
2-3. バイオテクノロジー・医療ITの進展
バイオテクノロジー分野も、一定の進展を見せています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を契機に、mRNAワクチンの実用化という大きな成果が生まれました。
この技術は、個別化医療の実現にも貢献するとされており、がん免疫療法などへの応用が期待されています。
さらに、ゲノム編集技術「CRISPR-Cas9(クリスパー・キャスナイン)」の実用化も進み、遺伝子疾患に対する新しい治療法として注目を集めています。これまで治療が困難だった難病に対し、根本的な治療というアプローチが可能になりつつあります。
医療ITも、電子カルテのクラウド化や遠隔診療の普及、AIによる診断支援など、着実に進化を遂げています。コロナ禍の影響で2020年以降、遠隔医療の導入は世界中で加速し、とくに医師不足の地域においては極めて有効な手段となっています。
2-4. クラウド、IoTなどの爆発的普及
技術進化において、もっとも大きな変化が起きたのは「クラウド」と「IoT」かもしれません。
2005年当時は、データは自分のPCに保存する、バックアップは別のメディアに行うのが常識でしたが、いまやGoogle DriveやDropbox、Microsoft OneDriveといったクラウドサービスがビジネス・生活のインフラになっています。
企業はオンプレミスからクラウドへとシフトし、データ活用やBCP(事業継続計画)の面でもクラウド活用は必須となっています。とくにコロナ禍以降、テレワーク体制の構築が急速に進み、クラウドサービスの価値は上昇しています。
IoTは、家電、農業、自動車、医療などあらゆる分野に広がり、センサーや通信機能を持つデバイスが日常的に活用されるようになりました。スマート家電が電力消費を自動制御したり、農業用のIoTセンサーが収穫時期や病害を予測したりするなど、その活用範囲は拡大の一途をたどっています。とくにドローンの進歩は目を見張るものがあります。
今後は「エッジAI」と呼ばれる、端末側でAI処理を行う技術が注目され、IoTとAIがより密接に連携する世界が予測されています。つまり、クラウドとIoTは単なるインフラから、次のイノベーションの土台へと変貌を遂げはじめています。
3. 2005年ごろの「予測」と現実のギャップ
2005年の「予測」と2025年現在の状況を概観してきました。
ここでは、「当たった」予測、「ハズレた」予測、少し無理筋だった「予測困難だったこと」を挙げていきます。
3-1. 主な「当たった」予測
2005年当時に語られていたIT技術の未来予測の中で、見事に的中したと思われるのが、AIによる業務自動化や医療支援、そしてバイオテクノロジーの医療応用でしょう。
「AIがオフィスの単純作業を代行する」といわれていましたが、2025年の現在、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)や生成AIが、それを現実のものとしています。事務処理の効率化、メール返信の自動化、文書作成の支援など、あらゆる分野でAIが活用されています。
また、バイオテクノロジーにおけるmRNAワクチンやゲノム編集技術の実用化も、当時の期待を超えた成功事例といるでしょう。人類が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応できたのは、まさに長年のバイオ技術研究の成果によるものでした。
他にも、電気自動車(EV)の普及や遠隔診療の進展なども、概ね予測どおりといってよいと思います。とくにEVについては、テスラやBYDなどが台頭し、自動車市場に影響を与えています。
ネットワークを介した情報共有とコミュニケーションの発展も、当時の予測とは多少異なる面がありますが、SNSの普及によって現実のものとなっています。X(旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNSが人々のコミュニケーションの中心となり、ニュースや意見がリアルタイムで共有されています。
3-2. 主な「ハズれた」予測
一方、当時の「夢」が実現しなかったり、予測が外れたりした例を見ていきましょう。
その一つは「完全電化社会」かもしれません。
2005年には原子力発電を軸に、化石燃料から脱却し、クリーンで安定したエネルギー供給が実現することが期待されていました。これは原油依存から脱却したい想いもあったと考えられます。
しかし、2011年の東日本大震災を機に原子力発電の安全性が大きく問われることになり、エネルギー政策は見直しを迫られているところです。
また、量子コンピューティングの進展も、思っていたよりもスピーディではありませんでした。確かに研究は進んでいますが、一般的な商用サービスとしての活用には、まだハードルが高いといってよいと思います。
ロボットの本格的な普及も「伊野辺家の1日」ほどは進んでいません。2005年ごろには、家庭用ロボットが掃除や料理、介護といった日常のタスクをこなし、人間社会に溶け込む未来が描かれていました。
しかし、2025年現在、お掃除ロボットや一部のペットロボットは普及しているものの、多機能で人間と対話しながら家事をこなすような汎用的な家庭用ロボットは、まだまだ限定的といます。
3-3. 予測困難だったことは?
ある意味、誤算といえるのは、当時ほとんど想像されていなかった技術が、社会を大きく変えたことです。
代表例は「スマートフォン」です。2007年にiPhoneが登場するまでは、誰もがキーボード付きの端末やウェアラブル端末を想像していました。例にあげた「伊野辺家の1日」にも似たものは出てきますが、スマートフォンは登場しません。
しかし、いまやスマホは生活の中心であり、情報端末、決済手段、エンタメ機器、健康管理ツールなど、あらゆる機能を担っています。人によっては「体の一部」的な存在になっています。
そして、生成AIも2005年には現在のようなUI/UXでは予見できていませんでした。音声による入出力が有力視されていた印象があります。
また、クラウドコンピューティングの爆発的普及も、2005年時点では一般的には予測困難だったように思えます。当時、企業は自社サーバーを持つことが一般的でしたが、この20年でクラウドはITインフラの主流となり、企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させたともいます。個人の写真保存などでのクラウド利用はあまりイメージされていなかった気がします。おそらく、当時クラウドサービスを開発中のエンジニアだけが予見していた未来でした。
このように、新しい潮流は、過去の延長線上ではなく、突然、現れるが多いのです。技術の進化は、いつも既存の常識を凌駕する形で進行します。まさにイノベーションといえます。
4. 技術進化がもたらしたITエンジニアの役割の変化
技術の進化は、ITエンジニアの働き方や役割にも大きな影響を及ぼしました。
2005年ごろのITエンジニアといえば、プログラムコードを書くことが中心であり、特定分野の技術に精通する専門職としての側面が強かったと思います。ウォーターフォール開発モデルが主流であり、要件定義から設計、開発、テスト、運用へと段階的に進む中で、それぞれのフェーズで専門性が求められました。
しかし2025年現在では、ITエンジニアに求められる役割は格段に広がっています。開発によって社会に貢献したり、社会課題を解決したりすることが求められる時代になりました。
つまり、ITエンジニアは「技術を使う人」から「技術と社会をつなぐ人」へと立場が進化しています。専門性に加え、チームとの協働力や、倫理的判断、社会的責任といった、より複合的なスキルが求められています。「技術が進化したら、仕事がなくなるのでは」と恐れる声もありますが、実際は逆かもしれません。社会からのITエンジニアへの期待は増すばかりといってよいでしょう。
5. まとめ
2005年から2025年にかけての20年間、IT技術は劇的な進化を遂げました。
AI、クラウド、IoTなど、多くの予測が現実となる一方で、量子コンピュータやエネルギー政策では課題も残っています。そして、予測していなかったスマートフォンや生成AIが社会を変えました。エンジニアの役割も変わり続ける今、私たちは変化を恐れず、技術とともに前進し続ける必要があります。