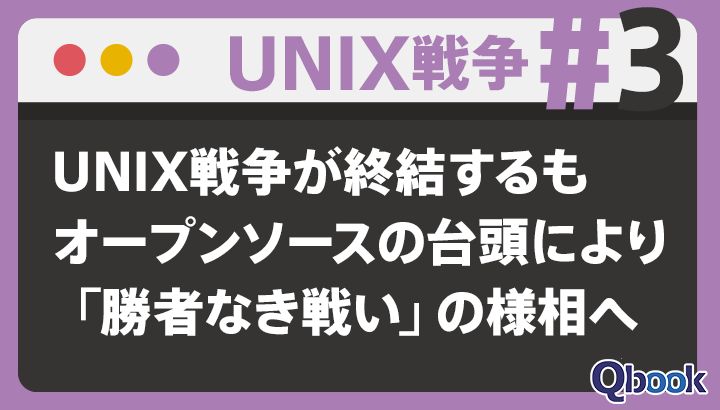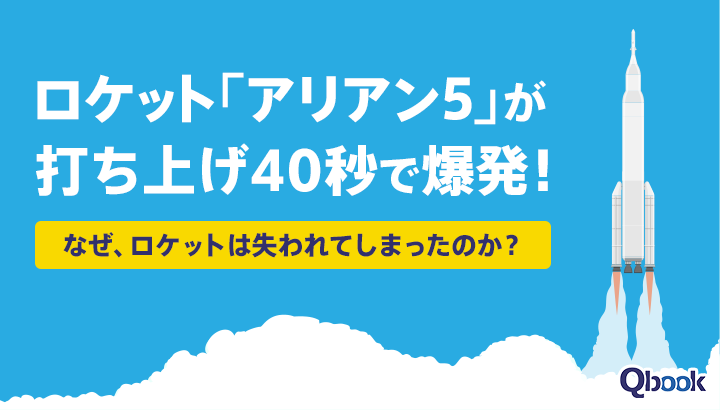1980年代末から1990年代初頭にかけて、コンピュータ業界では「UNIX戦争」と呼ばれる激しい標準化競争が繰り広げられました。
AT&Tとサン・マイクロシステムズの主導するUI陣営と、IBM、HPなどが結集したOSF/1陣営が業界を二分し、互いに自陣営の仕様を標準とすべく「UNIX戦争」を展開しました。
この対立は技術革新を促す一方、UNIX市場の成長を阻害する問題もあり、終結へと向かいます。最終となる第三回では終結への流れをまとめました。
- もくじ
1. 【前回までのまとめと補足】「UNIX戦争」終結までの動き
★【UNIX戦争】とは?
UNIX戦争とは、1980年代末から1990年代にかけて発生した、UNIXの標準化を巡る技術的・商業的な企業間競争です。
「UNIX International(UI)」陣営と「Open Software Foundation(OSF)」陣営が、それぞれ異なるUNIXバージョンを展開し、業界を二分する争いを展開しました。
この争いは技術革新をもたらす一方、互換性の問題などから、UNIX市場の成長を阻害する一面もあり、終結を望む声が高まっていました。
1-1. UNIXの誕生と多様化、対立
UNIXは1969年、AT&Tベル研究所で開発されました。当初は研究目的のプロジェクトでしたが、そのシンプルで移植性が高い設計、マルチユーザー・マルチタスク機能により、大学や研究機関、そして次第に企業にも広がっていきました。
UNIXの歴史における重要な転機は、AT&Tがベル研究所で開発したUNIXのソースコードを、教育機関に低コストで提供しはじめたことでした。とくにカリフォルニア大学バークレー校は、独自の拡張を加えたBSD(Berkeley Software Distribution)を開発し、多くの機関に配布。これが後のBSD系UNIXの源流となります。
1980年代前半になると、AT&TはUNIXの商用ライセンスを本格的に展開しはじめます。これに伴い、IBMはAIX、HP(当時はヒューレット・パッカード)はHP-UX、サン・マイクロシステムズ(Sun Microsystems)はSunOSというように、各社が独自のUNIX派生OSを開発し、自社ハードウェアとともに販売するようになります。マイクロソフトもXenixという独自のUNIX互換OSを開発し、第三の勢力として台頭していました。
こうして、主にAT&TのSystem V系と、BSD系という二大潮流が形成されるとともに、ベンダーごとの独自仕様の追加により、UNIX互換OSの世界は複雑化していきました。互換性の問題は日に日に深刻化し、ユーザー企業からの不満が高まる中、業界は標準化に向けて動きはじめます。
1-2. 標準化を巡る動きに変化
標準化に向けた具体的な動きは1980年代半ばから本格化します。AT&Tは1985年に「System V Interface Definition(SVID)を策定。これとは別に、欧州のコンピュータベンダーは1984年に「X/Openコンソーシアム」を結成し、UNIXベースのオープンシステム仕様の策定を目指します。
また、IEEE(米国電気電子技術者協会)は1988年に「POSIX(Portable Operating System Interface)」規格を公開しました。これはSystem VとBSDの両陣営で実装可能なAPIを定義したもので、後のUNIX標準化において重要な基盤となりました。
1988年、AT&Tはサン・マイクロシステムズと連携し、System V、BSD/SunOS、Xenixの良いところを統合した「System V Release 4(SVR4)」を開発。この動きが刺激となり、1988年5月、IBM、HPなどの大手コンピュータメーカーは「Open Software Foundation(OSF)」を結成し、独自のUNIX(OSF/1)を開発することで、AT&Tとサン・マイクロシステムズ陣営への対抗を図ります。
これに対し、AT&Tとサンは「UNIX International(UI)」を設立し、業界は完全に二分される形となり、標準化を目指す動きが、皮肉にも業界の分断とUNIX戦争を招くことになりました。
UNIX戦争は、技術革新をもたらす一方、互換性の問題などから、UNIX市場全体の成長を阻害しはじめます。そして性能的に優れていながら、UNIXはコンシューマー向け市場(つまり個人向け)に展開するチャンスを失います。
結果的に当時のアップル(Apple)の「マッキントッシュ(Macintosh)」の普及、さらにはマイクロソフト(Microsoft)Windowsの台頭と世界制覇を許す要因の一つになったといわれています。
2. UNIX戦争の終結と標準化の進展
2-1. なぜAT&TはUNIXを売却したか?
長引くUNIX戦争に変化が訪れたのは1993年です。
AT&TがUNIX事業をNetWareで成功していたノベル(Novell)に売却してしまったのでした。この決断には複数の要因がありました。
一つ目の要因は、AT&TにとってUNIX事業は本業である通信事業に比べて重要度が低かったことがあげられます。通信業界の規制緩和が進む中、AT&Tは本業への集中を図る必要がありました。
次の要因としてUNIX戦争による市場の混乱と長期化する標準化競争で、UNIX事業の収益性が低下していたことがあげられます。
そして、1990年代に入ると、マイクロソフトの台頭が顕著になっていました。Windows 3.0/3.1が個人向け市場で普及し、Windows NTがサーバー市場にも参入しはじめたことで、AT&TはUNIX市場の将来性に疑問を抱くようになっていたことも大きな要因となりました。
ノベルは、NetWareとUNIXを統合することで新たな市場を創出する戦略を描いていましたが、結果的にはその狙いを達成できませんでした。ノベルは1995年にはUNIX商標権を「X/Open(後のThe Open Group)」に譲渡し、1996年には、UNIXのソースコード権利(System Vのコードベース開発権等)を「Santa Cruz Operation(SCO)」に売却しています。
これらの動きは、UNIX戦争の当事者が変わったことと、戦争自体のエネルギーが失われていたことを示しています。市場の現実と長期戦による疲弊が、徐々に業界を標準化の方向へと導いていったことになります。
また、1993年には、IBM、HP、サン・マイクロシステムズといった主要ベンダーがついに手を組んで「Common Open Software Environment(COSE)」を設立します。COSEの設立は、UNIX戦争終結への第一歩として歓迎されました。
2-2. X/OpenとOSFの合併によるThe Open Groupの形成
UNIX戦争終結への大きな転機となったのは、1996年に実現したX/OpenとOSFの合併でしょう。
この合併によって「The Open Group」が発足し、UNIXの標準化と認証、UNIX商標の管理を一元的に担う組織が誕生しました。
「The Open Group」は、UNIXの標準化を協調によって進めることを目指し、かつての対立陣営のメンバーも含めた850社以上の企業が参加する大規模な標準化団体となりました。この合併は長く続いた業界の分断状態に終止符を打つ象徴的な出来事だったといえます。
「The Open Group」は、単にUNIXの標準化だけでなく、IT業界全体のオープン標準の推進を使命としています。企業がベンダー間の協調により標準化を進めるというモデルは、その後のIT分野における国際協調の重要なモデルケースとなりました。
これにより、UIとOSFという二大陣営の対立構造は解消され、業界は統一された標準に向けて協力する体制が整いました。長く混乱していたUNIX業界にとってインパクトの大きい出来事となりました。
2-3. 「Single UNIX Specification」の確立と意義
「The Open Group」による重要な成果の一つが「Single UNIX Specification(SUS)」の策定です。
SUSは、UNIX系OSが満たすべきAPI、システムコール、コマンド体系などを包括的に定義したもので、異なるベンダーのUNIX間での互換性と移植性を大きく向上させる役割を果たしました。
SUSは、1994年に初版が発表され、その後も改訂が続けられています。この仕様に準拠しているOSのみが「UNIX」商標を使用する権利を得ることができ、これによりUNIXの定義が明確になりました。
SUSの登場により、「どのUNIXが真のUNIXか」という論争に終止符が打たれたことになります。
また、SUSのコアはPOSIX標準と技術的に同一であり、C言語によるプログラミングインターフェース、シェル、ユーティリティなどが規定されています。これにより、アプリケーション開発者は、特定のUNIXに依存せず、標準に準拠したコードを書くことで、複数のUNIX環境での動作を保証できるようになりました。
このようにUNIX戦争の終結は「The Open Group」の発足と「Single UNIX Specification」の確立に象徴されます。同時に、UNIX戦争の外側で静かに力をつけていたオープンソース陣営の台頭により、「戦争をする余裕がなくなる」事態になっていました。
3. オープンソースの台頭によるUNIX「旧勢力」の衰退
3-1. 「Linux」と「GNUツール」が一気に普及
UNIX戦争の最中である1991年、フィンランドのヘルシンキ大学の学生だったリーナス・トーバルズ氏((Linus Torvalds)が、自作のカーネル「Linux」を発表しました。Linuxはフリーソフトウェア財団(FSF)のGNUプロジェクトのツール群と組み合わされ、事実上、UNIX互換のOSとして機能するようになります。
「UNIX商標」を持つわけではありませんが、何といっても無料で自由という特徴があり、一気に広まっていきます。Linuxは誰でも自由に利用、改変、再配布できるGPLライセンスを採用し、ソースコードが公開されていたため、世界中の開発者がバグ修正や機能追加に貢献することができたためです。
インターネットの普及も、Linuxの発展に大きく寄与しました。地理的な制約がなく、世界中の開発者がコードを共有し、協力して開発を進めることができたのです。1990年代後半には「Red Hat」「Debian」「Slackware」「SUSE」など、多様なLinuxディストリビューション(配布版)が登場。それぞれ独自の特徴を持ちながらも、基本的な互換性を保っていました。
このような背景もあり、Webサーバーやデータベースサーバーといった用途では、Linuxの安定性と低コストが高く評価されることになり、商用UNIXが得意としていたエンタープライズ市場にも急速に浸透していきます。
「LAMP」(Linux、Apache、MySQL、PHP/Perl/Python)と呼ばれるオープンソースの組み合わせは、WEBアプリケーション開発の定番となり、インターネットの爆発的な普及を技術面から支えることになりました。
3-2. 商用UNIXの市場縮小
Linuxの台頭により、従来の商用UNIXは市場シェアを急速に失っていきます。
Intel製x86プロセッサのパフォーマンスが向上し、コストパフォーマンスの高いサーバーが普及するにつれ、専用のハードウェアを必要とする商用UNIXの魅力も薄れてしまいました。
商用UNIXが最後まで強みを持っていたのがスーパーコンピュータ分野でしたが、ここでも状況は劇的に変化します。
世界のスーパーコンピュータのランキング「TOP500」を見ると、1998年にはLinuxを採用するシステムはわずか0.2%にすぎませんでしたが、2005年には72%に達し、2017年には驚くべきことに100%がLinuxベースとなりました。最新のデータでも、この傾向は変わっていません。
商用UNIX市場は急速に縮小し、かつての主要プレイヤーも戦略の転換を迫られました。
IBMはLinuxへの投資を増やし、HPもLinuxサーバーのラインナップを拡充。サン・マイクロシステムズは2009年にOracleに買収され、Solarisの開発は縮小します。
IDCの調査によれば、2012年時点で商用UNIX市場はIBM(AIX)が56%、Oracle(Solaris)が19.2%、HP(HP-UX)が18.6%を占めていましたが、市場全体の規模は急速に縮小しており、新規導入よりも既存システムの維持が中心となっている状況です。
UNIXベンダーにとって皮肉なことに、標準化を巡る争い=UNIX戦争が終結した頃には、すでに市場の主導権は別の場所へと移っていたことになります。
3-3. オープンソースによる新エコシステム
21世紀に入ると、オープンソースによる新たなエコシステムが確立されました。
Linuxを中心に、クラウドコンピューティング、コンテナ技術、IoT、AIなど多様な分野でオープンソースソフトウェアが標準となり、従来の商用UNIXは「レガシーシステム」としての位置づけが強まっています。
オープンソースの成功要因は、ソフトウェア開発のあり方そのものを変革したことにあります。「所有から共有へ」という考え方の転換は、従来のソフトウェアビジネスモデルを根本から覆しました。企業間の協調と競争が同時に存在する「コープティション」モデルが広がり、多くの企業がオープンソースプロジェクトに参加するようになります。
皮肉なことに、かつてUNIX戦争で争った企業の多くが、現在はLinuxやオープンソースへの貢献者となっています。
例えば、Linux Foundationには、かつて競合関係にあったIBM、HP、インテル、Oracle、マイクロソフトなどが参加し、共同でLinuxの開発を支援しています。オープンソースへの貢献が、企業の技術力や社会貢献の指標として評価されるようになったのです。
また、Red Hatのようなオープンソースサポート企業の成功は、「無料のソフトウェア」でもビジネスとして成立することを証明しました。Red Hatは2019年にIBMに340億ドルで買収されていますが、これはオープンソースの商業的価値が認められた象徴的な出来事といるでしょう。
クラウドコンピューティングの普及も、オープンソースの地位を確固たるものにしました。
Amazon Web Services、Google Cloud Platform、Microsoft Azureといった主要クラウドサービスは、その基盤にLinuxを採用しています。
また、Kubernetes(コンテナオーケストレーション)、Docker(コンテナ技術)、OpenStack(クラウド基盤)など、クラウドネイティブな技術の多くもオープンソースで開発されています。
UNIXの精神や設計思想は、LinuxやBSD、さらにはmacOS(Darwinカーネル)などの現代OSに受け継がれ、ITインフラの根幹を今も支え続けているといってよいでしょう。
4. まとめ:「UNIX戦争」が遺したこと
UNIX戦争は、UNIXの標準化と主導権を巡る、激しい企業間競争でした。この争いは、最終的にはThe Open Groupの設立とSingle UNIX Specificationの確立という形で決着し、UNIX標準化への道を開きました。しかし皮肉なことに、標準化が実現した頃には、争いの外側で静かに力をつけていたLinuxをはじめとするオープンソースソフトウェアが商用UNIXに取って代わる存在となっていました。商用UNIXは急速に市場シェアを失い、現在ではレガシーシステムとしての位置づけが強まっています。
一方、UNIXの精神や設計思想はLinuxなどを通じて現代のITインフラに深く根付き、クラウドコンピューティングやコンテナ技術など、新たな技術革新の基盤となっています。UNIX戦争の歴史は、標準化の重要性と同時に、オープンな協力の力が閉鎖的な競争を凌駕することを示す教訓となりました。
主要参考文献
History of Unix, BSD, GNU, and Linux - CrystalLabs -- Davor Ocelic's Blog