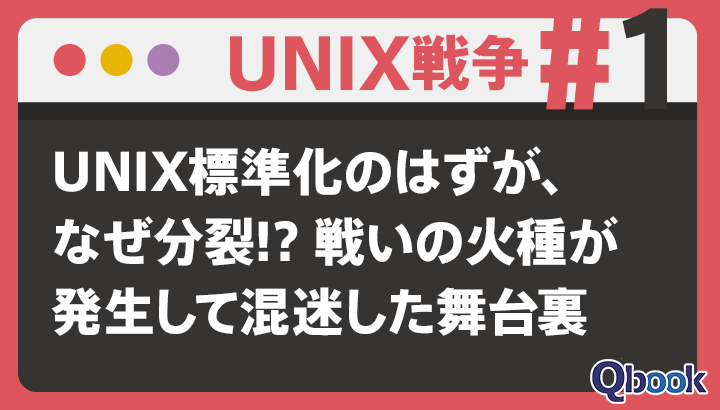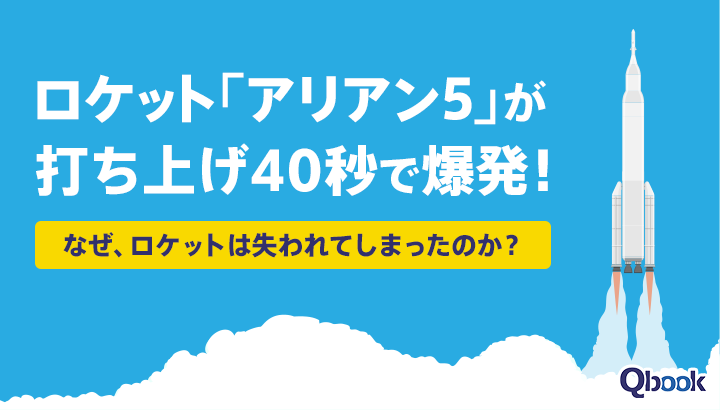1980年代、世界のコンピュータ業界を席巻したUNIX。しかし、UNIXの標準化の動きは皮肉にも激しい分裂と対立を生み出してしまいます。
AT&Tとサン・マイクロシステムズが牽引する「UNIX International(UI)」と、多数企業が結集した「Open Software Foundation(OSF)」。
この2大陣営の争いは「UNIX戦争」と呼ばれることになります。そこで、今回から3回に分けて、UNIX戦争についてまとめました。
1. 『UNIX戦争』とは?
「UNIX戦争」とは、1980年代後半から1990年代前半にかけて、UNIXの標準化を巡って、AT&Tとサン・マイクロシステムズ(Sun Microsystems)が主導する「UNIX International(UI)」と、複数企業が結成した「Open Software Foundation」がUNIXの標準化を巡って激しく競い合ったことを指します。
両陣営は互いに異なるUNIXバージョンを展開して、業界全体を巻き込む混乱と分裂を招いてしまいます。
本記事では、UNIXの誕生と混乱、対立への流れについて解説していきます。
2. UNIXの誕生と分岐
2-1. ベル研究所がUNIXの起源
UNIXの物語は1969年、アメリカのベル研究所に溯ります。
ケン・トンプソン氏(Ken Thompson)やデニス・リッチー氏(Dennis Ritchie)らによって開発されたUNIXは、シンプルな設計と移植性の高さ、マルチタスク・マルチユーザーに対応できる能力が高く評価され、研究機関、学術機関や企業に急速に広がっていきました。
当初はトンプソン氏によって「UNICS(Uniplexed Information and Computing Service)」と名付けられましたが、後に「UNIX」という名称に変わりました。UNIXはオープンな設計思想が多くの開発者を惹きつけたこともあり、短期間で多様な派生版が生まれることになります。
2-2. 「BSD」と「System V」の二系統へ分岐
UNIXは当初、ベル研究所からソースコード付きで大学や研究機関にライセンスされていました。1970年代後半になると、カリフォルニア大学バークレー校の学生ビル・ジョイ氏(Bill Joy)らがUNIXを改良して「Berkeley Software Distribution(BSD)」として配布を開始します。
BSDはTCP/IPなど先進的な機能を積極的に取り入れ、学術機関を中心に高い支持を集めます。BSDがTCP/IPを実装したことは、インターネット普及の原動力の一つになったといってよいでしょう。
一方、AT&Tは自社の商用版UNIXである「System III」「System V」を開発して、企業向けに展開します。System Vは、エンタープライズ分野での利用を意識し、信頼性や商用サポートを重視していました。こうして、UNIXは「BSD系」と「System V系」という二つの大きな流れに分岐し、それぞれが独自の進化を遂げていくことになります。
この分岐は、それぞれの開発主体が異なる目的や思想を持っていたこと、そして当時のライセンス形態が改良や再配布を比較的容易にしていたことが背景にありました。
2-3. 「ライセンス」と「ソースコード」の問題
UNIXの発展を支えたのは、初期のソースコード付きライセンスでした。
しかし、商用化が進むにつれ、AT&Tはライセンス条件を厳格化し、ソースコードの公開を制限します。BSDは比較的緩やかなライセンスで広がっていましたが、System Vは商用ライセンスが中心だったこともあり、互換性や移植性に課題が生じることになります。
AT&TがUNIXの知的財産権を主張し、ライセンス料を求めるようになったため、BSDなどの派生バージョンを開発・配布していた組織との間で、ライセンスに関する問題や法的な係争が発生する可能性が出てきました。
また、各社が独自の拡張を加えた結果、UNIXの各バージョン間、派生版間で互換性が低下してしまい、標準化のニーズが高まっていきました。UNIXとは名乗っていても"別物"のようになっていたという状況でした。
3. 標準化への取り組み開始
3-1. 「SVID」と「POSIX」の苦労
UNIXのバージョンが乱立している事態を重く見たAT&Tは「System V Interface Definition(SVID)」という標準仕様を策定します。しかし、SVIDはSystem V系に偏っていたこともあり、BSD系との溝は埋まらず、標準化には至りませんでした。
そこで、より中立的な標準化を目指して登場したのが「POSIX(Portable Operating System Interface)」です。POSIXは、UNIX系OS間の互換性を高めるため、IEEE(米国電気電子技術者協会)やISO(国際標準化機構)が主導して策定されましたが、各ベンダーの思惑や政治的な駆け引きが絡み、合意形成が難航することになります。
標準化を目指しているはずのSVIDとPOSIXの間にも差異が存在するなど、標準化への道のりは平坦ではありませんでした。
3-2. 「X/Open」と「/usr/group」の活動
1984年になると、欧州の主要ベンダーを中心に「X/Open」という団体が設立され、UNIXをベースにしたオープンな標準化を推進します。X/Openは、各社のUNIXバージョン間の互換性を高めるための仕様策定や、認証プログラムを展開し、のちのUNIX戦争時には調整役な立場をとることになります。
また、アメリカでは「/usr/group」(後にUniForumと改称)も標準化活動を進め、業界全体で互換性向上への機運が高まっていきます。
これらの組織は、ベンダーの壁を越えて協力し、相互運用可能なシステム環境の実現を目指しましたが、それぞれの標準化の取り組みが乱立する形となり、当時、混乱を招く側面もあったという指摘もありました。
3-3. どうしても埋まらない溝...
こうした標準化の試みがつづく一方で、各社の利害や技術的な違いから、UNIXの統一はなかなか進みませんでした。さらにSystem VとBSD系、それぞれの陣営が独自の機能拡張を優先したため、標準仕様が現実の製品に反映されにくいという問題も生じます。
AT&TはSystem Vを自社の主要な商用OSとして位置づけ、SVIDを事実上の業界標準にしようと考えました。しかし、他のベンダーはAT&T一社にUNIXの標準化の主導権を握られることを嫌いました。とくに、BSDをベースとしたシステムを開発していたサン・マイクロシステムズ(Sun Microsystems)などは、AT&TのSystem Vへの傾倒に強い懸念を抱いていたとされています。
依然として標準化への努力はつづられていたものの、対立の火種が増えてしまう状況となってしまいました。
4. AT&TとSun Microsystemsの提携
4-1. 「System V Release 4(SVR4)」登場
1988年10月、ここで事態は大きく動きます。AT&Tとサン・マイクロシステムズが提携して、「System V Release 4(SVR4)」の開発を正式発表したのです。
System VとBSD系、SunOS(Sun MicrosystemsのBSDベースOS)、Xenixの機能を統合したSVR4は、UNIXの標準化を目指す野心的なプロジェクトでした。
サン・マイクロシステムズは、BSDベースの高性能ワークステーションで急速に成長していましたが、UNIXの分裂による互換性の問題に直面していました。一方、AT&TはSystem Vの普及を進めたいと考えていました。ここで両社の利害が一致し、AT&Tは、System VとSunOSの技術を統合した、新しいUNIX「SVR4」の開発をSun Microsystemsと推進することを決定したのです。
SVR4は、System Vの堅牢性や商用機能をベースに、BSDのネットワーキング機能や仮想記憶管理、SunOSのファイルシステムなど、両系統の優れた機能を取り込み、高い性能と豊富な機能を備えた統合版UNIXとして登場しました。
多くのユーザーや業界関係者は、この動きを歓迎しましたが、一部の企業はサン・マイクロシステムズが過度に有利になることを懸念して、不満を募らせることになります。
4-2. 反発、そして「OSF」の設立へ
AT&Tとサン・マイクロシステムズによるSVR4を中心とした提携は、他のUNIXベンダーにとっては「寝耳に水」だったこともあって、強い警戒感を抱かせることになってしまいました。
つまりSVR4が事実上の標準となり、自社開発のUNIX製品が不利になるのではないかと考えたわけです。
そこで、サン・マイクロシステムズの影響力拡大を警戒したIBMやHPなどの大手ベンダーは、1988年に「Open Software Foundation(OSF)」を設立します。OSFは、AT&T・Sun陣営に対抗し、独自のオープンUNIXを開発・提供することを目指しました。
こうして、UNIX標準化を巡る動きは、むしろ業界の分裂を加速させる結果となります。OSFは独自のUNIXである「OSF/1」を開発し、UI陣営のSVR4に対抗していくことになります。
4-3. 「UNIX International」登場で業界分裂へ
OSFに対抗するため、AT&Tとサン・マイクロシステムズは「UNIX International(UI)」という団体を結成し、業界は2大陣営に分裂することになります。
UIには、日本からも富士通、日本電気(NEC)、東芝などの企業が参加し、SVR4をUNIXの唯一の公式な標準として推進することを目的としました。
OSF、UIの両陣営はそれぞれ独自のUNIXバージョンを開発し、商業的・技術的な競争が激化。技術的な議論は次第に後景に追いやられ、政治的・商業的な駆け引きが前面に出るようになっていき、ある意味、ドロ沼化した状況になっていきます。
UIはSVR4の技術的な優位性を主張し、OSFは特定のベンダーであるAT&Tとサン・マイクロシステムズが自社の利益を優先しすぎていると批判しました。このUIとOSFの間の激しい競争こそが、「UNIX戦争」の核心となり、業界全体の混乱を招くこととなります。
5. 「フリーソフトウェア」の成長
5-1. 1983年「GNU」プロジェクト始動
OSFとUIが激しく争う一方、1983年にリチャード・ストールマン氏(Richard Stallman)が「GNUプロジェクト」を立ち上げます。GNUとは「GNU's Not Unix!」の略で、UNIX互換のフリーなOSを開発することを目指すプロジェクトでした。
当時、マサチューセッツ工科大学(MIT)の人工知能研究所にいたストールマン氏は、自身が利用していたソフトウェアがプロプライエタリ化(独占的なライセンスの下で提供されること)されていく状況に危機感を抱いていました。
ストールマン氏はソフトウェアのソースコードが非公開になり、ユーザーが自由にソフトウェアを修正したり、再配布したりすることができなくなる状況は、技術の進歩や知識の共有を阻害すると考えました。それもあり、「ソフトウェアの自由こそがユーザーの権利である」と主張して、商用UNIXとは一線を画すGNUプロジェクトを展開していきます。
5-2. 「GPL」と「フリーソフトウェア」の理念
GNUプロジェクトの最大の特徴は、ソフトウェアのライセンスに「GNU General Public License(GPL)」を採用したことです。GPLは、ソースコードの公開と改変・再配布の自由を保証し、「コピーレフト」という斬新な概念を導入しました。
ストールマン氏は、ソフトウェアには以下の4つの自由が必要であると提唱しました。
- プログラムを、目的を問わず実行する自由
- プログラムがどのように動作しているか研究し、必要に応じて改変する自由(ソースコードへのアクセスは必須条件)
- プログラムのコピーを再配布する自由
- プログラムを改良し、改良した版を公衆に広める自由
当時、商用ソフトウェアが主流だった中で、GPLの理念は画期的で、多くの開発者やユーザーを惹きつけることになり、大きなうねりを作り出していくことになります。
【第2回へつづく】
まとめ
UNIX戦争は、標準化を目指したはずのUNIXが、むしろ分裂と対立を深める結果となった歴史的事件でした。複数陣営の競争は短期的な混乱を生みましたが、その一方でオープンソース運動の台頭や、後の業界標準化への道筋を築くきっかけともなりました。UNIXの分裂と標準化の葛藤は、現代のIT業界にも多くの教訓を残しています。
主要参考文献
History of Unix, BSD, GNU, and Linux - CrystalLabs -- Davor Ocelic's Blog