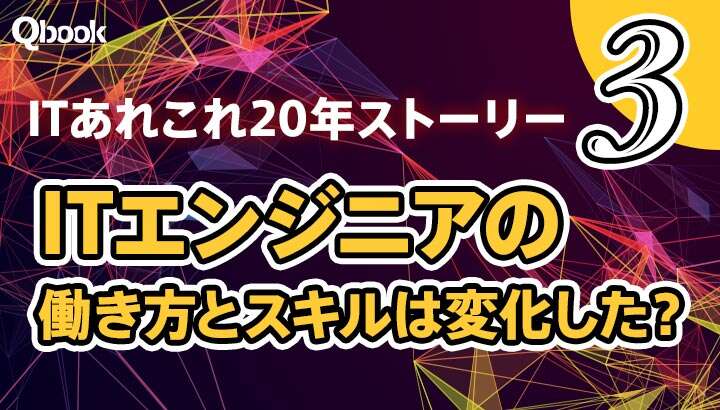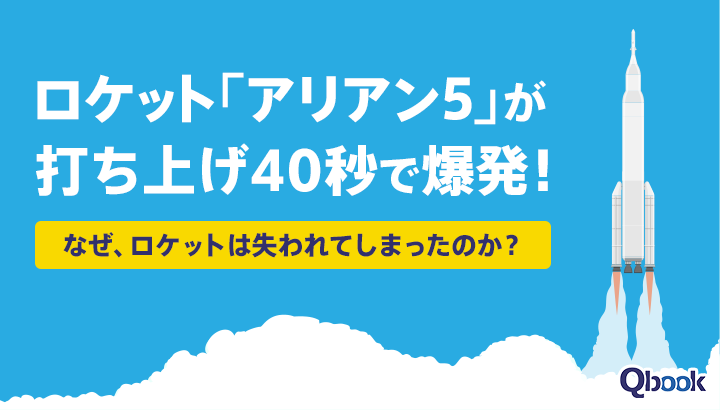ITエンジニアは、2005年から2025年の20年で大きな転換点をいくつも経験してきました。2005年当時には想像すらできなかったリモートワークの一般化、生成AIによる開発支援の浸透、そしてDXによるビジネスの構造変化。これらに伴って求められるスキルも変化し続け、今や非技術スキルや経営視点さえも重要視されるようになっているといわれています。
そこで今回は、この20年間の働き方と求められるスキルの変遷を見ていきたいと思います。
- もくじ
1. ITエンジニアの働き方20年変遷
1-1. 2005年から2025年、働き方は変わった
2005年当時、一般的なITエンジニアの働き方といえば、朝出社して決まったオフィスのデスクに座り、夕方まで開発に打ち込む固定された労働スタイルが中心でした。プロジェクトが佳境を迎えれば泊まり込みやいわゆる「デスマーチ(death march)」ということも珍しくなく、職場が生活の中心というITエンジニアも多く見受けられました。
この「当たり前」が揺さぶられたのは、2011年の東日本大震災がきっかけでした。大規模なインフラ障害と通勤困難により、「自宅で働けないか?」という議論が現実味を帯び始め、さまざまな試みがなされるようになりました。そして決定的な変化をもたらしたのが、2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行でした。
日本でも緊急事態宣言をきっかけに、急ピッチでリモートワーク(テレワーク)環境が整備され、リモートワークが一般化。Zoom、Slackなどを活用し、場所に縛られない働き方が一気に広がりました。
この劇的な変化は、単なる環境の変化にとどまりません。コミュニケーション手法の見直し、評価制度の再設計、セキュリティ対策など、組織のあり方そのものにまで及ぶものでした。感染拡大防止の観点からオフィス出社を制限しなければならなくなったことで、遠隔会議やオンラインでの共同作業が当たり前となり、技術面ではクラウドインフラやセキュアなVPNの導入、業務面ではチャットやナレッジ共有の仕組みが急速に進化しました。
国土交通省の「テレワーク人口実態調査」の結果を見ると、コロナ禍中よりもリモートワーク人口は減っていることが分かりますが、2005年と比べると大きくその数を増やしている実態がわかります。
1-2. リモートワークとハイブリッドワークの普及と現実
2025年現在、リモートワークや出社とリモートを併用するハイブリッドワークは珍しい働き方ではなくなりました。とくにIT系企業では、フルリモートを許容する企業も増加傾向にあります。人材確保の競争が激化するなか、優秀な人材に柔軟な働き方を提供することが採用競争力を向上させることにもつながっています。
しかし、リモートワークにすると生産性が下がる、といった意見もあり、2024年12月にはLINEヤフーがフルリモートを廃止し、SNSを中心に議論となりました。
また、米国のヤフーも2023年、在宅勤務を禁止し、話題となりました。
現実はもう少し複雑かもしれません。オンライン会議、情報共有の断絶、メンタルヘルスの悪化、成果の可視化の難しさなど、多くの課題も表面化しています。
例えば「自宅にいて一人で働くことで孤独感や疎外感が生まれやすい」「画面越しのやり取りでは伝わりづらいこともある」「時差やスケジュール調整が難しい」といった声も少なくありません。
このように、リモートワークは「魔法の杖」ではなく、設計次第で良くも悪くもなる選択肢の一つとして今後活用されていくのかもしれません。
1-3. 場所時間の壁がなくなりキャリアの選択肢が広がる
リモートワークのメリットの一つは、地理的な制約を取り払ったことです。東京都内の企業に所属しながら北海道に住む、あるいは週の半分だけ地方に移住するといった働き方も現実になっています。
また、時差を利用したグローバルチームの編成も進み、ITエンジニアが国境を越えて働くケースも増加しました。クラウドソーシングや副業解禁の流れもあり、「一社専属」ではない働き方も広まりつつあります。物理的な制約が緩和されたことで、ITエンジニアには新しいキャリアの道が開かれた、選択肢が増えたともいえます。
見方を変えると、「何をしたいのか」「どこで働きたいのか」「どんな価値を提供したいのか」といった、自分自身の軸がないと迷いやすくなる時代になったのかもしれません。
2. ITエンジニアに求められるスキルの「淘汰」と「創造」
2-1. 生成AIと自動化によるコーディングスキルの変容と新しい役割
生成AIがコードを書く時代が現実となりました。例えば「GitHub Copilot」や「Amazon CodeWhisperer」といったAIツールは、自然言語で記述された命令からコードを生成し、ITエンジニアの作業を補助してくれます。この20年で開発現場に生成AIや自動化ツールが急速に広まり、コーディングのスタイルが大きく様変わりしました。
この流れにより、従来の「手を動かして書くスキル」だけでなく、「何を実現したいのかを明確に構造化する力」や「生成AIが書いたコードを読み解き、修正するスキル」が重要視されるようになってきました。つまり、生成AIとの協働を前提とした新しい開発スタイルが主流になりつつあるのです。
そのためITエンジニアには、生成AIを活用して要件を整理したり、設計やアーキテクチャをまとめたりする力、AIが書いたコードの品質担保や最適化といった新しい仕事が発生しています。見方を変えると設計力やリテラシーのスキルが求められるようになったと言えるでしょう。
さらに言い換えると、2005年のように「コードをゼロからすべて自分で書ける自走力」よりも「チームで価値を最短距離で届けるスキル」が重視される時代になってきているようです。
2-2. 「2025年の崖」との対峙
「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に公表したレポート(DXレポート)で示されたキーワードです。これは、多くの企業が古いITシステム(レガシーシステム)を使い続けた結果、2025年以降に業務効率の低下やセキュリティリスクの高まり、人材不足による技術継承困難といった大きな問題が一斉に顕在化する恐れがあるという警鐘でした。
このため、日本のIT業界では「2025年の崖(2025年問題)」が大きく取り沙汰されることになりました。レガシーシステムの移行や保守を担える人材が急減し、システムをどう刷新するかが深刻な課題になったのです。
2025年現在、クラウドネイティブ、マイクロサービス、ローコード/ノーコードといった新しい技術や開発スタイルを身に着けたITエンジニアへの需要は急増しています。従来の保守・運用中心のスキルセットから、変化に対応できるシステム構築するスキルセットへとニーズは移り変わっています。
しかし現時点で「2025年の崖」は完全クリアとはいえず、今後しばらくはこれに対峙するITエンジニアやスキルも同時に求められることになります。
2-3. 次々に生まれる新職種と新スキル
ここまで見てきたように、急速にDX(デジタルトランスフォーメーション)が進むなかで、ITエンジニアの役割は単なる開発や保守にとどまらなくなっています。
例えば、「データサイエンティスト」「クラウドアーキテクト」「プロダクトマネージャー」など、新しい肩書きや職種が次々と登場しています。従来の「プログラマ」「システム管理者」「SE」といった枠組みにとどまらず、今後はさらに新たな職種も続々と増加していくはずです。
名称が細分化し、次々に現れる新職種(ポジション)に多く共通して求められているのは、技術だけでなく、ビジネス課題を理解し、技術で解決できるよう問題を俯瞰するスキルやコミュニケーションスキルです。さらに、部署や業務領域をまたいで連携するためのファシリテーション力も必要とされることが増えています。
DXは単なるIT化ではありません。企業の文化や働き方、組織構造にまで変革を迫る全社的取り組みです。つまり、ITエンジニア自身も組織変革の担い手としての意識が求められるようになっているようです。
3. これからのITエンジニアに求められる力
3-1. コミュニケーション・マネジメントなど非技術スキル
以前は、技術があれば無口でも許される「黙々と手を動かす職人」に憧れる風潮がありましたが、今やそんな時代ではありません。プロジェクトは多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成され、ビジネス部門との連携も欠かせません。これからのITエンジニアにとって、非技術的なスキルの重要性はかつてないほど高まっているといってよいでしょう。
重要になってくるのは、「自分の考えをわかりやすく伝える力」と「相手の意図を正しく汲み取る力」とされています。これらの基本的なコミュニケーション能力が、プロジェクトの成否を左右するほどの重みを持つようになりました。
また、メンバーの進捗やモチベーションを把握してプロジェクトを円滑に進める「マネジメント力」も求められるケースが増えました。これはリモートワークが増えたことで、「雑談」や「空気」で情報が共有される機会が減るため、意識的な情報共有やフォローアップが重視されるようになってきたからです。これまでは「間」でできていたことを、チャットツールやオンラインミーティングでも可能にするスキルが求められています。
その意味で、マネジメントやリーダーシップのスキルはこれまで以上に大きな価値を持つようになると推測できます。個人で成果を出すだけでなく、チームメンバーの強みを引き出し、組織全体に貢献できるITエンジニアが重宝されます。非技術スキルは今後もITエンジニアの「武器」になっていくでしょう。
3-2. 経営視点とビジネススキル
技術だけでなく「経営の視点」もITエンジニアに求められるようになってきました。これは単にコスト意識を持つという話ではなく、企業のビジョンや目標と技術戦略を結びつける力のことです。近年、ITエンジニアにもビジネス全体を俯瞰する力が求められるようになっています。
例えば、どのクラウドサービスを採用すべきか、開発リソースをどう配分すべかといった判断には、技術知識だけでなく「ROI(投資対効果)」や「市場ニーズ」といったビジネス的観点が欠かせません。こうした「経営視点」での判断がスキルの一部とみなされます。
近年では「BizDevOps(ビズ・デブ・オプス)」という言葉も登場しています。これは、ビジネス(Biz)、開発(Dev)、運用(Ops)が一体となって価値提供のスピードと質を高めていくという概念で、まさにITエンジニアが経営の一翼を担う時代を象徴しているといるかもしれません。
3-3. 変化に適応し続ける「学び続ける力」が必要
テクノロジーの世界では、「昨日の常識が明日の非常識」となることは珍しくありません。だからこそ、ITエンジニアにとって最も重要なのは「学び続ける力」だといえるでしょう。IT技術の進化はとどまることを知りません。AIやクラウド、業務プロセスの自動化、次々と登場する新しいフレームワーク――「一度身につけたら終わり」ではなく、「時代に合わせて学び直し、適応し続ける力」が不可欠です。
「学び続ける力」は、単なる技術のキャッチアップだけでなく、自分に足りないものを素直に認め、柔軟に考えて行動する適応性も含まれます。今後も変化が激しい環境のなかで、自分自身を「アップデート」し続けられる人こそが、生き残り活躍できるITエンジニアとなれるでしょう。
4. まとめ
2005年から2025年の20年間で、ITエンジニアの働き方とスキルには大きな変化が起こりました。リモートワークやAIの普及により、地理的・時間的な制約が薄れ、キャリアの選択肢も広がっています。同時に、ITエンジニアに求められるのは、技術力だけではなく、ビジネスや組織とつながる視点や、変化に適応する「学び続ける力」です。未来を切り開く鍵は、自分の可能性を広げるための意識的な選択と、成長を続ける姿勢にあるのかもしれません。