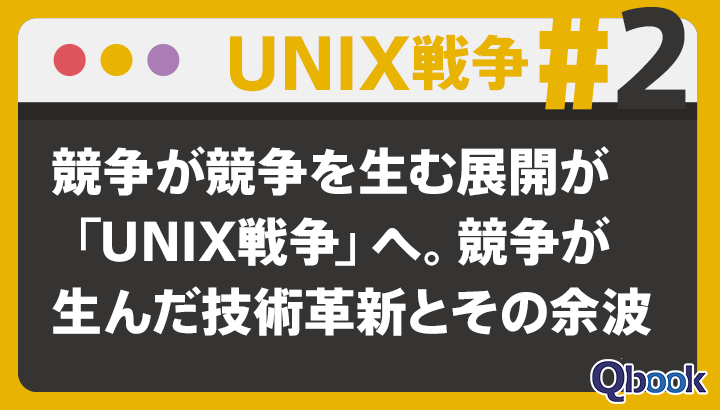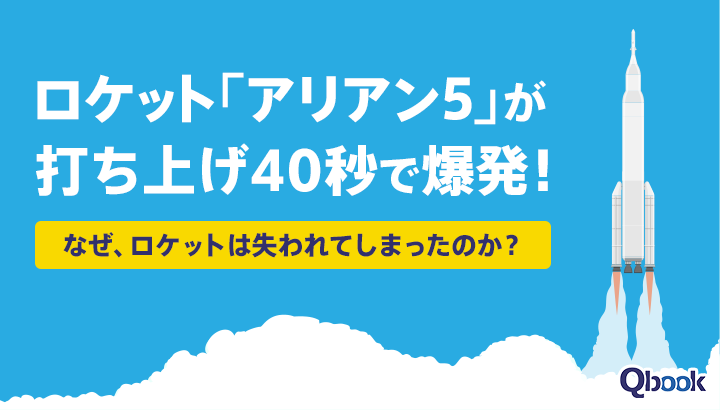1980年代後半から1990年代前半、コンピュータ業界は「UNIX戦争」と呼ばれる激しい標準化競争の渦中にありました。
AT&Tとサン・マイクロシステムズが主導する「UNIX International(UI)」と、IBMやHPなど多くの企業が結集した「Open Software Foundation(OSF)」が、それぞれ異なるUNIXの標準を掲げて対立していたのです。
今回は、UNIX戦争の動きをまとめた第二回をお届けします。
- もくじ
1. 【前回までのまとめ】UNIX戦争勃発の背景
★【UNIX戦争】とは?
UNIX戦争とは、1980年代末から1990年代にかけて発生した、UNIXの標準化を巡る技術的・商業的な企業間競争です。
「UNIX International(UI)」陣営と「Open Software Foundation(OSF)」陣営が、それぞれ異なるUNIXバージョンを展開し、業界を二分する争いを展開しました。
この争いは技術革新をもたらす一方、互換性の問題などから、UNIX市場の成長を阻害する一面もあり、終結を望む声が高まっていました。
1-1. 「System V Release 4(SVR4)」の影響
UNIXはもともとAT&Tベル研究所で開発された汎用OSで、1970年代から多くの大学や企業に広がっていました。しかし1980年代に入ると、各社が独自の拡張を施した「方言UNIX」が乱立して、互換性の問題が顕在化します。
その流れの中で標準化への期待が高まりを見せ、AT&Tとサン・マイクロシステムズ(Sun Microsystems)が「System V Release 4(SVR4)」の開発に着手。これが業界の分裂の引き金となります。
1-2. 「Open Software Foundation(OSF)」と「UNIX International(UI)」
「SVR4」の登場は他の大手ベンダー、とくにIBMやHPなどにとって脅威でした。彼らは自社のUNIXバージョンや市場シェアを守るため、AT&Tとサン・マイクロシステムズの連合に対抗する必要性を感じました。
そこでIBMやHPなどの大手ベンダーは1988年に「Open Software Foundation(OSF)」を設立。OSFは、独自のUNIX仕様(OSF/1)と関連技術を開発します。
こうして「UI(UNIX International)」と「OSF」という二大陣営が誕生し、互いに競争しながら異なるUNIXバージョンを展開する「UNIX戦争」の火ぶたが切られることになったのです。
「標準化」が目的だったはずの動きが、皮肉にも業界の「分裂」を加速させる結果になったのでした。
2. 「UNIX戦争」がもたらしたもの
UNIX戦争は業界に大きな混乱をもたらします。一方で、さまざまな技術革新や標準化の動きも促進しました。現代のIT業界に大きな影響を与えたUNIX戦争の「成果」と「余波」を見ていきましょう。
2-1. 「System V」と「OSF/1」はどう違う?
System V(とくにSVR4)とOSF/1は、どちらもUNIXの標準を目指して開発されたUNIX OSですが、その設計思想や技術的な特徴には違いがありました。
「SVR4」はSystem V Release 3、4.3BSD、XENIX、SunOSなど複数のUNIX系OSの機能を統合した「集大成型」のOSでしたが、各社による独自拡張もつづいてしまい、完全な標準化が困難な状況を抱えていました。
一方、「OSF/1」はマイクロカーネル(とくにMach)ベースのアーキテクチャを採用し、将来を見据えた柔軟性とモジュール性を重視していました。これが、後のUNIX系OSやLinux、さらには現代のクラウドインフラにも影響を与えることになります。
例えば、OSF/1の技術は「Tru64 UNIX(旧Digital UNIX)」に受け継がれることになり、System Vベースで独自進化したIBMが開発したUNIXベースのOS「AIX」も一部でOSF技術を採用しています。
2-2. さまざまな技術が劇的に進化
UNIX戦争の時代は、業界が分裂し競争した結果、さまざまな技術が急速に進化した時期でもありました。
各陣営が自らのUNIXを差別化するために、ファイルシステム、ネットワーク機能、セキュリティ、GUIなど、OSの各コンポーネントの開発を活発に行ったためです。
例えば、サン・マイクロシステムズが開発した「NFS(Network File System)」は、異なるUNIXシステム間でのファイル共有を可能にし、後の分散コンピューティングの基盤となりました。
また、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の標準化を巡る「Motif」や「Open Look」の争い、ネットワーク機能の強化、マルチプロセッサ対応や分散処理技術の発展など技術革新がいくつも達成されることになります。
このような技術革新は、現代のLinuxやmacOS、さらにはクラウドOSにまで受け継がれることになります。
2-3. 「SPARC」と「Solaris」の登場
UNIX戦争のさなか、サン・マイクロシステムズは独自のRISCプロセッサ「SPARC」と、その上で動作するOS「Solaris」を投入します。SPARCは高い性能と拡張性を持ち、「Solaris」科学技術計算やサーバ用途で広く採用されました。
「Solaris」はSVR4ベースのUNIXとして、堅牢なマルチタスク処理やネットワーク機能を備え、技術的に非常に洗練されたOSとしてエンタープライズ分野で存在感を示し、当時の代表的なOSとなりました。
「Solaris」がSPARCとの親和性を高めることで、ハードウェアとソフトウェアの最適化が実現され、とくに金融や通信といった分野で圧倒的な信頼を得ました。このような垂直統合型の開発手法は、後にAppleがMacやiPhoneの開発に取り入れています。現代でも、SPARCアーキテクチャの理念は、多くのサーバOSやクラウド基盤に影響を与えているといってよいと思います。
2-4. テレビCM等々でも「場外乱闘」
UNIX戦争は技術やビジネスの場だけでなく、広告戦略の面でも激しい競争が繰り広げられました。
各社は自社のUNIX製品をアピールするため、テレビCMや雑誌広告に多額の資金を投入。
例えば、サン・マイクロシステムズは「The Network is the Computer」というキャッチフレーズでネットワーク時代の到来を強調し、IBMやHPも「信頼性」や「拡張性」を前面に出した広告を展開しました。
こうした広告合戦は、当時のIT業界の熱気と競争の激しさを象徴しています。現在では、当時のCM映像がYouTubeなどで視聴でき、時代の雰囲気を感じることができます。
サン・マイクロシステムズの「The Network is the Computer」は有名なキャッチフレーズで、この言葉で検索をすると今でも当時のCM動画を見ることができます。
3. 「Common Open Software Environment(COSE)」の設立
分裂と競争がつづいたUNIX戦争ですが、やがて業界全体で「標準化」への機運が高まっていきます。UNIX戦争が長期化すると、業界全体で「このまま分裂をつづけていては顧客の信頼を失い、市場そのものが縮小しかねない」という危機感が高まります。
1993年、ついにIBM、HP、サン・マイクロシステムズなど主要ベンダーが手を組んで、「Common Open Software Environment(COSE)」を設立します。
COSEは、これまでバラバラだったUNIX陣営が共通のソフトウェア基盤を作ることで、アプリケーションや開発者の利便性を高め、業界全体の発展を目指すプロジェクトでした。COSEの設立は、UNIX戦争終結への転換点となる出来事だったといえます。
COSEの登場で、かつて激しく争った企業が共通のプラットフォームを構築しようとする姿勢が多くの技術者や企業に希望を与えたと思います。
4. 「Linux」と「BSDの子孫」たちの誕生
UNIX戦争のさなか、オープンソースの新たな潮流が生まれていました。LinuxやBSD派生系の登場は、業界に大きなインパクトを与えることになります。
4-1. 1991年、「Linux」誕生
UNIX戦争が激化していた1991年、フィンランドの学生リーナス・トーバルズ氏(Linus Torvalds)によってLinuxカーネルが公開されました。当初は学習目的の小規模なプロジェクトでしたが、トーバルズ氏は自らの開発したカーネルをインターネット上で公開して、世界中の開発者から改良案を募るという、当時としては画期的な手法を採用します。
LinuxはUNIX互換のフリーOSとして、世界中の開発者が参加するオープンソースプロジェクトに発展していきます。UNIX戦争で業界が分裂し、商業UNIXの標準化が遅れる中、Linuxは「誰でも自由に使えるUNIX互換OS」として急速に普及。商業的な思惑に縛られない開発スタイルが多くの技術者や企業を惹きつけました。
興味深いのは、Linux自身もUNIXを参考にしつつ、POSIXに準拠して開発された点です。つまりUNIX戦争の「果実」ともいえる標準化の成果を活かしながら、全く新しい自由なエコシステムを築いたのです。UNIX戦争の混乱が、逆説的にLinuxの台頭を後押ししたともいえるでしょう。
4-2. 「BSDの子孫」たち
UNIX戦争の後半ごろ、1993年には「NetBSD 0.8」や「FreeBSD 1.0」など、BSD系のフリーOSも登場します。
「BSD(Berkeley Software Distribution)」は、カリフォルニア大学バークレー校で開発されたUNIXの派生バージョンであり、もともとUNIXの学術的な派生系として発展してきましたが、1980年代後半から法的な問題により長く沈黙していました。
しかし、1992~1994年ごろにはBSD系OSの法的問題の問題が和解により段階的に解決され、自由に配布できるOSとして復活したのです。
「NetBSD」「FreeBSD」「OpenBSD」等はいわばBSDの子孫です。これらはセキュリティ、ネットワーク性能、安定性といった点で高く評価され、とくにFreeBSDは商用サーバや組み込み機器で広く使われるようになりました。
【第3回へつづく】
まとめ
1980年代後半から1990年代前半にかけて繰り広げられたUNIX戦争は、分裂と競争を通じて業界に混乱をもたらしましたが、その過程で多くの技術革新や標準化の動きが生まれました。AT&Tとサン・マイクロシステムズが主導するUIと、IBMやHPなどが推進したOSF/1の対立は、技術開発を加速させ、その後も利用される重要な技術を生み出しました。しかし、UNIX戦争は皮肉にもLinuxやBSDなどオープンソースの隆盛を後押しすることにも繋がっていました。
主要参考文献
History of Unix, BSD, GNU, and Linux - CrystalLabs -- Davor Ocelic's Blog