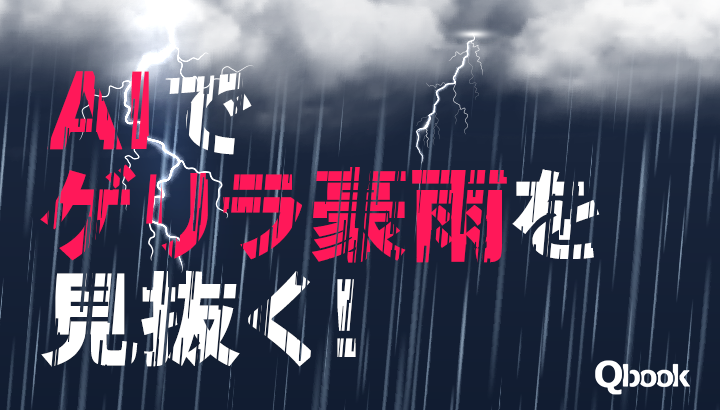突然のゲリラ豪雨や局地的な大雪のニュースを見るたびに自然の脅威を感じている方も多いでしょう。大きな被害を防ぐために欠かせないのが天気予報です。天気予報は、今、AIによって大きな進化を遂げつつあるといわれています。これまで主流だったスーパーコンピュータによる物理モデルにくわえてAI技術が導入されて、予測の精度が格段に向上しているといいます。そこで今回はAIと天気予報の最近の状況についてまとめてみました。
- もくじ
1. 天気予報の基礎とAI導入の背景
1-1. スパコンが支える物理モデル
これまで天気予報は、スーパーコンピュータを使って大気の動きを物理モデルで解析する方法が主流でした。これは「数値予報」と呼ばれ、気温、湿度、風速、気圧といった大量の気象データをもとに、大気の流れを物理法則に従って計算する手法です。日本では気象庁がこのモデルを活用しており、世界でも最高レベルの精度を誇ります。気象庁のスーパーコンピュータは、毎日何千万もの計算を行い、未来の天気をシミュレートしています。
物理モデルは複雑で計算量が非常に多いため、膨大な処理時間が必要です。くわえて、計算の前提となる初期データのわずかな誤差が、予測結果を大きく変えることもあります。膨大な処理時間が、ゲリラ豪雨のような局地的な天気の急変を予測する上で課題となっていたといわれています。
1-2. AIと気象データ
近年、こうした予測の難しさを補う手段として登場したのが、AI(人工知能)による予測モデルです。AIは、過去の膨大な気象データを学習することで、パターンを見つけ出し、将来の天気を短時間で推定できる特性があります。
AIモデルの多くは「ディープラーニング」技術をベースにしていて、人間では気づけないような複雑な関係性やパターンを自動的に抽出できます。これにより、これまでのモデルと異なるアプローチから天気を予測することが可能になりました。
GoogleのDeepMindが開発した「GraphCast」は、まさにこの分野の代表例です。2023年11月に発表されたこのAIは、従来の数値予報モデルと比べて、より短時間で高精度な予測ができるとされています。具体的には、10日間の天気を予測する場合、従来ではスパコンを数時間稼働させていた計算が、GraphCastでは1台のマシンを1分稼働させるだけでできるとGoogleは説明しています。
ただし、GraphCastなどのAIモデルは、従来の物理モデルを完全に置き換えるものではなく、現時点では補完的に活用されています。今後は両者の強みを活かしたハイブリッド運用が主流となる見込みです。
GraphCast: AI model for faster and more accurate global weather forecasting(Google DeepMind)
1-3. 予測困難な現象への挑戦
AIの活躍が期待されているのが、「予測が困難な現象」の予測です。最大の関心事の一つともいえるゲリラ豪雨は、積乱雲が急速に発達し、狭い範囲に短時間で大量の雨を降らせる現象であり、突発性と局地性から、従来モデルでは正確な発生場所や時間を予測することが難しいとされていました。
日本のウェザーニュースは、AIを使ってゲリラ豪雨を事前に予測する技術を開発し、アプリ「ウェザーニュース」などでリアルタイムの予報情報を提供するようになりました。
全国から寄せられるユーザーの天気報告や気象センサーから得られたデータをAIで分析させて、雨雲の発達傾向や移動予測をしています。これにより、「30分後に突然ゲリラ豪雨がくる」といった警戒情報が早めに得られるようになります。
2. AIによる天気予報の進化事例
2-1. 数値予報とAIの融合
AIと数値予報モデルの融合は、気象予測技術の「次のステージ」ともいえる動きです。従来の数値予報は物理法則に基づく極めて堅実な予測方法ですが、限られた解像度や計算能力の壁がありました。ここにAIの能力をくわえることで、予測の精度やカバー範囲をさらに向上させる試みが進んでいます。
たとえば、欧州中期予報センター(ECMWF)は、従来の数値予報モデルの出力をAIで後処理(ポストプロセス)することで、より精密な予報を得ようとする研究を進めています。2025年2月には、従来の統合予測システム(IFS)と並行して人工知能予測システム(AIFS)を運用開始しています。
AIは初期値の改善にも貢献します。観測データには誤差や不足している部分がありますが、AIは過去の膨大な観測データと予報結果を学習することで、観測誤差を補正したり、データが少ない地域の気象状態を推測したりして、より精度の高い初期値を生成することができます。また、AIは数値予報モデルの計算結果を補正するためにも用いられます。
このようにAIによる気象予測は高精度化が進む一方で、まだ、物理的な因果関係の説明や観測データのバイアスへの対応など、解決すべき課題も残されているとされています。
2-2. 局地予測におけるAIの力
ここまで述べてきたように、天気予報の課題の一つが「ピンポイントでの予測」つまり局所の予測があります。数km単位といわれる局所的な変化を、従来のモデルだけで捉えるのは困難でした。
ここで力を発揮すると考えられたのがAIでした。気象レーダーや気象衛星が捉えるリアルタイムの膨大な画像データを、AIが瞬時に解析して、雨雲の動きや発達を予測できるからです。
日本の株式会社メトロウェザーは、ドップラーライダー「Wind Guardian」とAIを組み合わせて、都市部での風の流れや突風をリアルタイムに予測する技術を開発していると紹介されています。
2-3. 海外のAI天気予報の動向は?
海外でもAIによる天気予報の進化は加速しています。とくに注目されているのが、先ほど紹介したGoogle DeepMindによる「GraphCast」です。GraphCastは、グラフニューラルネットワーク手法を活用し、地球全体の気象状況を高精度にシミュレートできるとされています。
中国では、AI技術を気象予測システムに統合する取り組みが進んでおり、とくに洪水や干ばつといった極端気象現象の予測精度向上にAIを活用しようとしています。
アメリカIBMの「Prithvi WxC」やMicrosoft、欧州の気象スタートアップなども、AIによる天気予報サービスの開発を進めており、グローバルに「AI化」の波が広がっています。
IBM and NASA's versatile AI model for weather and climate(IBM Research)
Microsoft Start Weather Team Unveils Revolutionary 30-Day Forecast Model(WinBuzzer)
各国がAI技術を活用して気象予報に取り組む背景には、気候変動によって予測が困難になる現象が増えていることがあります。猛暑、洪水、山火事、台風の激甚化といった異常気象への備えとして、AIを活用したリアルタイムかつ高精度な予測は、国際的な社会課題への対応手段となっているといってよいでしょう。
3. 日本と世界の天気予報事情
3-1. 日本独自の「天気予報」の進化
日本の天気予報は、世界的にもきめ細やかさで知られています。その背景には、全国に張り巡らされた高密度な観測ネットワークや、独自に発展した雨雲レーダー技術があります。
気象庁が運用する「高解像度降水ナウキャスト」は、250m四方という非常に細かい解像度で、数分先から1時間先の降水状況を予測するものです。刻々と変化する雨雲の動きをリアルタイムで捉え、ゲリラ豪雨のような突発的な現象の発生や移動を詳細に予測することを可能にしています。
日本は防災意識が高いこともあり、気象庁、NHKなどの公共放送、民間の気象会社が連携して、国民への情報伝達を重視しています。線状降水帯などの危険な気象現象については、その発生の可能性を早期に注意喚起できる体制が整っているといえます。
3-2. 海外各国の天気予報は?
海外における天気予報の信頼度や人気度は、国や地域によって大きく異なります。
アメリカでは、竜巻やハリケーンなどの甚大な気象災害が頻繁に発生するため、国立気象局(NWS)が提供する気象情報は非常に重視されているようです。
とくに、災害時には緊急警報システムを通じて迅速に情報が伝達される体制が整っています。また、民間気象会社も非常に発達しており、ビジネスやレジャーなど、多様なニーズに応じた詳細な気象サービスが提供されています。
ヨーロッパでは、欧州中期予報センター(ECMWF)のような国際機関が高度な数値予報モデルを開発し、各国の予報を支えています。
発展途上国においては、気象観測網の不十分さや予報技術の限界から、天気予報の信頼度が低い地域も少なくないとされます。しかし、気候変動の影響で極端な気象現象が増加していることもあり、今後は国際協力や技術支援を通じて、天気予報の改善への取り組みが加速していくと思います。
天気予報は農業や交通、観光など、経済活動に直結するため、信頼性の高い情報が求められています。日本のようにゲリラ豪雨を数分前に予測する技術が世界に広まっていくのかもしれません。
3-3. 天気予報データ活用の未来
今後の天気予報は、「オープンデータ」と「AI」の融合がますます重要になると考えられています。気象庁は観測データや予報データの一部を「気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)」などを通じて民間にも公開しています。
オープンデータ化された気象データにより、大学やスタートアップ企業などが自由に気象データを分析し、新たな予測モデルの開発や、これまでになかったサービス創出に挑戦できるようになります。将来的には、AIが個人の行動やニーズに合わせて最適な天気情報を提供し、災害リスクの低減や生活の質向上に貢献することができるようになるかもしません。
気象予報データは、単に「今日の天気」を知るためだけでなく、重要な社会のインフラとしての役割が強まっていくことでしょう。
4. まとめ
AIの登場によって、天気予報の世界は大きく変わりつつあります。
スーパーコンピュータによる数値予報にAIを融合することで、予測精度の向上や局地的な現象への対応が進み、日本を含む各国で実用化が加速しています。今後もオープンデータとの連携や、AIによる新しい天気予報サービスの登場に注目が集まるでしょう。