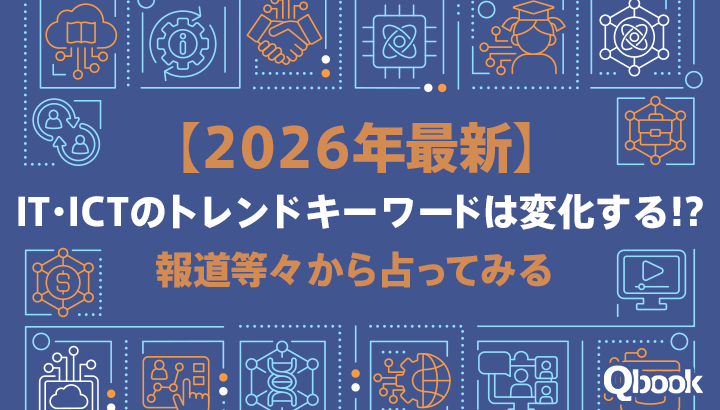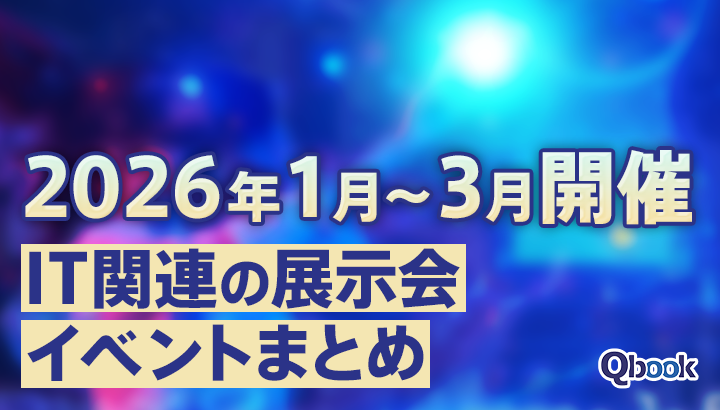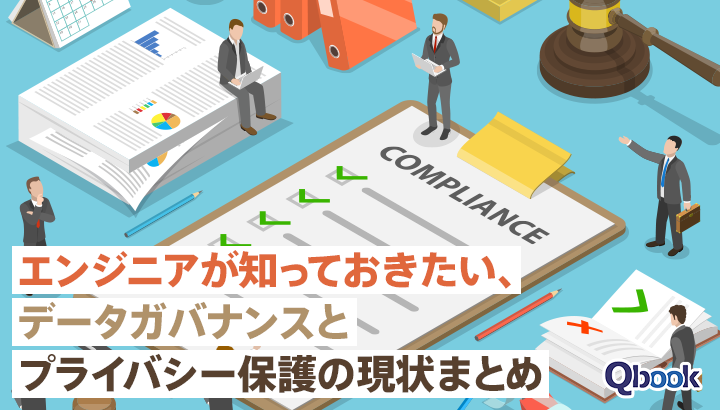5G(第5世代移動通信システム)は、スマートフォン・携帯電話などで用いられる次世代通信規格の5世代目です。
5Gが与える影響は情報技術分野だけにとどまらず、IoTを支える基盤技術になります。
そこで今回は、5Gとは何か、特長と通信技術、ビジネスに与える影響についてご紹介します。
- もくじ
1.5G(第5世代移動通信システム)とは?
5Gとは「第5世代移動通信システム」を意味する言葉です。スマートフォンなどで用いられる通信規格の5世代目を指します。
5Gの「G」は「世代」を表す「Generation」という言葉の略です。
これまでの通信規格を振り返ると、1Gは音声通話が中心のアナログ通信でした。
2Gが初のデジタル通信規格で、メールやネットの閲覧が可能になり、3G、4Gでデータ容量および通信速度がアップしてきました。
当然のことながら、5Gに進化することによって通信容量はさらにアップします。
2.5Gの3つの特長
5Gは「高速大容量」「多数同時接続」「超低遅延通信」の3つの特徴があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 高速大容量
一つ目の特徴が「高速大容量」です。
4G・LTEの通信速度が50Mbps~1Gbpsくらいであるのに対し、5Gでは10 Gbps~20Gbpsにまで向上します。
そのため、4G環境で映画を1本ダウンロードするのに30秒程度かかっていた場合、5Gでは3秒で完了する計算になります。
これまで処理に時間がかかっていた大容量のデータも高速でやり取りできるようになります。
2-2 多数同時接続
二つ目の特徴が「多数同時接続」です。
4Gと比べて、1平方キロメートルあたりの同時に接続できるデバイスの数が約10倍に増えました。
それにより、IoT活用が進んだり、大人数が集まるライブ会場・スタジアムなどでも、ネット回線が使えるなど、より快適にインターネット通信ができるようになりました。
2-3 超低遅延通信
三つ目も特徴が、「超低遅延通信」です。
5Gでは端末の近くにサーバを構築する「エッジコンピューティング」を使用することで、超低遅延通信が可能になりました。(詳細は3-4で解説します)
4Gでは10ミリ秒ほどの遅延がありましたが、5Gでは1ミリ秒ほどです。
これにより遅延が大幅に解消され、VR技術を応用した遠隔地での手術など、リアルタイムでの画像処理が要求されるシステムが今後実現していくことも考えられます。
この他にも、野球場やサッカースタジアムをVR技術と融合させ、あたかもその場にいるような臨場感のあるバーチャルスタジオでのスポーツ観戦システムも実現可能です。
3.5Gを実現する通信技術
5Gを実現した通信技術を、具体的にご紹介します。
3-1 高周波数帯の活用
「高速・大容量化」を実現するための基盤技術がこの高周波帯の利用です。
5Gでは高速・大容量通信を実現するために、4Gで使われてきた3.6GHz以下の周波数帯だけではなく、さらに3.6~6GHz帯や、28GHz帯までも利用することを予定しています。
電波は周波数が高くなるほど特定の方向に強い信号を送ることが可能です。
5Gではこの特性を利用して電波を特定方向のユーザーに向けることにより、遠くまで飛びやすくできます。
さらにビームフォーミングと呼ばれる技術を用いて移動するユーザーを追尾することが可能です。
これによって高速で移動する対象に電波を送りながら素早く基地局を切り替えられるようになり、途切れることなく高速・大容量通信を行うことが可能です。
コネクテッドカーのように常にネットに接続しながら走行し、車両とリアルタイムで通信できるようになるのです。
3-2 超多素子アンテナ技術
また、高周波の指向性の高い電波をやり取りするために必要となるのが、MIMO(multiple-input and multiple-output、マイモ)と呼ばれる方式を採用している超多素子アンテナ技術です。
これは複数のアンテナ素子から同じ周波数で同時に信号を送信する技術で、使用する周波数帯域を増やさずに通信の高速化を実現します。
この技術はすでにLTE/LTE-Advanced技術で採用されていますが、さらに高速・大容量化する研究開発が5Gに向けて進められました。
3-3 ネットワークスライシング
どんなに電波での通信スピードが向上してもデータ通信自体に渋滞が起こっていては肝心の通信速度をアップさせることはできません。
特にIoTでは多接続を必要とし、現在の100倍の同時接続を目指しているため、データの遅延が発生したり信頼性が低くなったりするリスクが高まります。
その問題を解決するために導入されるのがネットワークスライシングと呼ばれる技術です。
現在は全てのネットワーク通信が一つの経路でやり取りされていますが、これを通信サービスごとに分割しデータの流れをスムーズにするというものです。
例えば、現在のネットワーク技術は一般道しかなく渋滞が起きやすい道路のようなもので、これに高速道路やバイパスを開通させて渋滞を回避するようにします。
これにより、5Gは「多接続」「低遅延・超高信頼性」を実現することが可能になりました。
3-4 エッジ・コンピューティング
ただし、「多接続」「低遅延・超高信頼性」を実現するには、ネットワークスライシングだけでは十分とは言えません。
5Gではネットワークを介してサーバー側でAIやビッグデータ処理など高負荷な演算処理を行う必要があります。
そのため従来のクラウド技術では、データを送ってから演算処理を行っている間に通信の遅延が発生してしまいます。
そのような場面で有効なのが、エッジ・コンピューティング技術です。
これは端末の近くにサーバーを分散配置するネットワーク技法の一つで、ユーザーや端末の近くでデータ処理することで、上位システムへの負荷や通信遅延を解消します。
これによりコネクテッドカーなどの移動する機器でも、途切れることなく通信と演算処理を行うことが可能です。
4.5G時代、ビジネスモデルはB2XからB2B2Xへ
5G時代にはビジネスの形がB2XからB2B2Xへ変わる可能性が秘められています。
考えられるビジネスモデルについてご紹介いたします。
4-1 B2X
B2Xとは今までの4G環境で行われていたビジネスモデルと同等です。
Bは「通信事業者」を表しており、Xは「消費者や企業」のことを指しています。
すなわち、「通信事業者がエンドユーザーに対して通信サービスを提供することにより対価を得るビジネスモデル」のことです。
例えば、NTTドコモが携帯端末とともに通信回線を提供するようなことです。
MVNOなどの格安通信事業者が現れましたが、通信業者の種類が変わっただけでありB2Xの域を出てはいません。とはいえ、5G時代においても、B2Xのビジネスモデル自体は残り続けるでしょう。
4-2 B2B2X
5G時代に注目されるのが、B2B2Xです。
B2B2Xは、「通信業者が企業にサービスを提供するだけでなく、サービスを提供した企業のアプローチする顧客を含めたビジネスモデル」のことです。
B2B2Xでは通信事業者は通信サービスのみでなく、企業に合わせた+αの情報を提供します。例えば、タクシー間の通信を提供している場合には交通状況の情報や潜在顧客情報などを提供します。
また、B2B2Xでは中間に位置する企業は、様々な業界の法人になり得ます。そのため、通信サービスを使用したいという顧客以外の様々な問題解決にアプローチできます。
5.5Gでビジネスはどう変わるのか
5Gの導入が進むことでインターネット関連技術は飛躍的に進化し、それによりビジネス環境も大きく変化します。
総務省は「IoTサービス創出支援事業」と題して地方公共団体、民間企業、大学、民間非営利団体(NPO)等のIoT導入を積極的に推進しています。
例えば、ある医科大学が「ウエアラブル血圧測定器と口腔ケアIoTによる脳卒中AI予防対策サービス事業」に乗り出しているように、従来の技術だけでは不可能だった、新しい領域におけるビジネス創出への取り組みが行われています。
これらの技術のほとんどは、まだ実証実験が行われている段階にすぎません。
そのため今後は商用利用の段階で大規模なソフトウェア開発需要の発生が予想されますが、変化は量の面だけではなく質の面でも起こります。
5Gの実用化を見越した試みは従来のシステム開発と違い、AIやエッジ・コンピューティングなどの新しい技術も複合的に絡めた総合的な技術開発が必要とされます。
新しい技術を取り入れたソフトウェア開発は試行錯誤を繰り返すことが予想され、開発手法やテスト手法も従来とは異なる観点が必要になるかもしれません。
また、処理するデータ量や関連機器が飛躍的に増えることから、情報セキュリティの強化など従来以上に考慮すべき課題が増えることも想定されます。
6.5Gビジネスの注意点
5G通信をビジネスに活用することで様々な業界で発展が予想されますが、便利になる反面、注意しなくてはならないことがあります。
デメリットも理解しての活用をしましょう
6-1 セキュリティ面でのリスクがある
5Gの導入が進むにつれて、5G回線を利用する様々なIoT機器がネットワークに繋がります。
そのため、ルーターやPCだけでなく、WEBカメラやプリンター、レコーダーなどもサイバー攻撃の対象となることが考えられ、リスクの拡大も懸念されます。
現在も様々な企業において、セキュリティ事故・事件が発生しているため、セキュリティツールの導入・脆弱性診断の実施など対策が必要なります。
6-2 情報量が増える
5Gの特徴である「大容量・高速通信」によりネットワーク上に流れる情報量が増えます。
2015年の通信量が6ZBで、2020年の通信量は44ZBと言われています(ZB=ゼタバイト、1ZBは1TBの10億倍)。
今後も情報量が増えると予想されるため、悪用される対象となる情報も増えるでしょう。そのため、情報漏洩の危機に晒されやすいのです。
企業の中はもちろんですが、エンドユーザーで使用しているデバイスから情報が漏洩してしまう可能性も増えていくため、社内外で情報の取り扱いはより慎重にしていきましょう。
まとめ
5G(第5世代移動通信システム)は、スマートフォン・携帯電話などで用いられる次世代通信規格の5世代目です。
大きな特徴は、「高速大容量」「多数同時接続」「超低遅延通信」であり、今まで以上に快適にインターネット通信ができます。
5Gの普及が進んでいくとビジネスモデルや環境も変わっていくことが考えられます。
ただし扱える情報が増える一方でセキュリティや情報漏洩など企業として注意すべきことも増えていきます。
セキュリティ対策やネットリテラシー教育など、企業としてできる対策も同時に進めていきましょう。
▼企業におけるネットリテラシーについてはこちらをご覧ください。