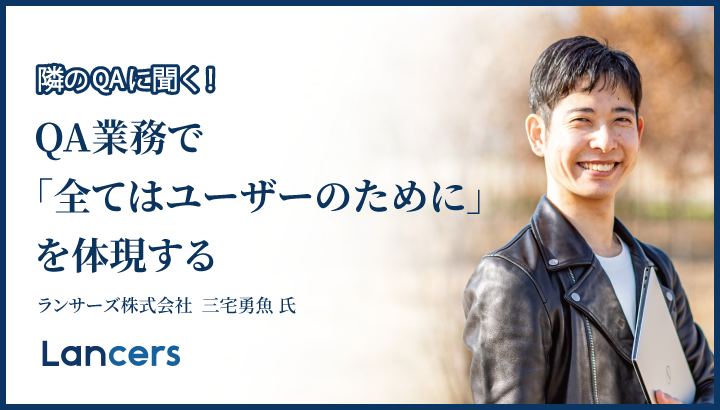さまざまな現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。社会のデジタル化が進み、クラウドサービスを活用して企業変革を推進する時代になっています。その流れもあり、さまざまなクラウドサービスへの関心が高まりを見せ、同時にアプリやソフトウェアの品質も重視されるようになりました。そんな中、他のチームでは、どのようにQA業務を実施しているか、気になっているエンジニアの方も多いのではないでしょうか?
本記事では、QAに取り組む上でのポイントなどを伺い、皆さまにお伝えします。
今回はランサーズ株式会社の三宅勇魚さんに、同社の専門チームやポジションがない独自のQA活動についてお話をいただきました。
今回インタビューを受けてくださった方

- 三宅 勇魚 氏
ランサーズ株式会社 Productivityチーム
豊田工業高等専門学校卒業後、大手エアコンメーカーに入社。製造現場にて組み立てや改善を担当し、トヨタ式「カイゼン」を学ぶ。エンジニア派遣の会社に転職し、 VBAでの業務改善やコンサルティングの経験を経てWeb系エンジニアにキャリアチェンジする。2021年ランサーズにジョイン。Productivityチームにて開発生産性向上のための業務を担当。大阪からフルリモートで勤務中。
- もくじ
1.ものづくりの経験を生かしてDevOpsの実現を目指す

――まずはこれまでのご経歴をお聞かせいただけますか。
私のキャリアはエアコンメーカーからスタートしました。そこで3年ほど働き、トヨタ生産方式をはじめとする、ものづくりの基礎となる体系的な知識を学びました。その後、業務改善エンジニアという仕事を経て、現在はランサーズのProductivityチームに所属しています。トヨタ生産方式は、ウェブの世界では「リーン開発」や「リーンマネジメント」と呼ばれます。
製造業で培った知識や経験を活かしながら、今はDevOpsの実現をミッションとして幅広い業務を担当しています。
――製造業からウェブ業界だと大きく異なる印象ですが、どんな転職動機があったんですか。
私は学生の頃に情報工学を専攻していました。その当時は卒業後プログラマーになることへのハードルがかなり高いと感じていて、進路選択ではソフトウェアの世界に踏み込むことができませんでした。それで一度は機械系の会社に就職しました。でも製造の仕事を通して手を動かすうちに、やはりソフトウェアの世界でやりたいことがあると自覚し始めました。製造で得た仕事への自信から、当初感じていた心理的ハードルも徐々に下がっていき、やっぱりソフトウェアの世界に行きたいと思って転職しました。
――数ある企業の中でランサーズを選ばれたのは、そうした製造業や業務改善エンジニアの経験を活かせるからですか。
経験もそうですが、一番はカルチャーが自分の価値観と合っていたからです。ランサーズの行動規範「ランサーズWay」の1つに、「アクションアジャイル」というものがあります。これは「ユーザーにとって真に価値のあるものをより早く提供するために、率先して動いていこう」という内容ですが、私は製造業でもウェブ業界でもその部分は一致して重要だと思っているので、目指す先が同じというのは大きなポイントでした。
2.コロナ禍によりオンラインでの仕事マッチングの需要は伸びている
――御社のサービス・ミッションについて教えてください。
ランサーズは、仕事を発注したい企業と、スキルを持つ個人をマッチングするプラットフォームを提供しています。350種類以上の多様なカテゴリで実績を持つプロに仕事を依頼でき、低コストでスピーディーに成果物を得られるのが特徴です。
当社は「個のエンパワーメント」をミッションに掲げています。これは、個人の力が最大限発揮できる社会を実現するということです。個人の持つ才能やスキルが誰かに届いて、それによって価値を生むことができれば、住む場所や働く時間に縛られず、より自分らしいライフスタイルが実現しますよね。ランサーズでは、それこそが「個のエンパワーメントが実現した社会」という風に考えています。
――コロナ禍をきっかけに多くの企業でリモートワークが普及しましたが、そんな社会背景の中でランサーズを使う方は増えているのでしょうか。
コロナ前後の登録者の増加数で言いますと、コロナ前の2019年4月とコロナ禍の2020年4月の1カ月間を比べた場合、動画編集者などを含む映像クリエイターの登録者数が約500%増加したというデータが出ています。コロナ禍で在宅勤務が主流になったことや、通勤時間がなくなったことから時間の余裕ができ、今まで挑戦してみたかったものに挑戦する人が増加したと考えられます。
また、発注側においても、コロナ禍でYouTubeやTikTokなどの動画コンテンツが人気となり、サイトや広告なども動画を利用する場が広がりました。それによって「動画編集」のカテゴリの発注数の増加率がコロナ前後で最も高い結果となるなど、社会背景に伴い、新たな利用者が増えているのではないかと思います。