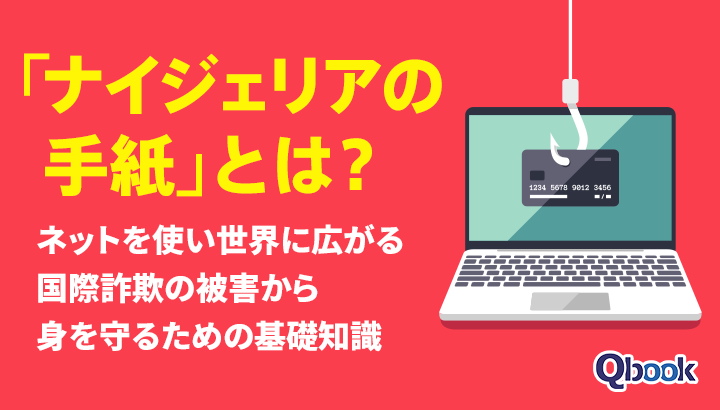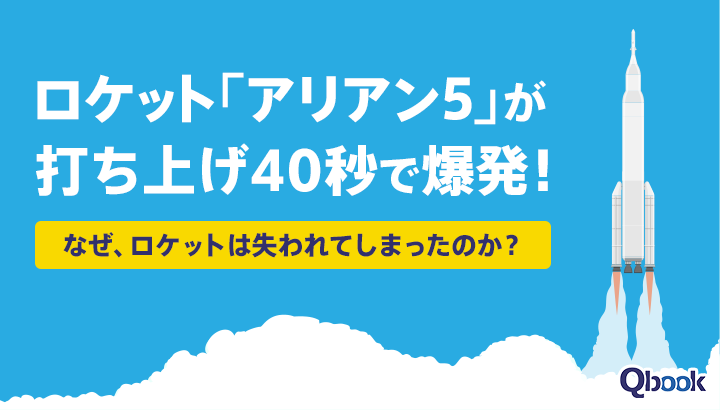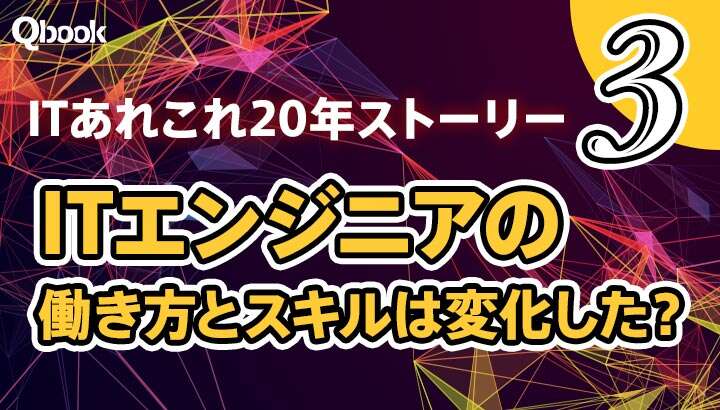インターネットが普及した現代社会において、ビジネスからプライベートまで欠かせないコミュニケーションツールの一つとなった電子メール(email:Eメール)。
毎日何気なく使用していますが、その誕生には興味深い歴史があります。
そこで、世界初のEメール送信から現代に至るまでの進化の過程、そして豆知識まで、Eメールについてまとめてみました。
- もくじ
1. 世界初の「Eメール」送信元・内容は?
1-1 1971年、世界で初めてEメールが送信された!
1971年、プログラマのレイ・トムリンソン(Ray Tomlinson)氏によって、世界で初めて電子メール(Eメール)が送信されました。
当時、トムリンソン氏は、インターネットの前身となるアメリカ国防総省のARPANET(アーパネット)プロジェクトに参加しており、異なるコンピュータ間でやり取りするメッセージ送信プログラム「SNDMSG」を開発しました。
それまで、メッセージのやり取りは同一コンピュータのユーザー間でのみ可能でしたが、彼が電子メールシステムを開発したことにより、ネットワークを介した通信が可能になったのです。この歴史的な出来事が、現代のEメール文化の基礎を築き、私たちのコミュニケーション方法を大きく変えることとなりました。
ある意味、電話以来の革命ともいえるEメールシステムを開発したレイ・トムリンソン氏の名は、電話を発明したグラハム・ベル(Graham Bell)氏に匹敵するものといえるのですが、知名度は残念ながらベル氏には及ばないようです。
1-2 なぜ「@」がメールアドレスの区切りに選ばれた?
トムリンソン氏がEメールシステムを開発する時の課題の一つは「送信先の指定方法」でした。
異なるコンピュータ上のユーザーを区別するため、ユーザー名とコンピュータ名を組み合わせる必要がありました。つまり「ユーザー名 + コンピュータ名」の「+」の部分を何の記号にするか、ということです。
そこで、トムリンソン氏はキーボードを見渡して、名前の一部として使用される可能性が低く、混乱を招かず、視覚的に分かりやすい記号を探し、「@」(アットマーク)を使うことにしました。
この記号は当時、商業用途以外であまり使用されていなかったうえに、視覚的にも目立つ記号でした。さらに、その意味である「?で(at)」が「(ユーザーが)そのコンピュータを使用している」といった概念とも合っていたのです。
Forbes.comの「Legends」シリーズにおいて、トムリンソン氏の「I thought about other symbols, but @ didn't appear in any names, so it worked(他の記号についても考えましたが、@はどの名前でも使われていなかったので、上手くいった)」という発言が引用されています。
今では「@」は、インターネット時代の象徴いえる記号で、様々な用途で使用されています。特にSNSのユーザー名として使用されるようになり、デジタルアイデンティティを示す記号として定着したといえます。
1-3 最初のEメールの内容は?
世界初のEメールの内容については、諸説ありますが、「QWERTYUIOP」という文字列だったといわれています。実は、文献によっては、トムリンソン氏はよく覚えていないといった旨を語ったとされています。
ちなみに、前述のグラハム・ベル氏が初めて電話のテストをした時は「Mr. Watson. Come here. I want to see you.」と発言しています。
日本でテレビ放映がテストされた時、初めてブラウン管に映し出されたのはカタカナの「イ」の文字だったとされています。このように電話やテレビでは「初メッセージ」がはっきりしていても、Eメールではあやふやです。
「QWERTYUIOP」説には、技術的な利点があったという指摘があります。もし送信に失敗しても、元の文字列と受信した文字列を比較することで、どの部分でエラーが発生したのかを特定しやすいといえるのです。
しかし、真偽は定かではないようです。いずれにせよ、意味のない文字列が送信された可能性は高いと考えられています。
2. Eメールの進化と一般化
2-1 初期のEメールシステムの限界とは
初期のEメールシステムには様々な制約がありました。メッセージは英語(ASCII文字)のみで、現在のように画像やファイルの添付はできませんでした。もちろん、日本語をはじめとする各国の言語を使用することもできませんでした。
さらに、受信者は同じネットワーク(ARPANET)に接続されているユーザーに限定されており、メールボックスの容量も小さいものでした。
これらの制限により、初期のEメールは主に研究機関や軍事機関内での簡素なメッセージのやり取りにしか使われていませんでしたが、そこから、より使いやすく、より多機能なEメールシステムが開発されていくことになりました。
2-2 インターネットでEメールが一般化した
Eメールが転換期を迎えたのは、1980年代後半からです。「TCP/IP」プロトコルが標準化され、インターネットの商用利用が開始されると、Eメールは一般のユーザーでも利用できるようになっていきました。
特に重要とされるのは、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)が採用されたことです。これにより、異なるメールシステム間で相互運用が可能になったのです。そして、MIMEが規格化されることによって、添付ファイルや日本語などの多言語対応も実現し、Eメールが普及し始めます。
1980年代から普及していた「パソコン通信」のサービスの一つだった「メール」も、インターネットの普及とともに、より使いやすく、パソコン通信ネット外ともやり取りができるようになっていきました。
そして、1995年にWindows 95が発売され、インターネットプロバイダーも増加したことで、Eメールは一気に一般化への道を進み始めることになります。
2-3 Eメールクライアントの変遷
Eメールクライアントの歴史は、技術の進化とユーザーニーズの変化を如実に反映しています。
初期の1970年代から1980年代は、「Pine」や「Elm」といったテキストベースのクライアントが主流でした。これらは一般ユーザーには扱いづらいものとされています。
1980年代後半から2000年代前半にかけては、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を採用した電子メールソフトが全盛期を迎えます。
「Outlook Express」「Netscape Messenger」「Eudora」、そして日本では「Becky!」などが人気を集めました。これらのソフトウェアは、Eメールの送受信だけでなく、整理や検索、アドレス帳の管理など、多彩な機能を提供しており、便利に使うことができました。この時代に現在の電子メールソフトの雛形が形成されたといってよいと思います。
そして、2000年代中期に大きな転換点が訪れます。2004年4月1日に「Gmail」が登場したのです。
「Gmail」は、それまでのメールクライアントの概念を根本から覆しました。ブラウザさえあれば、どの端末からでもアクセス可能で、大容量の保存領域を提供し、強力な検索機能を備えていた画期的なものでした。ここから、「Yahoo!メール」や他のサービスなども含めたWebメールの時代が本格的に幕を開けました。
さらに、スマートフォンが普及し始めた2007年ごろから、Webメールの「どの端末からでもアクセスできる」というメリットが重視されるようになり、現在に至っています。
3. Eメールにまつわる「豆知識」
3-1 「スパムメール」の起源
最近では、迷惑メールや出所不明の宣伝メールなど、受信者の意向を無視して送られてくるメールをまとめて「スパム(spam)」と呼ぶようになっています。
歴史上初めてのスパムメールは1978年5月、DEC(Digital Equipment Corporation)のマーケティング担当者が、約400人に対して自社の新製品の宣伝メールを送信したこととされています。
「スパム」という名称自体は、イギリスのコメディグループ「モンティ・パイソン」の人気コント「Spam」にちなんでいます(レストランのウェイトレスがスパムを連呼します)。ここから、執拗に繰り返される迷惑な行為を「スパム」と呼ぶようになり、それが望まれないEメールの代名詞として定着しました。
3-2 国ごとに「@」の呼び方が違う
「@」の読み方は、各国の文化や感覚、想像力が反映されて、多様です。日本での呼び方「アットマーク」「アット」は、シンプルで直接的です。日本では「@」を純粋に機能的な記号として捉えているからと思いますが、和製英語です。
英語圏では、「at sign」や「at symbol」と読みますが、@の形から、「snail(かたつむり)」とすることもあるそうです。イタリアでは「chiocciola(キオッチョラ)」と読まれ、これもかたつむり。ウクライナ語や韓国語もかたつむりのようです。たしかに「@」は渦巻き模様に見えます。
ロシアでは「собака(サバーカ)」で、「子犬」。デンマークでは「snabel-a(スヌアベル)」で、その形から「象の鼻のa」ということのようです。各国いろいろな読み方、呼び方をしています。
3-3 Eメールアドレスの最大文字数は254文字
Eメールアドレスの最大文字数については、インターネット技術の仕様を記した「RFC」では、「@」の左側右側を合わせて最大254文字(RFC5321)と定められています。
例えばGmailの場合、ユーザー名(@gmail.comの前の部分)は6文字以上30文字以下となっています。これは、ユーザビリティとシステムの効率性を考慮したためと考えられます。NTTドコモやau、ソフトバンクなど携帯電話会社のメールも30文字までとなっています。
4. Eメールの役割と課題
4-1 ビジネスコミュニケーションの要
Eメールは、現代のビジネスコミュニケーションにおいて、今なお中心的な存在といってよいでしょう。
Eメールがビジネスで使われるのは記録として残せることが挙げられます。また、添付ファイルの送受信が容易であること、時間や場所を選ばないコミュニケーションが可能であること、そして複数の関係者に同時に情報共有できることなどもメリットです。
しかし近年では、「Slack」や「Microsoft Teams」、日本では「Chatwork」などといったビジネスチャットツールの台頭により、社内コミュニケーションにおけるEメールの役割は変化しつつあるといわれています。即時性や気軽さを重視する用途では、これらのビジネスチャットツールが選択されるケースが増えています。
とはいえ、社外とのやり取りや正式な文書のやり取りでは、今しばらく、Eメールが重要な役割を果たしていくことでしょう。
4-2 セキュリティリスクとその対策
Eメールは現代のサイバー犯罪者たちにとって、最も効果的な攻撃の入り口として悪用されています。そのセキュリティ上の問題は多岐にわたり、特に通信経路の脆弱性、なりすまし、フィッシング攻撃、ビジネスメール詐欺(BEC)などが深刻な問題となっています。
標準的なSMTPは暗号化されていないため、中間者攻撃や「Eメール盗聴」のリスクがあります。さらに送信元の詐称も容易です。
フィッシングメールや標的型攻撃メールは実在の企業や組織になりすまし、個人情報や認証情報を詐取する手口として悪用されています。特に、AIを活用した精巧なメール作成技術が進化し、見分けがさらに困難になっています。
これらの問題に対して、様々な対策が講じられています。
S/MIMEやPGPによる暗号化、SPF、DKIM、DMARCによる送信元認証、AIを活用したスパム・フィッシング対策、多要素認証の導入などが実施されています。特に近年は、AIによる不正検知の精度が向上しており、セキュリティ対策の新たな可能性が開かれつつあります。
加えて、セキュリティ面では、ブロックチェーン技術の活用や生体認証との連携、エンドツーエンド暗号化の標準化なども進むと考えられます。これにより、なりすましやデータの改ざんを防ぎつつ、より安全で信頼性の高いコミュニケーションが可能になるでしょう。
また、企業や個人レベルでも、迷惑メールフィルタの活用や不審なメールを開かない意識づけも重要です。今後、Eメールが発展していくには、まず、セキュリティ対策が進み、より安全でスピーディに使用できるようになることが求められているといえるでしょう。
4-3 SNSやAIとの共存 - Eメールの未来
Eメールは、これからどのように進化していくのでしょうか。
一つの大きな方向性として、AIとの統合が挙げられます。既にGmailでは、AIを活用した返信の自動提案機能が実装されていますが、今後はさらに高度な機能が実現されると予想されます。
例えば、メールの内容を解析し、優先度を自動判定したり、スケジュール調整を自動化したりする機能が一般化するでしょう。
まとめ
1971年、レイ・トムリンソンによって「@」とともに誕生したEメールは、半世紀以上の時を経て、現代社会に不可欠なコミュニケーションツールへと進化しました。
テキストのみだった初期のシステムから、現在では多彩な機能を備え、ビジネスから個人利用まで幅広く活用されています。
セキュリティの課題は依然として存在しますが、AIとの統合やSNSとの連携により、Eメールはさらなる進化を遂げようとしています。Eメールはこれからも時代とともに形を変えながら、重要なコミュニケーション手段であり続けることでしょう。