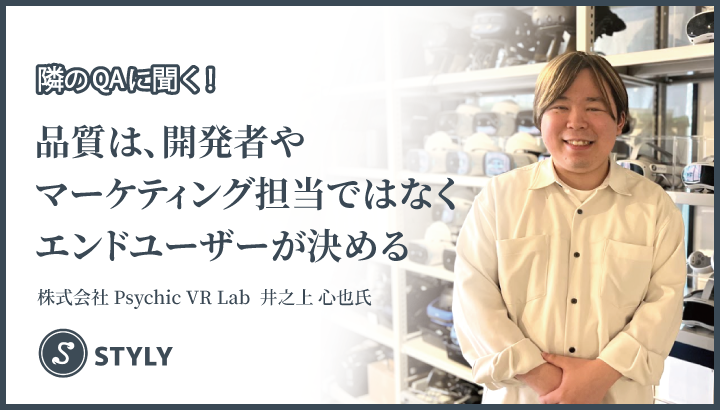様々な現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。スマートフォン用ARゲームアプリのヒットなどがきっかけで話題となったXR(VR/AR/MR)領域。今後、一気に広まる可能性が高いと目されています。
その流れで今、熱い注目を集めているのが、株式会社 Psychic VR Labが開発する、誰でも簡単にARやVRの作品を制作できるXRプラットフォーム「STYLY」です。
そんな最先端のプラットフォームを開発するチームでは、どのようにQA業務が実施されているか、気になるエンジニアの方も多いのではないでしょうか?
本記事では、同社の井之上 心也さんに同社のQA活動やQAに取り組む上でのポイントなどについてお話いただきました。
今回インタビューを受けてくださった方

- 井之上 心也 氏
株式会社 Psychic VR Lab
情報系の学科で学んだ後、大手精密機器メーカーに入社しソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタート。オフィス用複合機のQA部門に配属後、QA技術に触れて感銘を受け、ソフトウェアテストやQAについて理解と学びを深めた。その後、新しい世界に触れたいとの思いからXRの世界に興味を持ち、XR領域でQAリーダーを目指すようになり、株式会社 Psychic VR Labに参画する。現在はチームリーダーとしてXR領域でのQA活動を推進している。
- もくじ
1.世界をリードするXRプラットフォーム「STYLY」を開発する先端企業

――株式会社 Psychic VR Labはどのようなサービスを展開していらっしゃいますか?
当社は、都市空間と連動したXRコンテンツを制作・配信できるリアルメタバースプラットフォーム「STYLY(スタイリー)」をメインで開発しています。STYLYにはあらゆる都市の3Dデータが実装されていて、実空間と連動したXR(VR/AR/ MR)コンテンツを誰でも制作・配信することができます。

当社のバリューは『「空間を身にまとう時代」をつくる。』です。ウォークマンやiPodが登場して、人々が音楽を聴きながら移動できるようになり、音楽を身にまとうことができるようになりました。
同様に、空間そのものを身にまとい、これまでテキストや動画を送受信してきたのと同じように、空間そのものを送受信できるようになる時代がくると考えています。その実現に向けて、私たちは「リアルメタバース」を提唱しています。
今後も、世界中のクリエイターや各都市と連携し合いながら、現実世界をテクノロジーで拡張させる「リアルメタバース」を推進していき、ライフスタイルの中でXR/リアルメタバースを利用する「空間を身にまとう時代」の創造を目指していきます。
――これから、ARやVRのコンテンツやサービスが増えると思いますが、その流れにあって、御社の強みは何でしょうか?
ARやVRといったそれぞれの区切りで見ると同じような取り組みをしている会社は多いと思います。しかし、ARとVRを自由に操り、作品を作ることができるプラットフォームは我々が調べている限り「STYLY」だけだと思います。ARとVRを両立する技術を持っているのが当社の強みです。
2.「プロダクトの成長を妨げるものをなくす」のがQAのミッション

――御社のQA業務の位置づけや、今、目指していることを教えてください。
QAチームとしては、「プロダクトの成長を妨げるものをなくす」活動をしています。例えば、車が走る先に岩があったり、倒木があったりしたら進むことができません。「to B」「to B to C」を意識して、プロダクトが成長する上での心配事をなくすのが目標です。
――QA業務を進める上で、自動化などの技術は取り入れていますか?
AR、VRを作るサービス「STYLY Studio」では、ユーザーが作品を作って再生して見るまでの流れを一貫して全て自動テストで回し、画像処理を使って正解の判定をしています。この自動テストには「SikuliX(シクリックス)」を使っています。これを毎日やることで、リグレッションテストではありませんが、日々、重要な部分が壊れていないか確認しています。
現在は「STYLY」のモバイルアプリを自動でリグレッションテストできるようにする計画があり、この仕組み作りに着手しています。
この部分はフルスクラッチの「Unity」で書かれているので、NetEase Gamesの「Airtest」や「Poco」といったフレームワークを使い、外側からテストできる体制を作っています。あまり、従来のQAでは使われていない方法かもしれません。
――他の事例があまりないので、ご自身で新しいツールや方法を用意して、最適な組み合わせを考え、トライアンドエラーをしているのでしょうか?
そうですね。例えば、AI自動化テストツール「Magic Pod」のようなテストを自動化するソリューションは数多くあると思います。ただ、「Unity」で作られたアプリは自動操作することができないことが多いので、他のツールを半年近く試して捜索したという感じです。
AR/VRでは、一般的なQAやテストとはテスト観点が違っていたりするため、調べても事例が全く出てこないことが多いです。その意味で、特有の難しさがあると思っています。
――まさに今、AR/VR業界のQA分野を開拓しているところなのですね。
もしかしたら、まだ表に出てきていないだけなのかもしれませんが、正解がないといいますか、調べても出てこないのは確かなので、開拓をしている感覚はありますね。