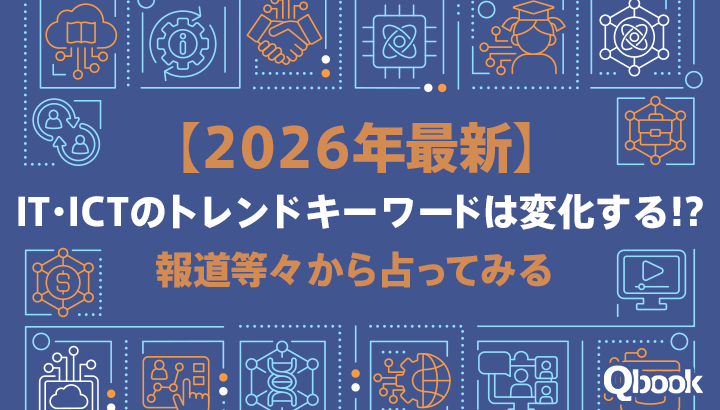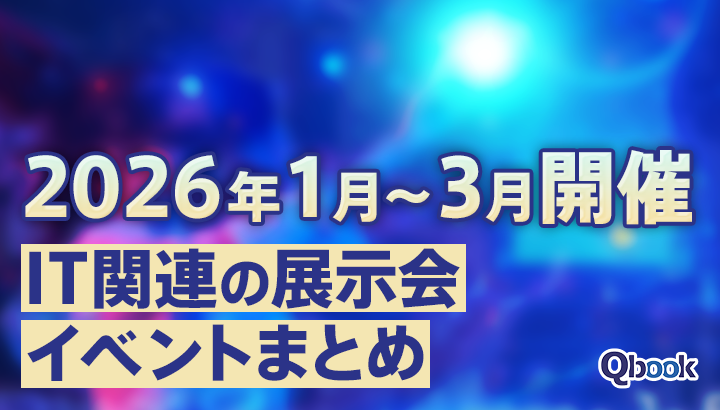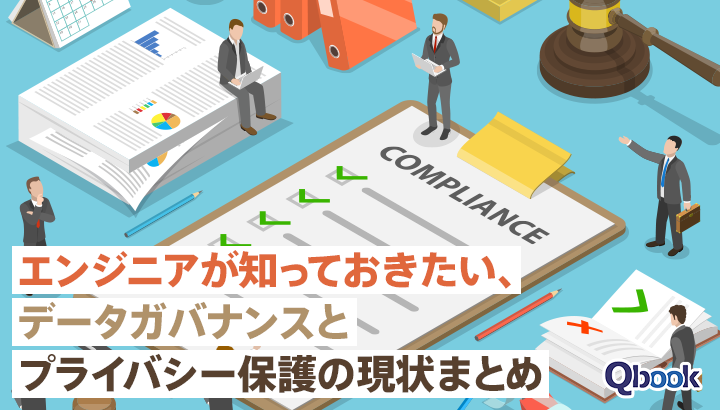「2050年の未来」と聞いて、あなたはどんな世界を思い浮かべますか?
実は今、「2050年までに、人が身体、脳、空間の制約から解放された社会を実現する」――こんなSF映画のような大胆な目標をを内閣府が掲げていることはご存知でしたか?
政府は、空飛ぶ車、ロボットとの共存、病気のない社会といった未来を本気で目指す国家プロジェクト「ムーンショット型研究開発制度」を進めています。
今回は、その目的となる「ムーンショット目標」についてまとめました。
- もくじ
1. 「ムーンショット型研究開発制度」とは何か?
1-1. 「ムーンショット」の由来と意味
「ムーンショット(Moonshot)」とは、もともとアメリカのアポロ計画で「月に人類を送り込む」という、当時は夢物語だった目標に由来します。
1960年代、ケネディ大統領が掲げたこの壮大な目標は、まさに「月へロケットを飛ばす」といった、これまでの延長線上にはない非常に困難で革新的な挑戦でした。2016年には、元Apple ComputerのCEO、ジョン・スカリー氏が著書『Moonshot!』(2016)のタイトルで使い、この概念を広めました。
そんな「大胆で革新的な挑戦」や「常識の枠を超えた目標」を意味する、日本政府の「ムーンショット目標」も、現状の延長線上にはない、大きなジャンプを目指す挑戦です。そのため、多少の失敗を許容しつつ、社会を根本から変えるような飛躍的なイノベーションを推進しよう――というのが「ムーンショット型研究開発制度」なのです。
政府が真面目に取り組む「SFプロトタイピング」の事例といってもよいかもしれません。
1-2. 日本政府が「ムーンショット目標」を掲げた背景
日本は今、少子高齢化や労働人口の減少、地球環境問題など、従来のやり方だけでは解決できない困難な課題に直面しています。これらの課題は、地球規模での社会課題でもあり、従来の技術開発や政策だけでは根本的な解決が難しいと認識されています。
こうした課題を突破するには、これまでの常識や前例にとらわれない「大胆な目標」と「長期的な視点」が必要です。そこで政府は、2050年をゴールに、社会や産業のあり方を根本から変える「ムーンショット目標」を掲げたのです。このプロジェクトは2019年に正式に動き出し、内閣府が中心となって推進されています。
また、急速に進むグローバル化やテクノロジーの進化のなかで、日本が国際競争力を維持し、持続可能な社会を築いていくためには、これまでにない発想と大胆な挑戦が必要不可欠であるという認識もあります。このプロジェクトは、たんなる技術開発だけでなく、社会全体の仕組みや価値観にも大きな変革をもたらすことを狙っています。
1-3. 10の「ムーンショット目標」とは?
「ムーンショット目標」は、現在で合計10目標が設定されています。それぞれが医療・健康、環境、食料、量子コンピュータ、AI、ロボティクスなど、幅広い分野で未来社会を描いています。

「ムーンショット型研究開発制度」より引用
「もし実現したら、世界が大きく変わる」内容ばかりです。これら10の目標は、それぞれが独立しているだけでなく、相互に関連し合いながら、より良い未来社会の実現を目指しています。それぞれ、次のような目標が掲げられています。
- 目標1. 人が身体、脳、空間、時間の制約から解放される社会を実現
- 目標2. 超早期に疾患予測・予防が可能な社会を実現
- 目標3. 自ら学習・行動するAIロボットと人が共生する社会を実現
- 目標4. 地球環境再生に向けた持続可能な資源循環社会を実現
- 目標5. 食糧供給と地球環境の両立を実現
- 目標6. 経済・産業・安全保障を発展させる汎用量子コンピュータを実現
- 目標7. 2040年までに主要な疾病を予防・克服し100歳まで生きられる医療を実現
- 目標8. 激甚化しつつある台風や豪雨を制御
- 目標9. 精神的に豊かで躍動的な社会を実現
- 目標10. フュージョンエネルギーの活用で資源制約から解き放たれた社会を実現
2. インパクトが大きい「ムーンショット目標1」
2-1. 目標1「身体、脳、空間、時間の制約からの解放」とは
「ムーンショット目標1」は、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現する」というものです。これは、テクノロジーの力で「できない」「行けない」「伝わらない」といった物理的・精神的な壁をなくし、誰もが自由に社会参加できる未来を目指すもので、「もしかして、不老不死の実現......?」とも思えてしまうような大きな目標になっています。
実際には、「身体的な制約からの解放」は、病気や高齢化によって身体が不自由になったとしても、テクノロジーの力で活動範囲を広げたり、まるで健康な身体のように自由に動けたりするようになることを指しています。
「脳の制約からの解放」は、記憶力や計算能力といった人間の脳の能力を拡張したり、遠隔地にいる人と脳波を通じてコミュニケーションを取ったりする可能性を示唆するもののようです。
「空間の制約からの解放」は、遠く離れた場所にいる人とあたかも同じ空間にいるかのように交流したり、危険な場所での作業を遠隔で行ったりすることを可能にします。
そして、「時間の制約からの解放」は、たとえば遠い過去の出来事を仮想的に体験したり、未来の情報を予測したりといった、これまで想像もできなかったような可能性を秘めています。
たとえば、外出が難しい人も、アバターやロボットを使って仕事や趣味を楽しめる、距離や時間にとらわれず、どこからでも学び、働き、交流できる、脳とコンピュータをつなぎ、意思や感覚をより自由に伝えられる未来が想定されています。
こうした「制約からの解放」は、単なる便利さを超え、社会のあり方そのものを変える可能性を秘めています。
2-2. 「サイバネティック・アバター」とは何か?その役割と可能性
「ムーンショット目標1」をクリアするために考えられているのが、「サイバネティック・アバター」基盤です。
「サイバネティック・アバター」とは、簡単にいえば「自分の分身」となるロボットや仮想キャラクターのことです。人間の身体能力、認知能力、知覚能力を拡張したり、代替したりする分身ロボットやVR(仮想現実)、AR(拡張現実)技術のことを指します。
たとえば、家にいながら遠くの職場やイベント会場でアバターを操作し、現地の人と会話したり作業したりできる――そんな未来が描かれています。手元の操作や身体の動きを感知して、離れた場所にあるロボットが同じように動くといった仕組みが想定されています。
この技術が進化すれば、介護や医療、教育、災害現場など、さまざまな分野で「人の代わり」として活躍することができます。高齢者や障害者、子育て中の人も、社会参加の幅が大きく広がります。また、危険な現場や人が行けない場所での活動も可能になります。
単なる「ロボットの遠隔操作」ではなく、脳波や視線、筋電といった人間の神経活動に近い信号を読み取り、それを使って自在に操作できるようにすることが目標とされています。
これにより、障害がある人や高齢者でも、身体的な制約なく社会に参加できるようになるのです。
「サイバネティック・アバター」は「制約からの解放」を象徴する存在といってよいでしょう。
2-3. 実現に向けた技術開発とマイルストーン
壮大な「ムーンショット目標1」を実現するため、政府は段階的な技術開発のマイルストーンを設定しています。
まず2030年までに、サイバネティック・アバターによって、遠隔地から複数人が協働できる環境を整備することが目指されています。
具体的には、1人で10体以上のアバターを同時に操作できる技術の開発や、身体的ハンディを持つ人でもアバターを使って職場や学校に「通える」ようにすることが含まれています。
さらに2040年までには、脳とアバターのインターフェースを高度化し、思考によるアバターの操作を可能にすることが計画されています。たとえば、手を動かさずとも、頭で考えるだけでアバターを動かせるようになることが想定されています。
そして2050年までには、複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせ、大規模で複雑な作業を実現し、望む人は誰でも、身体的・認知的・知覚的な能力を最大限まで拡張できる技術の普及が目標とされています。
現在、多くの研究機関や企業が協力し、脳科学、ロボット工学、AI(人工知能)、VR/AR技術、通信技術など、多岐にわたる最先端技術が融合することで、これらの革新的なシステムが生まれると期待されています。これらの技術が社会に根付けば、「どこでも、誰でも、何でもできる」時代がやってきます。
3. 「ムーンショット型研究開発制度」と未来社会
3-1. 医療、量子コンピュータなどあらゆる分野で目標設定
ムーンショット目標は、目標1だけではありません。1-3で示したように、他の目標も私たちの生活に深く関わる重要な分野に焦点が当てられています。よく見ると、それぞれが深い関わりがあるようです。
医療・健康分野では、病気になる前にその兆候を捉えて、早期に治療することで、多くの人が健康な状態で長生きできる社会を目指すことが読み取れます。
環境分野では、地球環境の再生や台風や豪雨を制御など、災害の脅威からの解放や資源の枯渇といった地球規模の課題に対して、再生可能エネルギーの導入や資源の効率的な利用で、持続可能な地球環境を実現することを目指していることがわかります。
食料分野では、持続的な食糧供給産業の創出を目指しています。実現すれば、世界的な人口増加や気候変動による食料不足の問題を解決できる革命的な出来事となるでしょう。
そして、エンジニアが注目する情報技術分野では、汎用量子コンピュータの実現が掲げられています。実際のところ、他の分野の目標もパワフルなコンピュータの活用なくしては解決できないのは今日の目から見ても明らかです。コンピュータの力は、社会問題の解決にはなくてはならないものとなっています。
なかでも、複雑な問題を高速で処理できると期待されている量子コンピュータなど、次世代コンピュータの今後には注目したいところです。新薬の開発や新素材の発見、気象予測の精度向上など、さまざまな分野で飛躍的な進歩がみられることでしょう。
これらの目標が実現すれば、人類共通の課題も、今とはまったく違うアプローチで解決できる可能性が高まります。
3-2. 少子高齢化や労働人口減少への対応
日本が直面する「少子高齢化」「労働人口の減少」は、社会の大きな課題です。総務省の統計によれば、2023年時点で日本の総人口に占める65歳以上の割合は約30%で、2050年には労働人口が現在の約7割にまで減少するとも試算されています。
ムーンショット目標では、アバターやAI、ロボット技術の活用によって、高齢者や障害者も含めた多様な人材が社会で活躍できる仕組みを目指しています。さらに、医療・健康分野の目標によって、人々の健康寿命が延伸されれば、より長く社会で活躍できる期間が増えるため、労働人口の質的な向上にもつながります。
こうした技術の進化は、誰もが活躍できる社会への大きな一歩となります。ムーンショット目標は、個別の課題解決だけでなく、日本の社会構造そのものに変革をもたらし、少子高齢化や労働人口減少といった大きな課題に対し、解決策を提示しようとするものです。
3-3. ムーンショット目標がもたらす社会変革と課題
ムーンショット目標が実現すれば、私たちの暮らしは劇的に変わります。達成は2040年~2050年が目標とされています。もしかしたら、SF映画で見た光景を現実に目のあたりにできるかもしれないのです。
サイバネティック・アバターや自立して行動するAIロボットというのは、「アイアンマン」や「ドラえもん」の世界観です。場所や時間に縛られない働き方や学び方、病気や障害にとらわれない社会参加、環境負荷の少ない持続可能な生活――そんな未来を体験したいものです。
ムーンショット目標の実現に向けた研究開発は、仮に達成できなかったとしても、新たな技術やサービスを創出して、未だ見ぬ産業を作り出す可能性は高いでしょう。
ムーンショット目標の達成にあたっては「プライバシーや倫理の問題」「格差の拡大」「技術への依存」「セキュリティ」といった新たな課題を生むことがあるという指摘もあります。これらの課題を乗り越えるのは決して容易ではありませんが、ムーンショット目標が達成されて、より豊かな社会が実現することを望みたいですね。
まとめ
日本政府が掲げる「ムーンショット型研究開発制度」は、2050年をゴールに、身体・脳・空間・時間など、これまで人類を縛ってきた根本的な制約を超える社会の実現を目指す国家プロジェクトです。
特に「目標1」は、人間の能力をテクノロジーで拡張し、多様な社会参加を可能にするテクノロジーの発展を構想しています。
その核となる「サイバネティック・アバター」技術をはじめ、医療、環境、量子コンピュータといった多岐にわたる分野で10の目標掲げられ、少子高齢化や環境問題といった社会課題への新たなアプローチを示しています。一方で、倫理的な問題や格差拡大など新たな課題にも向き合う必要があります。
技術革新と社会課題の解決が両立する未来が実現すれば、SFの世界が現実となる日も遠くはないかもしれません。