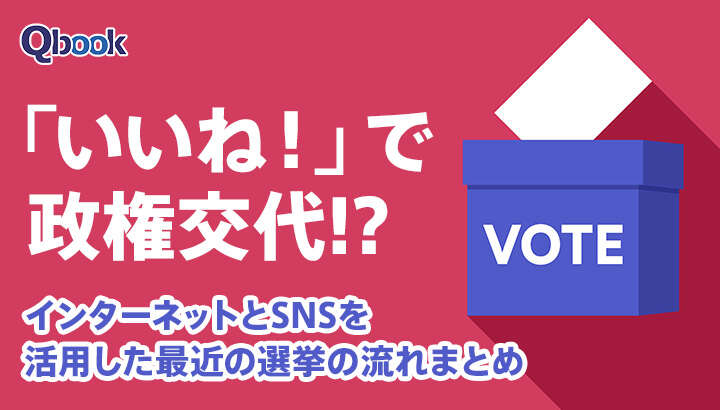ソーシャルメディアの急速な普及によって、国政、地方自治を問わず選挙戦略が大きな転換期を迎えているといわれています。
そこで今回はインターネットと選挙の関係する歴史を振り返り、ネットとSNSを活用した選挙戦術の事例や効果、そしてビジネスへの応用可能性をまとめてみました。
- もくじ
1.ネットとSNSが変えた選挙の風景
1-1 2013年、日本のネット選挙が解禁される
2013年、日本の選挙活動に大きな変革が訪れました。公職選挙法の改正によって、夏の参議院議員選挙からインターネットを利用した選挙運動が解禁されたのです。
公職選挙法の改正は4月26日に公布され、5月26日に施行されました。これにより、候補者や政党は、WEBサイトやSNSを通じて有権者に直接メッセージを発信することが可能になりました。
この改正以前は選挙期間中のインターネットを使った選挙運動は制限されていました。候補者のWEBサイトの更新は許されず、SNSでの投稿も控えられていたのです。しかし、公職選挙法の改正で、WEBサイトやブログでの選挙運動、SNSを利用した情報発信、一定の制限はありますが電子メールによる選挙運動や動画サイトを利用した選挙運動が可能になりました。
この改正は、とくに若年層の有権者へアプローチしやすくなり、政治参加の新たな可能性を開いたと評価されています。候補者たちは自身の政策や主張をより直接的に、そして迅速に有権者に伝えられるようになりました。
2013年の公職選挙法改正によるネット選挙解禁は、その後の日本の政治文化に大きな影響を与え、選挙戦略の多様化をもたらしたことは間違いないと思います。
1-2 日本におけるSNS選挙
ネット選挙解禁から10年以上が経過し、日本の政治におけるSNSの影響力は着実に増大しています。とくに注目を集めたのが、2024年夏の「石丸現象」と呼ばれる出来事でした。
石丸伸二氏は広島県安芸高田市長を務められていましたが、2024年の東京都知事選挙に出馬。SNSを巧みに活用した選挙戦略で大きな話題となりました。
石丸氏のYouTubeチャンネルやX(旧Twitter)アカウントは多くのフォロワーを獲得することに成功し、従来の政治家像を覆すような新鮮なイメージを作り上げました。
石丸氏は動画コンテンツの活用やSNSでの双方向コミュニケーション、若者文化を積極的に取り入れた投稿で話題性を創出しました。結果として、現職の小池百合子氏に次ぐ2位という強烈な印象を残しました。この「石丸現象」は、SNSが選挙結果に大きな影響を与え得ることを示した現象のひとつでした。
しかし、偽情報(フェイクニュース)の拡散や、SNSの特性を利用した誹謗中傷の増加といった課題も同時に浮き彫りになっています。日本においてSNSが選挙に与える影響の大きさと同時に危険性も明示したといってよいと思います。
1-3 アメリカ大統領選挙とSNS
アメリカの政治においても、SNSは選挙戦略の中心的な役割を担っています。2008年の大統領選挙では、バラク・オバマ氏がFacebookを効果的に活用し、若年層の支持を獲得しています。
これは「オバマ旋風(the Obama Phenomenon)」と呼ばれ、SNSの政治的影響力を世界に知らしめる契機のひとつとなりました。オバマ陣営は草の根運動のデジタル化、個人化されたメッセージング、選挙資金調達の効率化などを実現していたと報じられています。
アメリカでは、その後の選挙でもSNSは重要な役割を果たし続けています。とくに、ドナルド・トランプ大統領はTwitter(前回就任時)を活用。現在もトランプ氏はSNSを重視し続けており、イーロン・マスク氏が所有するXと提携するなど、新たな展開を見せています。
トランプ氏はリアルタイムでの発言で常にメディアの注目を集め、挑発的な発言で議論を喚起し、メディアを介さずに有権者に直接メッセージを届ける直接的なコミュニケーションスタイルで注目を集めています。この戦略にSNSがハマるということだと思います。
このようなアメリカの事例は、SNSが政治や選挙戦略において極めて重要な要素のひとつになっていることを示しています。その一方で、SNSの利用が場合によっては政治的分断や偽情報の拡散といった問題を引き起こす可能性が明らかになったとの指摘が多くなされているのも一つの現実です。
2.SNSと選挙の関係性
2-1 SNS以前の選挙戦略
ネットやSNSが普及する以前の選挙戦略は、街頭演説、選挙ポスター、選挙カー、戸別訪問、マスメディア広告、後援会組織などが中心でした。
ときには「ドブ板選挙」といわれる有権者に個別にアプローチする選挙戦略も取られました。
これらの手法は現在でも選挙戦術の主流として使用されています。SNSはこれらの既存の戦略に追加するか、新たな選択肢として活用されています。
ネットやSNS以前の選挙戦略の特徴は、「物理的な接触」と「一方向的なコミュニケーション」にありました。候補者から有権者へ一方的に情報が流れる活動が主で、有権者から即時のフィードバックを得ることは難しいとされていました。
しかし、ネットやSNSの登場によって双方向のコミュニケーションが可能になり、有権者の反応をリアルタイムで把握できるようになったのです。これは大きな変化といえます。また、地理的・時間的制約を超えた情報発信が可能になったことで、より効率的かつ広範囲な選挙活動が可能になりました。
しかし、SNSだけでは全ての有権者にリーチすることは難しいでしょう。デジタルデバイスに慣れていない層、SNSを利用しない層には文字通り「届かない」からです。従来の手法が依然として重要な役割を果たしているのはこのような背景があります。
今後は、従来の選挙戦略とインターネットやSNSを活用した手法を組み合わせた「ハイブリッド戦略」が主流になっていくでしょう。
2-2 SNSが「政治」を変えた瞬間
SNSが政治に大きな影響を与えると人々が感じた象徴的な出来事は、2010年から2012年にかけて中東・北アフリカ地域で起こった「アラブの春」です。この一連の民主化運動において、FacebookやTwitterなどのSNSが重要な役割を果たし、世界中の人々がSNSの政治的影響力を認識する契機となりました。
アラブの春ではSNSが情報共有のプラットフォーム、組織化のツール、国際的な注目の喚起、匿名性の確保といった役割を担いました。この出来事以降、SNSは政治的な変革を促す強力なツールとして認識されるようになったといってよいと思います。
その後も、2016年のイギリスEU離脱(Brexit=BritainイギリスとExit離脱の造語)を問う国民投票や、前述したアメリカ大統領選挙などで、SNSが政治や選挙結果に大きな影響を及ぼしたと考えられる事例が続きました。
SNSが情報の流れを一方向から双方向へと変化させ、市民の政治参加の形も変わり、政治の在り方にも影響を及ぼすことが示されたことになります。
これらの動きから、SNSの政治的影響力が増大したことに警鐘を鳴らす人も少なくありません。前述したようなフェイクニュースの拡散や、同じ意見を持つ人々だけで情報を共有し、偏った見方が強化されるエコーチェンバー現象などが問題とされており、過激な動きにどう対処すべきか、今も議論が交わされています。
2-3 政治的なコミュニケーションの変化
ここまで見てきたようにSNSの普及により、政治家と有権者のコミュニケーションの在り方は大きく変化しました。従来のメディア戦略とは異なる、新たなアプローチが求められるようになったのです。
SNSを通じて政治家は有権者に直接メッセージを発信できるようになり、従来のメディアを介さない親密なコミュニケーションが可能になりました。また、SNSの即時性により、政治家は世論の動向にすぐに反応することができるようになりました。
政治家と有権者の距離感が縮まり、透明性が高い、より開かれた政治が行われる可能性も高まったのはポジティブな変化と考えられます。
そして、YouTube、Instagram、TikTokなどの視覚的要素が強いSNSが広まることで、政治コミュニケーションにおける画像や動画の重要性も増しています。政治家には従来とは異なるコミュニケーションスキルが求められる時代になっているといってよいでしょう。
3.政治と選挙から学ぶビジネス戦略
3-1 なぜSNSは政治と選挙に影響を与えるのか?
SNSが政治と選挙に大きな影響を与える理由として以下のような点が考えられます。
- 広範囲への即時的な情報拡散力がある
- ターゲティング精度が高い
- コスト効率がよい
- 双方向コミュニケーションを実現している
SNSは瞬時に大量の情報を広範囲に拡散することができるため、政治家や政党は、自身の主張や政策を迅速かつ効率的に有権者に届けることができるのが大きなメリットになっています。
従来のマスメディア広告と比較すると、SNSを活用した情報発信は低コストで実施できるため、資金力が乏しい新人候補者や小規模政党でも効果的な選挙運動をすることができます。
ここまであげてきた要因が相互に作用することで、SNSは政治と選挙に大きな影響を与えることが可能になっています。こういったSNS活用のメリットは政治とビジネスで共通といってよいと思います。
ビジネスではコスト面などからデジタルマーケティングを主軸に置くケースも増えていますが、選挙戦の場合、ここまで見てきたように、ほぼ確実に従来のアナログ戦略を併用しています。この「ハイブリッド戦略」はビジネスの場面でもさらに活用されていくのではないでしょうか。
3-2 インフルエンサーマーケティングの応用
政治の世界でも、ビジネスのマーケティング手法であるインフルエンサーマーケティングが応用されています。これは、SNSで影響力を持つインフルエンサーを通じて、政治的メッセージを拡散する戦略です。
インフルエンサーは既に特定のフォロワー層からの信頼を得ているため、政治家がインフルエンサーと協力することで、その信頼性を借りて自身の政策や主張を訴えかけることができるのです。また、特定の分野や興味関心に特化したインフルエンサーと協力することで、従来のマスメディアでは届きにくかった層にピンポイントでアプローチし、政策を主張することも可能です。
具体的な応用例としては、環境政策を訴える政治家が環境活動家のインフルエンサーと協力するケースや、地方創生を掲げる候補者が地域の魅力を発信する地元インフルエンサーと連携するケースなどがあげられます。
インフルエンサーマーケティングを政治で利用すると透明性の問題や信頼性の低下リスクが存在するという指摘がありますが、政治と選挙の動きからいわば"逆輸入"するような形で、今後、ビジネスでも活用されていく可能性がありそうです。
3-3 ストーリーテリングの重要性
政治の世界でも、ビジネスマーケティングと同様にストーリーテリングが活用されています。SNSの普及により、政治家は単に政策を列挙するだけでなく、魅力的なストーリーを通じて有権者の共感を得ることができるようになりました。
ストーリーは人々の感情に訴えかけ、政治家と有権者の間に感情的なつながりを生み出します。また、ストーリーは複雑な政策や理念を分かりやすく伝える手段として効果的で、有権者は具体的なエピソードを通じて、政策の意義や影響を理解しやすくなります。
また、個人的な経験や背景を織り交ぜたストーリーは、政治家を他の候補者から差別化する強力なツールとなりえます。自身の経験や動機を共有することで、政治家は有権者との信頼関係を築くことができます。政治におけるストーリーテリングの例としては、バラク・オバマ元大統領の「Hope」キャンペーンなどがあります。
ストーリーテリングにより生まれた「つながり」が強固で差別化が可能なことが示されたことで、これをビジネスでも重要視する動きが加速するのではないかと思います。
3-4 データ分析とターゲティング広告は有効
政治の世界でも、ビジネスマーケティングと同様に、データ分析とターゲティング広告の活用が進みました。今ではSNSやデジタル広告プラットフォームの発達により、より精緻な有権者分析と個別化されたメッセージングが可能になっています。
年齢、性別、居住地域、職業、興味関心などの属性に基づいて有権者を細分化し、それぞれのグループに最適化されたメッセージを届けたり、オンライン上の行動履歴などに基づいて、特定の関心を持つ有権者にアプローチしたりすることで、特定の有権者にピンポイントでメッセージを伝えられるようになっています。これは政治・選挙でもビジネスでも変わりない状況です。
高度化したデータ分析とターゲティング広告は、キャンペーンの効率と効果を大幅に向上させる可能性を秘めています。しかし、その使用には個人データの収集と利用に関する倫理的問題などの懸念点も存在するため、その使用については最大限に注意していく必要があるでしょう。
4.ネット・SNSを活用した選挙のこれから
4-1 フェイクニュースと情報操作の危険性
ここまで述べてきたようにSNSの政治利用が拡大する中で、フェイクニュースと情報操作の危険性が深刻な問題として浮上しています。虚偽の情報が拡散されることで有権者の判断が歪められたり、偏向した情報や誤情報が政治的対立を深めたりする危険があるとの指摘もあります。
フェイクニュースの蔓延で、メディアや政治家、さらには民主主義プロセス全体への信頼が損なわれる可能性もあります。SNSの特性もありますが、フェイクニュースのほうが従来のメディアよりも速く、広範囲に拡散されることがあることも問題になっています。
これらの問題に対処するため、SNSプラットフォームや第三者機関によるファクトチェック機能の導入、メディアリテラシー教育の推進、SNS企業に対するフェイクニュース拡散防止や透明性向上を求める法規制の検討などが行われています。
しかし、表現の自由との兼ね合いや、誰が、何が「真実」であるかを判断するのかという問題や、ますます巧妙化するディープフェイクへの対応といった課題もあり、課題解決への見通しは不透明です。
これら山積みの問題に効果的に対処していくことが、デジタル時代の民主主義を健全に機能させる上で不可欠になっている状況だといってよいでしょう。
4-2 選挙におけるSNS利用の規制拡大の動き
SNSの政治利用が拡大する一方で、その影響力の大きさなどから、選挙におけるSNS利用を規制しようとする動きも見られます。現時点でも、各国で「行き過ぎ」を止めるため様々なアプローチが試みられています。EUではデジタルサービス法を制定し、オンラインプラットフォームの透明性と責任を強化している一方、アメリカでは表現の自由を重視する傾向が強く、規制には慎重な姿勢が見られます。
SNSの政治や選挙での利用規制は、デジタル時代の民主主義の在り方を問う上で重要な課題になっています。技術革新のメリットを活かしつつ、公正で健全な選挙プロセスを維持するバランスを取ることが今後、求められていくことになります。
まとめ
SNSの登場によって、選挙戦略や政治の在り方は大きく変化しました。
日本では2013年にネット選挙が解禁され、以降、SNSは候補者にとって欠かせないツールとなっています。
ネットやSNSは政治、選挙と、ますます密接な関係を築いていくでしょう。ルールの整備も進むと考えられるので、今後の動きに注目したいところです。