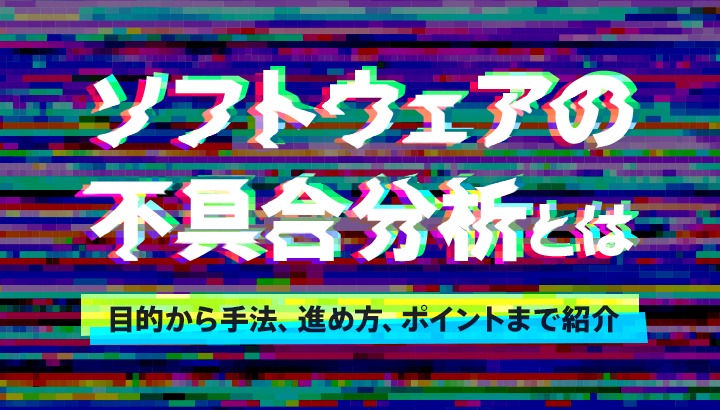「なぜなぜ分析」は、ビジネスの問題解決にあたって広く活用される手法です。この名前を聞いたことはあっても、「具体的な進め方が分からない」「実践しても上手くいかない」と悩む方も少なくないのではないでしょうか。
本稿では、ソフトウェア開発における具体例を交えながら、なぜなぜ分析について基本から解説します。なぜなぜ分析を成功させるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

- もくじ
1.なぜなぜ分析とは:トヨタ自動車が生み出した分析手法
なぜなぜ分析とは、トヨタ自動車が生み出した問題解決における分析手法です。発生した問題に対する原因を「なぜ?」と問い、その原因にさらに「なぜ?」と問います。このように「なぜ?」を何度も繰り返すことで、根本原因を究明することができます。
なぜなぜ分析は汎用性が高く、あらゆる業種・分野における問題解決や再発防止策の策定に役立ちます。元々はトヨタ自動車の生産プロセス改善に活用されていた手法ですが、昨今では幅広いビジネスシーンで広く取り入れられています。
2.なぜなぜ分析のやり方【具体例】
なぜなぜ分析を進める際の流れは、大まかに次の4ステップです。
- 問題を明確化する
- 問題に対する原因を分析する
- 原因に対する原因を繰り返し分析する
- 根本原因を特定し対策を講じる
ここでは、ソフトウェア開発の具体例を交えながら、なぜなぜ分析のやり方を紹介します。
ステップ1. 問題を明確化する
まずは、なぜなぜ分析の出発点となる問題を明確に定義します。問題が抽象的だと分析がうまく進まないため、具体的な問題をはっきりさせることが重要です。
たとえば、「社内システムのパフォーマンスが低下している問題」をなぜなぜ分析の出発点とする場合、次のような部分を明確化する必要があります。
- 何の指標(速度やデータ処理量など)におけるパフォーマンス低下なのか
- 何と比較して、どの程度パフォーマンスが低下しているのか
- 特定の機能やタイミングでパフォーマンスが低下しているのか
ここでは例として、「顧客データの処理時間が、先月の平均値と比較して10秒遅延している」という問題を出発点と設定します。このように問題を明確化することで、なぜなぜ分析のスタートラインを正しく切ることができます。
ステップ2. 問題に対する原因を分析する
次に、定義した問題に対して「なぜ?」と問い、考えられる原因を分析します。この段階では、可能性を狭めずに広く原因を洗い出し、直接的な原因を特定することが重要です。顧客データ処理遅延の問題を例にすると、次のような原因が考えられます。
- 顧客データベースへのアクセス負荷が増加しているため。
- 顧客データのデータ量が大幅に増加しているため。
- 顧客データベースにデータ不整合やエラーが発生しているため。
- システムのアップデートにより、データ処理プログラムの効率が低下しているため。
ひと通りリストアップしたうえで、それらが本当に原因の一端となっているのかを検証します。
たとえば、アクセス負荷についてはアクセスログなどを確認し、アクセス数の実態を調べる必要があるでしょう。ここでは、「顧客データベースにデータ不整合が発生していた」ことが確認でき、これが主原因と判明した前提で解説を進めます。
ステップ3. 原因に対する原因を繰り返し分析する
続いて、特定した原因に対して「なぜ?」と繰り返し問い、原因を深掘りしていきます。「なぜ?」を繰り返す回数は、5~7回ほどが目安とされています。ただし、これは目安であり、納得できる結論にたどり着くまでは繰り返すことが大切です。
たとえば、「顧客データベースにデータ不整合が発生していた」という原因をさらに深掘りすると、次のような分析結果が考えられます。
Q:なぜ、顧客データベースにデータ不整合が発生していたのか?
→複数のシステムが同時に同じ顧客データを更新しようとしたため。
Q:なぜ、複数のシステムが同じ顧客データを同時に更新しようとしたのか?
→データ更新時の排他制御(複数の処理が同時にデータを更新しないように制御する仕組み)が適切に実装されていなかったため。
Q:なぜ、排他制御が適切に実装されていなかったのか?
→排他制御を設計する段階で、その必要性が認識されていなかったため。
Q:なぜ、設計段階で排他制御の必要性が認識されなかったのか?
→要件定義において、排他制御に関する記載がなかったため。
Q:なぜ、要件定義において排他制御に関する記載がなかったのか?
→システムにおける同時アクセスのリスクが評価されていなかったため。
Q:なぜ、同時アクセスのリスクが評価されなかったのか?
→同時アクセスのリスクに関する専門知識がチームに不足していたため。
Q:なぜ、同時アクセスのリスクに関する専門知識がチームに不足していたのか?
→同時アクセスに関する知識の共有や教育が適切に行われていなかったため。
このように、「原因の原因」を繰り返し掘り下げながら問題の本質に近づくのが、なぜなぜ分析の特徴です。
ステップ4. 根本原因を特定し対策を講じる
そして、当初の問題に対する根本原因を特定し、対策を講じます。深掘りした原因の中から、問題に対する合理的な原因を見つけ出し、その解決につながる対策を考えることが重要です。
たとえば、先ほどの例では「同時アクセスに関する知識の共有や教育が適切に行われていなかった」が根本原因といえるでしょう。
このため、排他制御の必要性が要件定義や設計に反映されず、結果として実装されなかったのです。また、レビュー工程でも同様の理由により見逃されたと考えられます。
整理すると、この問題に対しては3つの対策を講じるのが良いでしょう。
- チームに対するトラブル事例の周知や教育を強化し、同時アクセスに関する理解を深める。
- 要件定義の段階で同時アクセスのリスクを評価し、必要な排他制御を含める。
- 設計レビューを実施し、排他制御の必要性を確認するチェック項目を追加する。
このように、「なぜ?」を繰り返して問題の解決を図るのが、なぜなぜ分析です。
3.なぜなぜ分析を成功させるための6つのポイント
なぜなぜ分析を取り入れているものの、実際には「上手くいかない」と悩む方も少なくないのではないでしょうか。
なぜなぜ分析は問題解決に有効な手法ですが、ポイントを押さえないと有効に機能しません。そこで、なぜなぜ分析を成功させるためのポイント6つを押さえておきましょう。
3-1 問題を具体的に定義する
なぜなぜ分析の出発点となる問題は、具体的に定義しましょう。
なぜなぜ分析が上手くいかない要因の1つは「問題があいまい」ということです。問題があいまいだと方向性が正しく定まらず、原因を正しく分析できません。
「いつ問題になるのか」「誰にとって問題になるのか」「それは本当に問題といえるのか」など、問題自体を掘り下げるところから始めましょう。
3-2 客観的な視点で分析する
なぜなぜ分析では、客観的な視点で分析することが大切です。
主観や憶測が入ると原因分析の精度が下がり、信頼性の低い分析結果となってしまいます。客観的なデータを活用しつつ、チーム全体で意見を出しながら分析を進めましょう。
たとえば「システムの遅延」を原因とする場合、具体的なパフォーマンス指標で遅延の実態を示せる必要があります。
また、「分かりづらい」「使いづらい」といった、人によって解釈が分かれる主観的な表現は避けましょう。
3-3 個人の問題で片づけない
なぜなぜ分析が上手くいかないケースの1つは、問題を個人に押し付けてしまうことです。個人の問題で片づけると不和を生みやすい上に、個人への注意・指導にとどまってしまい、根本解決にはつながりません。
「個人」ではなく「プロセス」に焦点を当てることが大切です。たとえば、「Aさんのレビュー品質が低い」と考えるのではなく、「レビューの手順や基準に不備がある」のように考えると良いでしょう。
3-4 問題と原因の関係を検証する
なぜなぜ分析が上手くいかない要因の1つに、問題と原因が正しく紐づいていないまま進めてしまうことがあります。
たとえば、システム遅延の原因を「サーバーのスペック不足」と安易に決めつけてしまうのはNGです。
実際には、システム設計に不備があるケースも考えられます。問題と原因が本当に紐づいているのか、しっかりと検証し、分析の精度を高めることが大切です。
3-5 根本原因の特定まで深掘りする
なぜなぜ分析では、表面的な原因分析で終わらせず、根本原因の特定まで深掘りしましょう。本当の根本原因を見つける前に終わらせると、有効な対策にはたどり着けません。
たとえば、「テストケースの不足」が問題だとしても、その原因が「作成フォーマットの不備」なのか、「作成時間の不足」なのかによって取るべき対策は異なります。
この掘り下げが不十分だと、実態とは食い違う対策を講じることになりかねません。これ以上掘り下げられないかを常に問い、根本原因をしっかり特定することが大切です。
3-6 分析しただけで終わらせない
なぜなぜ分析を行っただけで満足してしまい、実際の改善につながらない失敗ケースも少なくありません。
分析結果を活かすためには、原因と対策を全体に共有し、具体的なアクションにつなげることが大切です。
対策の実施日程を決め、対策状況や効果のモニタリングを継続的に行っていくと良いでしょう。期待した効果が得られない場合は、再分析や対策の見直しも必要です。
まとめ
なぜなぜ分析とは、トヨタ自動車が生み出した問題解決における分析手法です。
問題に対する原因を「なぜ?」と繰り返し問うことで、根本原因を究明します。あらゆる業種・分野に活用できる手法ですが、成功させるには正しい手順で進めることが大切です。
なぜなぜ分析をビジネスに取り入れる際は、今回の内容をぜひ参考にしてください。
また、本記事でご紹介した「なぜなぜ分析」についてより理解を深めたい方は、バルテスの専門講師によるオンライン講座にご参加ください。
講座内では、サンプルデータを用いての分析演習や、事例を用いた「なぜなぜ分析」の具体的なやり方など、実践的な内容を提供しています。
過去にご参加いただいた方にも「とにかく分かりやすい!」と大好評をいただいておりますので、この機会にぜひお申込みください。