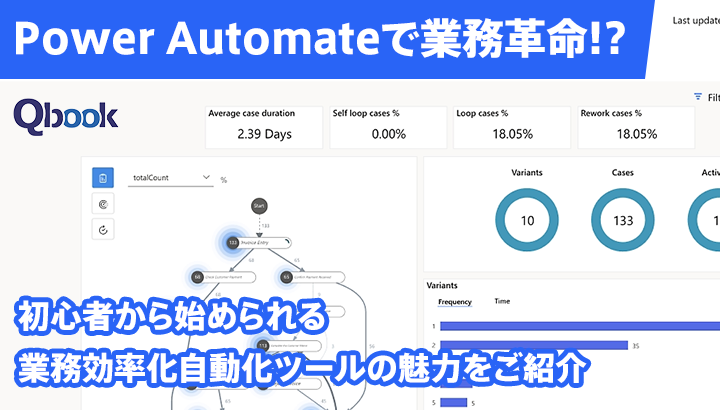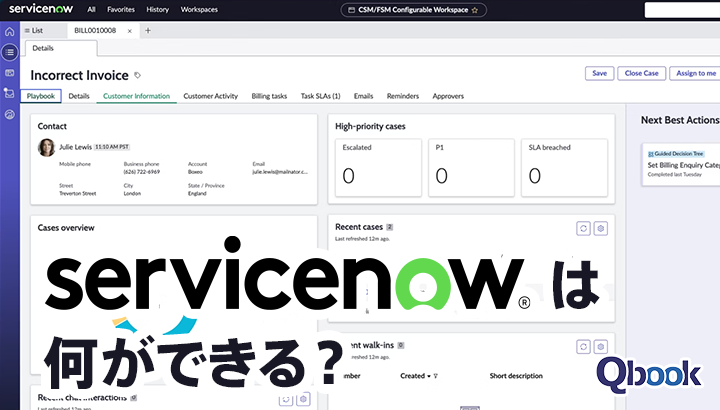企業や官公庁ではさまざまな種類のサーバーが利用されています。メールの管理を行なうメールサーバー、ホームページを設置するためのWebサーバー、ファイル共有のためのファイルサーバーなどその種類は多様です。
現在、サーバーにはオンプレミスとクラウドの2種類が存在します。オンプレミスとはサーバーやネットワーク機器を自社の建物内に設置・運用していく形態であり、それに対しクラウドはサーバーがネット上に存在し、ハードウェアを持つ必要がありません。
かつては自社にサーバーマシンを置き、自身らで管理するのが当たり前でした。しかし近年クラウド技術の発達により、必ずしもサーバーを自社内に持たなくてもよくなりました。
最近では、多くの企業がオンプレミスの環境からクラウドのサーバーへ移行する傾向にあります。
かといって、すべてのオンプレミスのサーバーが無くなったかと言うと決してそのようなことはありません。両者にはそれぞれ長所・短所があるため、運用する側はそれをよく見極めながら賢く利用するようになったと言えるでしょう。費用、セキュリティ面、カスタマイズ性においてそれぞれ違いがあります。
本記事では、オンプレミスからクラウドに移行するメリット・デメリットから、クラウドへの移行を検討すべきもの、移行の流れを解説していきます。
オンプレミスとクラウドの違いについては以下の記事をご覧ください。
- もくじ
1.オンプレミスからクラウドへ移行するメリットとデメリット
とても便利なクラウドシステムですが、完璧というわけではありません。当然のことながらメリットがあればデメリットが存在します。
オンプレミスからクラウドに移管することによるメリット・デメリットについて解説します。
1-1 クラウド移行のメリット
クラウドへ移行するメリットとしては主に以下の7つが挙げられます。
- 初期費用無料が一般的であり、低コストでスタート可能。
- 必要な時に必要なだけサーバー増減が可能。
- サーバーマシンやソフトのインストールが不要ですぐに利用できる。
- 障害に強く、ダウンしても自動的に復帰できる。
- 施設が堅牢な建築物内にあるため自然災害に強い。
- メンテナンスの必要がない。
- OSやアプリが自動アップデートされ、常に最新のものが使える
1-2 クラウド移行のデメリット
クラウドへ移行するデメリットとしては主に以下の4つが挙げられます。
- カスタマイズや設定の自由度が低い。
- ローカルなネットワークとの連携が難しい。場合によっては不可能なこともある。
- OSやアプリが自動アップデートされるため、特定のバージョンに依存した環境を構築したい場合に不便。
- 特定の企業に依存しすぎた場合、その企業が倒産するなどのトラブルが発生した際のリスクがかなり大きい。
2.クラウドへの移行を検討すべきもの
多くの企業はもともと自前でオンプレミスのサービスを持っていたため、それを徐々にクラウドサービスに移行していっているというのが現状です。
この章では、どのようなものをクラウドに移行すると良いのかを解説していきます。
★3種類のクラウドサービス
一般にクラウドと呼ばれるサービスは、大きくSaaS、PaaS、IaaSの3つに分けられます。
- SaaS...Software as a Serviceの略で、インターネットを経由してソフトウェアを提供するサービスです。代表的なものとしてはGoogle Apps やSalesforce、マイクロソフトのOffice365といったものが挙げられます。
- PaaS...Platform as a Serviceの略語でプラットフォーム一式を、インターネット上のサービスとして提供する形態のことを指し、主にソフトウェアベンダなどが活用するサービスです。
- IaaS...Infrastructure as a Serviceの略で、インターネット上のサービスとして、インフラを提供するサービスです。有名なサービスとしてはGoogle Compute Engine や AWSのElastic Compute Cloud (EC2)といったものが挙げられます。
一般的に企業及び官公庁が導入するクラウドは、SaaSおよびIaaSです。
テキストソフトや表計算ソフトなどビジネスで頻繁に使用するツールは、クラウドに移行すると良いでしょう。
例えば、Office365(代表的SaaS)があります。このシステム導入のメリットはかつてMicrosoft Officeのインスト―ル・管理のためにオフィス内のPC一台一台にCD-ROMやDVDなどのメディアを介さなければならなかったのが、ネットを介してインストール・ライセンス管理が簡単にできるようになりました。
さらに、SharePointのようにオンプレミスのサーバーでの運用・管理がとても手間であったグループウェアの管理も実に容易になるため、その様な負担に悩んでいた企業は積極的に取り入れることによりシスアドの業務やサーバー管理のコストを大幅に削減することができます。
現在もDVDなどのメディアでOfficeを使用していたり、オンプレミスのWindowsサーバーを利用していたりするような企業は、管理の手間などを考えるとOffice365に移行するのが良いでしょう。
また、GoogleやSalesforceのようなサービスはそもそも最初からクラウドで使用することを前提としているため、このようなサービスを導入することはクラウドサービスを導入することに他なりません。
そして、IaaSも検討してみましょう。Google Compute Engine や AWSのElastic Compute Cloud (EC2)などのIaaSは状況に応じてサーバーの性能やストレージの容量を自在に拡縮できます。Webでのサービスを主体としキャンペーン時期などにアクセスが一気に増大する可能性があるコンシューマ向けのECサイト運営会社などには、一時的にサーバーの容量を増大させるためなどに便利なサービスです。
そのため、ECサイトのサーバーもすべて社内に置くのではなく、一部をクラウドに移行すれば費用の面や管理の手間を考えてもとても効果的です。
3.オンプレミスからクラウドへ移行する流れ
ここではオンプレミスからクラウドに移行する具体的方法について説明します。
オンプレミスからクラウドへの移行は二段階の「クラウド化」を経る必要があります。詳しく解説していきます。
3-1 プライベートクラウド化する
第一はプライベートクラウド化です。もしオンプレミスのサーバー環境が物理サーバー上に直接構築されていたなら、VMWareなどを用いて作られた仮想環境上に移行させます。このような環境のことをプライベートクラウドと言います。一見は無意味に見えますが、仮想化によって障害時の復旧が容易になり、一般クラウドへの移行を容易に行えるようになるというメリットがあります。
3-2 パブリッククラウド化する
第二は一般のクラウドへの移行、つまりパブリッククラウド化です。プライベートクラウド化したものをAWSなどのサービスに移行するものですが、プライベートクラウドが構築されていればツールを使って簡単に移行できます。
ただし機密情報の入ったサーバーなどのように、セキュリティやコンプライアンスの関係上社外に持ち出されることが禁止されている情報が入ったサーバーはパブリッククラウド化してはいけません。また、中には社外に持ち出せても費用対効果を考えるとむしろ高コストになるようなサービスもあるので、その様な場合も移行する必要はありません。
まとめ
オンプレミスとはサーバーやネットワーク機器を自社の建物内に設置・運用していく形態であり、クラウドはコンピュート(計算)、ストレージ、ネットワークといったコンピューターリソースを、インターネット経由で提供するサービスです。
電車に例えるのならばクラウドは目的地まで最短の時間で到着できる特急電車、オンプレミスは各駅停車する普通電車に例えることができるでしょう。どちらか一方だけでは不便だったり、目的を達するためには不十分だったりします。
すべてをクラウド化することは必ずしも最善の方法ではなく、状況に応じてオンプレミスと使い分ける方が良いことが分かります。
「卵は一つのカゴに盛るな」という英語の格言があります。これは万が一のことを考えリスクを分散させるべき必要があるという意味でしばしば用いられるものですが、これはクラウドとオンプレミスの使い分けについても適用できる考え方です。
従来のネットワーク管理者の仕事はオンプレミスの環境を管理することしたが、クラウドが追加されたことにより、費用対効果や管理の手間を考慮した上でそれらを使い分ける必要が出てきました。サーバごとにクラウドかオンプレミスかを適切に選択していくことが、今後ますます求められていくことでしょう。