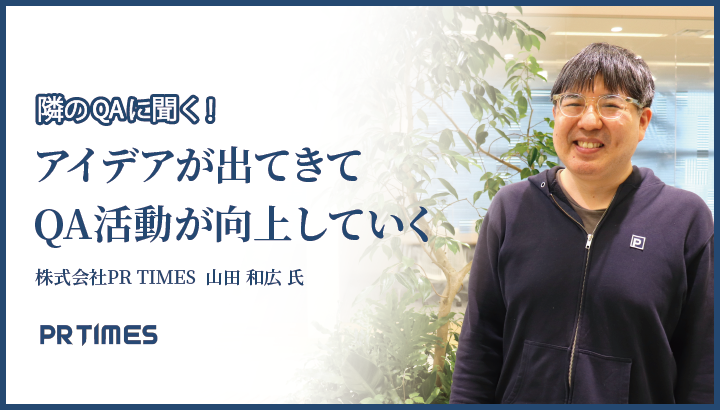さまざまな現場でQA業務に携わっている方々の「声」をお届けする『隣のQAに聞く!』。現在多様なオンラインサービスがリリースされ、社会のデジタル化が急速に進んでいます。同時にサービスやソフトウエアの品質への関心も高まりを見せており、QA・品質向上の重要性は増すばかりです。
そんな中、他のチームでは、どのようにQA業務を実施しているか、気になっているエンジニアの方も多いのではないでしょうか?
本記事では、QAに取り組む上で必要となることや「想い」などを伺い、皆さまにお伝えします。今回は株式会社PR TIMESの山田 和広さんに同社のQA活動についてお話をいただきました。
今回インタビューを受けてくださった方
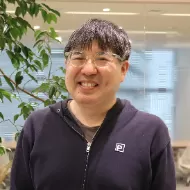
- 山田 和広 氏
株式会社PR TIMES
開発本部QAチームマネージャー
2014年にPR TIMESにフロントエンドエンジニアとして入社。開発部門でスクラムマスター等数多くの経験を積み、2019年に発足したQAチームに加わった。現在は豊富な知見・経験と心理学の知見を活かしてQAチームマネージャーとして同社プロダクトの品質向上への取り組みをリードしている。
- もくじ
1.バージョンアップを続けていくために専任のQAチームを置く

――フロントエンドエンジニアからQAへと移った理由は何だったんでしょうか?
私はエンジニアとして経験を積む他にも、関連する学びの幅を広げていくことが好きで、UX/UIや心理学など興味がある領域を学習していました。QAに入ったのは、そのようにして身につけた自分のさまざまな知見を活かせると考えたからです。
実はそれ以前、当社の内部にはQAの職種がありませんでした。テストは開発したら全てエンジニア自身が行っていたのです。自分で開発したものを自らがチェックするスタイルでは不具合も起きやすくなりますから、当然、社内にはQAチームを作ってしっかりテストしようという流れがありました。そこからQAチームがスタートしています。
PR TIMESがさまざまな開発をしていることは、まだ社外ではあまり広く知られていません。私たちは「PR TIMES」サービスに機能を増やしたり、より使いやすくしたり、新しい価値を加えたりしたいとの想いを込めて日々研究開発を進めています。そんなバージョンアップを続けていくために専任のQAを置くことになったわけです。
――プロダクトに新しい価値や機能を加えると開発の規模が大きくなり、QAの重要度が増すと考えてのことだったのですね。
はい。PR TIMESのミッションは「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」です。PR TIMESを使っていただくユーザーが行動者になっていただける、情報のインフラになることを目指していますので、QAチームは不具合を見るだけでありません。プロダクトに新たな価値を追加して魅力的なものにしていくために、ユーザビリティを含めて幅広く確認をする位置づけとなっています。
――現在、御社ではどのような体制でQA活動に取り組まれていますか?
今、QAチームは開発本部の中に存在していてメンバーは4名います。当社CTOの方針で開発スピードを上げていることもあり、QAもそれに追いつくためさまざまな施策を行っている段階です。それもあってメンバーは増やしたいと思っています。
――コロナ禍ということもあり、なかなかコミュニケーションが難しい面がありますが、何か工夫はされていますか?
隣にいればすぐ話せますが、リモートだと難しいことがありますね。私たちは対面でのコミュニケーションを重視しながら、Slackも使って繋がりを保っています。それから、QAチームでは週次で30分スタッフミーティングをして相談をしたり、QA活動の中で得た新しい知見を共有する場を設けたりしています。
――QA業務において何か工夫されていることはありますか?
開発最初の要件定義、仕様を詰める段階から最後にリリースするところまで一通り全ての工程に関わっていることだと思っています。
まず、PDMが中心になって要件定義するとき、QAが入って全体のチェックをします。続いてデザイナーがデザインを起こしますが、この段階にもQAチームが入り「デザインQA」という形で見ます。まだ動かない静止画の段階ですが、ユーザビリティやシステム・サービスとしての一貫性などを確認します。これが「OK」になると開発に回ることになります。
次に、開発できた段階でQAが入り、動作させてユーザビリティをチェックし、不具合がないか、仕様通りに作られているか検証します。ここで「OK」になってリリース日程を調整して本番に出します。さらに、"本番のQA"という形でチェックをしてQAチームが完了のOKを出す形です。こんな流れで開発の最初から最後までQAチームが関わっています。
――なるほど。「デザインQA」をユーザビリティ重視で行うことで、デザインが大幅に変わることはありますか?
デザイナーも、UX/UIやユーザビリティを大切にしていますので、180度変わることはほとんどありません。細かいポイントを指摘することが実際には多いですね。
2.不可能だったことが可能になる過程が見られるのがQA業務の魅力

――QAをされていて、どんなときに業務の魅力を感じますか?
プロダクトが良くなっていくのが見られる、開発の最初から最後まで見られることです。それまで不可能だったことが可能になり、実現していく過程を見られるのが魅力だと思います。社内に目を向けると、開発やカスタマーリレーション、営業などさまざまな部署の人たちと関われるのも良いですね。
――QA業務を進めていく上で大事なことは何だとお考えですか?
大事なのは、やはりプロダクトを好きになること、プロジェクトに愛を持つことです。好きになると、ユーザーのためにもっと使いやすくしたいとか、「こうしたらいいんじゃないか?」といったアイデアが出てくると思います。
――今、「こうしたらいいんじゃないか」と考えているアイデアはありますか?
課題としては現状、QAチームのメンバーが少ないので、テスト自動化を進めている段階です。また、エンジニア自身が必要なテストを実施してから次の工程に回すマインドを広めて、自動化を含めて上手く回すことでQAチームの負担が減る状況が作れると思っています。こうすることで、全体的な開発スピードが上げられると考えています。
PR TIMESは10年以上サービスを展開しています。古いソースコードが数多く残っているため、現在、リプレースを進めているところです。古いソースコードが残っていると、ある部分の改修で思いがけないところで不具合が発生することがあります。このような問題を早期に発見するためにも、自動化などを進めて、一つ一つ課題を解消し改善を進めている段階です。
――開発だけでなく、リプレースにもQAチームが入ることを考えると、省力化の意味で自動化は重要になってきますね。
当社では月に1回、「リファクタリングデー」を設けて、古いソースコードの不要部分を削除したり、リプレースしたりすることを進めています。サービス全体に影響が及ぶ部分を修正することもあるので、この際、PR TIMESの全ての機能を一通りチェックするのがQAチームです。この負担を下げる意味でも自動化は重要だと思っています。