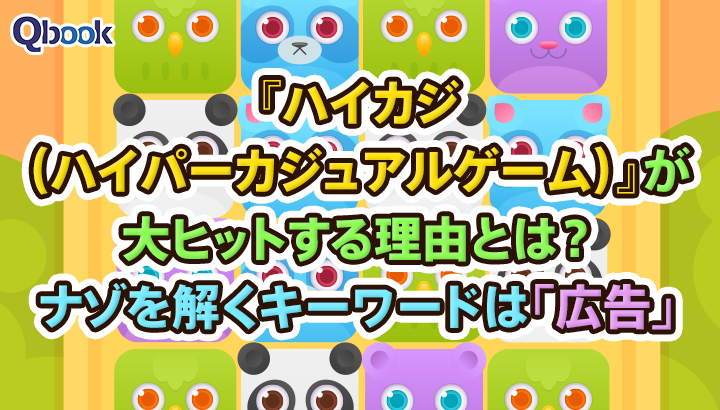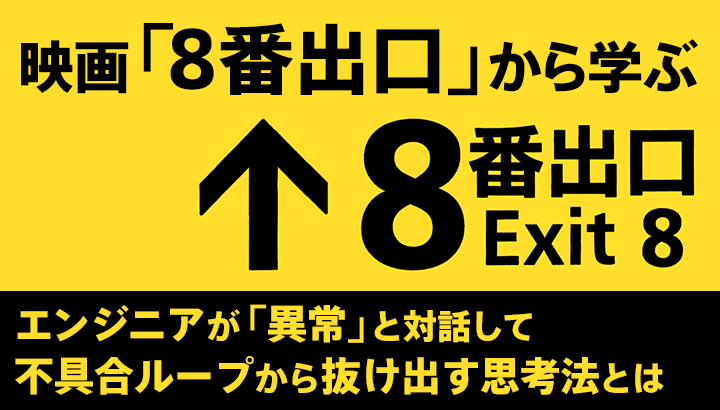近年、ゲーム機の世界は目覚ましい進化を遂げています。「Nintendo Switch」「PlayStation 5」「Xbox Series X/S」といった主要ゲーム機は高性能化が進むだけでなく、コストパフォーマンスの高さから大人気となっています。
その一方で、自由度の高さが魅力の「ゲーミングPC」や豊富なPCゲームを手元で遊べる「Steam Deck」、手軽な「スマートフォン」などゲームプラットフォームの選択肢も増加しており、ゲーマーは様々な環境で多くのゲームを楽しめるようになりました。
そこで今回は、最近の「ゲーム機の世界」をできるだけ多角的にまとめてみました。
1.2025年春現在の主要なゲーム機の特徴まとめ
まず、2025年春現在、どのようなゲーム機、ゲーム環境で人々が楽しんでいるか順不同でまとめてみました。
1-1 「Nintendo Switch」任天堂
任天堂の「Nintendo Switch」は携帯性と据置型の融合という独自コンセプトでゲーム機に革命をもたらしたといわれています。2017年3月に発売され、Joy-Conと呼ばれる着脱可能なコントローラーで様々なプレイスタイルに対応し、「ゼルダの伝説」や「スーパーマリオ」シリーズなど独自のキャラクターを活かした強力なゲームラインナップでヒットを連発しました。
インディーゲームの豊富さも特筆すべき点で、eショップを通じて多様なゲーム体験を提供しています。
2025年4月2日に、任天堂は後継機である「Nintendo Switch 2」を6月5日に発売すると発表しました。日本国内専用版の希望小売価格は税込み4万9980円ですが、おそらく、発売直後は品薄が続きそうです。
1-2 「PlayStation 5」ソニー・インタラクティブエンタテインメント:SIE
SIEの「PlayStation 5」は2020年11月の発売以来、次世代機の最前線を走り続けています。
超高速SSDによるロード時間の短縮と、DualSenseコントローラーの革新的な触覚フィードバック機能が没入感の高いゲーム体験を実現。VR技術との融合も進み、「PlayStation VR2」により臨場感のある仮想現実ゲームが楽しめるのも魅力です。
「God of War」シリーズや「Horizon」シリーズなど質の高いゲームタイトルが揃っていることで人気を集めています。
1-3 「Xbox Series X/S」マイクロソフト
マイクロソフトの「Xbox」の第四世代「Xbox Series X/S」は2020年10月に登場してから、クラウドゲーミングの可能性を広げている存在だといわれています。
Xbox Game Passを通じて数百タイトルをサブスクリプション形式で楽しめる点が特徴で、クラウドゲーミング技術の進化によってほぼ遅延のないプレイ体験を実現。XBOX独占のゲームタイトルが充実しています。オフィシャルサイトにはコミュニティなども揃っていて、ネットとの親和性をより高める工夫がなされています。
1-4 「Steam Deck」Valve Corporation
Valve Corporationが開発した「Steam Deck」は、一言でいうと「携帯ゲーム機型ゲーミングPC」。PCゲームを持ち歩ける携帯型ゲーム機です。
「Steam」は、PCゲームやPCソフトウェアなどのダウンロード販売サービスです。「Steam Deck」は「Steam」のライブラリにある数千本ものゲームを外出先でプレイできるという発想で作られており「PCゲームは家で遊ぶもの」という常識を覆したことで、一気に大人気となりました。
小さな本体でLinuxベースのSteamOSでPCゲームを快適に動作させる工夫が凝らされています。ただ、現時点では、PCの操作に慣れていないユーザーが設定しようとすると、すこしハードルが高いと感じられるかもしれません。こういった点は、いずれ改善されていくと思います。
1-5 各種「ゲーミングPC」
ゲーミングPCは自由度とカスタマイズ性の高さが魅力です。GPUやCPUを自分で選び、好みに応じて構成できるため、ユーザーにとって「理想のゲーム環境」を作れるのが最大の魅力です。
最近では、グラフィック性能に特化したNVIDIA RTXシリーズを使ったり、コスパに優れたAMDのRyzenシリーズを使ったりしたPCが人気です。高性能なゲーミングノートPCも増えており、据え置きでなくとも快適なゲームプレイが可能になっています。
また、MOD(改造ファイル)を活用してゲームをプレイしたり、ゲーム以外にも音楽やグラフィックスの制作などクリエイティブなことにも使うことができたりするなど多用途で活用できるメリットもあります。
自由度が高い反面、どうしても初期投資が高額になりやすいといわれています。また、自作を考えている場合は、パーツの選定や組み立てには、ある程度の知識が必要となります。これはやむを得ないかもしれません。
1-6 「ゲーミングスマホ」
高性能化が進むスマートフォンの中でも、ゲーミングスマホは明確な目的を持ったカテゴリです。機種としてはASUSの「ROG Phone」やnubiaの「REDMAGIC」などが知られており、冷却性能・リフレッシュレート・応答速度などを徹底的に追求した設計が特徴となっています。
ゲーミングスマホの大きな特徴の一つが冷却性能の高さです。長時間のゲームプレイでも本体が熱くなりにくいため、パフォーマンスの低下を抑えることができます。また、高リフレッシュレートのディスプレイやゲームに特化した操作インターフェースなど、ゲームを快適にプレイするための様々な工夫が凝らされています。このため、長時間、スマホで動画を閲覧するユーザーからも人気を集めています。
近年では「原神」や「Call of Duty Mobile」など、グラフィック・処理ともに高負荷なタイトルも増えており、それらを快適にプレイするために、こうしたゲームに特化した機種が求められるようになってきました。
価格帯は10万円?20万円程度と高価ですが、「スマホでありながらPC並みに遊べる」点に魅力を感じるユーザーが多いようです。さらに、配信機能や画面録画の簡便さ、SNSとの連携もスムーズな点などから、若年層を中心に確実にユーザーを増やし続けています。もし、低価格化が進めばさらに人気が高まる可能性があります。
2.ゲーム機 vs ゲーミングPC !性能とコストパフォーマンスの違い
2-1 性能・スペック
最新のゲーム機は、驚くほど高性能になっています。例えば「PlayStation 5」は8K解像度への対応や高速SSDの搭載などで多くのPCゲーマーを驚かせました。
「Xbox Series X」も同様に高性能で、4K解像度でのゲームプレイや高フレームレートに対応しています。
これらのゲーム機と同等スペックの「ゲーミングPC」を組むとおよそ15?18万円以上が必要になるとされています。ゲーム機が6?7万円で入手できるのに比べると、初期投資額は圧倒的にゲーム機が優れています。
難しいのは、単純なスペック比較だけでは不十分だということです。
ゲーム機はハードとソフトが最適化されているため、同スペックのゲーミングPCより高いパフォーマンスを発揮するケースが多いからです。
一方、「ゲーミングPC」は最先端技術を自由に導入できるなどカスタマイズ性が高いことが魅力です。また、目線を変えて、低スペックのゲーミングPCを組み、昔のゲームタイトルをプレイすることもできます。この場合、初期投資が大幅に抑えられるメリットがあります。PCゲームは過去資産が膨大なこともあり、レトロゲームを選択するプレイヤーも増えています。
2-2 コスパ分析
ここまで見てきたように、初期投資だけを見るとゲーム機が安価なことがわかりますが、長期的なコストやゲームタイトルの構成にも注目しておくとよいかもしれません。
「Nintendo Switch」は初期投資が低いうえに、家族で楽しめるゲームタイトルが多いため、コストパフォーマンスは最も高い部類に入ると思います。「PlayStation 5」や「Xbox Series X/S」は初期投資に対して圧倒的な高性能が得られますが、ゲーム価格はやや高めの傾向が見られます。
数多くゲームを楽しみたい場合は、サブスクリプションサービスを活用すれば経済的です。いずれにせよ、自分が遊びたいゲームタイトルが選択しようとしているゲーム環境で提供されているか導入前に確認しておきましょう。
「ゲーミングPC」は初期投資が高いものの、「Steam」はセールが行われるため、ゲームを安く入手できるチャンスが多く、長期的には高いコストパフォーマンスが得られる可能性があります。また、ハードを一度入手すると、パーツの交換で長く利用できるメリットも想定できます。
かんたんにまとめると「初期費用を抑えたい人」にはゲーム機、「長期的に幅広くゲームを楽しみたい人」にはPCが向いている傾向があると思います。とはいえ、自分が遊びたいゲームタイトルが存在しなければ損も得もなく、そもそも話になりません。これがコスパ計算を難しくしている理由です。
2-3 互換性
ゲームを長く楽しむために重要なのが「後方互換性」です。これは、新しいゲーム機で過去のゲームがプレイできるかどうかを示すもので、これがあることで、旧作ファンも安心して新ハードに移行できます。
後方互換性に優れているのは実はゲーミングPCです。知識は必要ですが、簡単な設定で数十年前のゲームも比較的容易にプレイできます。コンソール機では「Xbox Series X/S」が優れた後方互換性を持っており、初代Xboxのタイトルまでプレイ可能です。
「PlayStation 5」はPS4タイトルに対応していますが、それ以前となると限定的に感じられます。「Nintendo Switch」は過去機との直接的な互換性はありませんが、Nintendo Switch Onlineで過去の名作が楽しめるようになっていて、後方互換性が意識されていることがわかります。
2-4 ゲーム機市場のシェア
2025年現在のゲーム機市場シェアは、地域や用途によって大きく異なっているため、ここでは日本市場でのシェアをかんたんに見てみましょう。
『ファミ通』の発表を@DIME(アットダイム)がまとめた記事によると2024年の販売台数は「Nintendo Switch」が約310万台、「PlayStation 5」が約145万台、「Xbox Series X/S」が約11万台、「PlayStation 4」が約1.3万台でした。
2024年国内家庭用ゲームの市場規模は3013億円、ハードの販売台数はNintendo Switchが圧倒(@DIME アットダイム)
3.ゲーム開発の観点で見る、それぞれの違い
3-1 「参入障壁」の高さ
参入障壁が最も低いのはモバイルプラットフォームでしょう。個人開発者でも容易に開発・配信が可能な環境が整っています。
次いで参入しやすいのはPCです。「Unreal Engine」や「Unity」といった開発環境が無料で利用できることが参入障壁を下げているといってよいでしょう。
参入障壁が高いのは「Nintendo Switch」や「PlayStation 5」「Xbox Series X/S」といったコンソール機向けの開発です。開発キットの入手や審査プロセスが厳格といわれていますが、近年ではインディー向けのゲームを導入する流れも生まれてきているため、以前ほどではなくなってきている可能性があります。
3-2 開発コストと収益性
コンソール向けタイトルは開発コストがかかり、大規模なチームと長期の開発期間が必要です。しかし、ヒット時の売上規模も莫大で、ときには社会現象になるほどの人気を集めることから、参入する企業も多くなっています。
PC向け開発は中程度のコストで、ゲームへの早期アクセスサービスや開発費用のクラウドファンディングなどを活用して、積極的にリリースされています。
スマホなどモバイル向けは開発コストが最も低く、短期開発が可能です。最近では「ハイカジ(ハイパーカジュアルゲーム)」が人気で、「低リスクハイリターン」を実現しているケースも多く見られます。
★インディーゲームとハイパーカジュアルゲーム
近年、インディーゲームやハイパーカジュアルゲーム(ハイカジ)の市場が急成長しています。「Steam」とモバイルプラットフォームがその主戦場となっていて、シンプルながら奥深いプレイ体験を提供しています。
Steamでは、「Stardew Valley」や「Hades」といった大ヒット作が生まれ、新しいゲーム体験を求めるプレイヤーの支持を集めています。
新興市場からも参入しやすいため、今後さらに数が増えていくことでしょう。インディー開発者にとってモバイル市場は魅力的ですが、競争が非常に激しいのも特徴の一つといます。
4.ゲームの未来を予測してみる
4-1 ゲーム業界の未来
未来のゲーム業界のキーワードは「クラウドゲーミング」「VR/AR技術」「AI」になってくると思います。
5G普及によりクラウドゲーミングが発展し、高性能な機器がなくても高品質のゲームが楽しみやすくなる可能性があります。また、没入感を高めるVR/AR技術により、より臨場感のあるゲームが楽しめるようになりそうです。映画「レディ・プレイヤー1」には「オアシス」というVR世界が登場しますが、こういった世界を体験できる日が近づいてきていると感じます。
AI技術の発展は、主にゲームのストーリーに影響を与える可能性があります。これは本章の末尾で述べたいと思います。
4-2 ゲーム機の未来
ゲーム機のハードとしての形は、大きく多様化していると言えるでしょう。「Nintendo Switch」のように携帯と据え置きのハイブリッドタイプもあれば、「Steam Deck」のような携帯ゲーム機型のゲーミングPCもあり、さらにゲーミングスマホのようにゲームとスマホを融合させたような端末もあります。
このような多様化の流れの中にあっても、ゲーム機は多機能で多用途に使えるデバイスと特定用途に特化したデバイスの二方向に分かれつつあるようです。
ただし、今後はクラウドゲーミングの普及によってゲーム機ごとの境界が曖昧になっていく可能性もあります。
4-3 ゲームソフトの未来
AI技術の発展により、ゲームの世界もよりダイナミックで予測不可能なものへと変化しつつあります。
ゲーム内のNPC(ノンプレイヤーキャラ)の動き、ストーリーの分岐、さらにダイアログまでAIが生成する時代が始まりつつあります。具体的には、NPCの行動がより自然になり、プレイヤーの行動に応じて動的にストーリーが変化するゲームが増加するでしょう。
プラットフォームの多様化に伴って、ゲームソフトの形態も複雑化しています。かつてはパッケージ版が主流でしたが、今やダウンロード販売やサブスクも当たり前です。クロスプラットフォーム対応も進んでいることから、しばらくは状況が見渡せない多様性の時代がつづくことが予想できます。
まとめ
ゲーム環境は多様で魅力的です。
「Nintendo Switch」「PlayStation 5」「Xbox Series X/S」「Steam Deck」「ゲーミングPC」「スマホ」、それぞれに個性と強みがあり、ユーザーのライフスタイルに合わせた選択が可能になっています。
「ぜんぶ欲しい」と思われた方も多いのではないでしょうか。
今後もビッグタイトルが市場を牽引する時代が続くと予想されます。自分が何でどのように遊びたいかを考えて、自分にあったゲーム環境を選択したいですね。